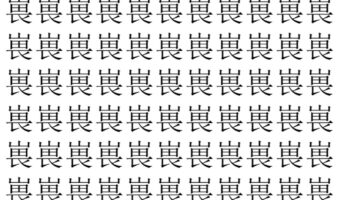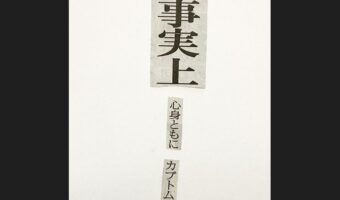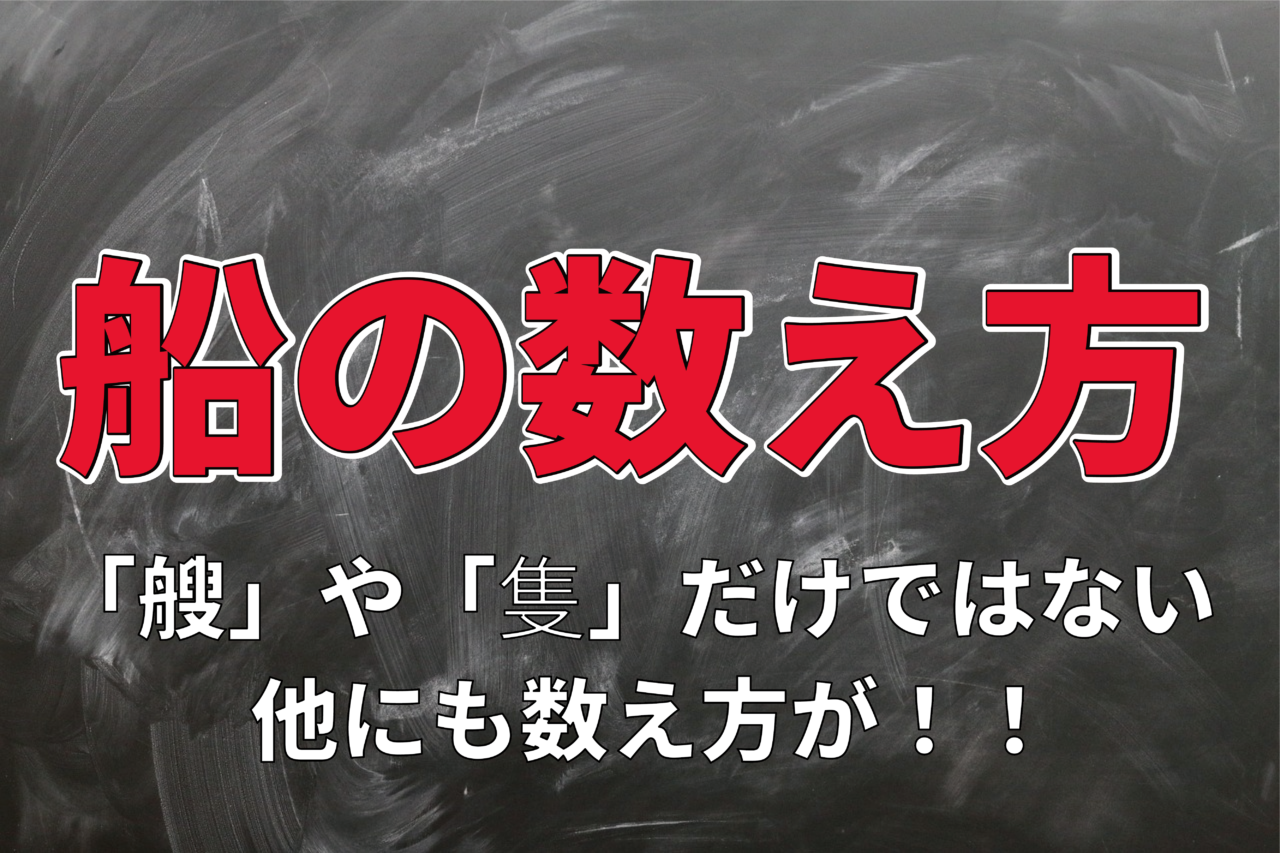
船は「一艘二艘」、もしくは」一隻二隻」と数えられます。
これらの数え方には厳密なルールが設けられていないよう。
そのため、どのような使い分けをするのがいいのかがわかりにくくなっています。
船は形状も大きさによって数え方があり、「艘(そう)」や「隻(せき)」以外の数え方がされることもあります。
そこでここでは、船の数え方について解説します。
目次
船の数え方のルール

船の数え方には、実のところ厳密なルールはありません。
ただし、大きさや高さ、形状や用途で使い分けされていることもあります。
大型船は「一隻二隻」と数え、小型船の数える際は「一艘二艘」が用いられる傾向にあります。
とはいえ、数え方を逆にされることもありますが・・・、ルールがないのでそれらも間違えではありません。
船の数え方はたくさん!

船の数え方は種類が豊富です。
数字の後ろにある単位を助数詞というのですが、船にはその助数詞がたくさんあるのです。
有名なのは、艘(そう)や隻(せき)
・艘(そう)
・隻(せき)
艘は小さい船で隻は大きい船に使われることが多いですが、厳密にどちらを使うのが正しいということはありません。
帆掛け船や和船などの小型船は艘で、貨物船やタンカーなどの大型船を隻と数えることが多くなっています。
競う船は、艇(てい)
ボートやヨットなど小型船の中でも、さらに小さい船を数える際には一艇二艇といったように「艇」で数えることがあります。
競艇などレースで用いられる船に使われる単位となっており、他にもスポーツなどに使われる船の多くは艇で数えます。
同じ理由から、水上バイクなども艇と数えることが多くなっています。
軍艦に使う、艦(かん)
軍艦や駆逐艦、航空母艦などの船の数え方は艦となっています。
「艦」という言葉自体に「いくさぶね」という意味があるため、主に軍事用やそれに準ずる船の数え方となっています。
そのため、それらに属する船なら大小に関わらず単位は艦となる傾向にあります。
杯や盃が使われることも
漁船などは杯や盃が使われることもあります。
ただし、この数え方は一般的なものではなく、いわゆる業界用語的な存在です。
船という言葉自体に「液体を入れておくもの」という意味があることから、杯や盃が使われるようになったのではないかという説があります。
船をそのまま使う場合も多い
船舶免許の試験などでは、「船(せん)」という助数詞が使われます。
名前が明確にわかっている場合や名前がとても重要な場合は、伝え方の一種として「船」という単位を用いることもあります。
船舶試験などの問題文では「2船の間を航行するばあい・・・」となっていることがあります。
普段はあまり使わない数え方も!

主には、艘や隻や船などで数え方をすることが多いのですが、あまり一般的ではない数え方も存在します。
一例を上げると「葉・本・枚・台・床・帆」などです。
葉は主に小舟などの数え方、本は丸太船など、枚や台や床は筏(いかだ)を数える際の単位となります。
帆は、帆掛け船が帆を張った状態を表す際に使います。
まとめ
船の数え方は豊富にあります。
一艘二艘や一隻二隻の他に、艇や艦などもありますよ。
船が大型なら「隻」で、小型船は「艘」を用いるともされますが、厳密なルールというわけでもないため大型船が「艘」と数えられる事もあります。