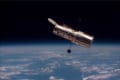クスクスという動物は、「クスクス」という笑い声のようなかわいいネーミングをしています。
この動物はオーストラリアなどに生息する雑食動物で、カンガルーやコアラと同じ有袋目に分類されています。
今回はそんなクスクスについて見ていきましょう。
目次
珍獣クスクス

クスクスは、哺乳網有袋目クスクス科クスクス属に含まれる動物の総称です。
「カスカス」や「ユビムスビ」とも呼ばれています。
まずは珍獣と言われる、クスクスの特徴を見ていきましょう。
クスクスの生息地
クスクスはオーストラリアの北端部のヨーク岬半島、ニューギニア島の熱帯林、マルク島、スラウェシ島、ソロモン諸島、モルッカ諸島などに生息しています。
クスクスの大きさや外見
クスクスの頭から胴体までの長さは、27~70㎝、尾の長さが24~48㎝、体重は5kg前後です。
胴体は体毛で密に覆われていて、尾には体毛で被われていない裸出部があります。
基本的にメスよりもオスの方が大きく、頭は丸くて小さく、目は大きいです。
また、耳は短くほとんど毛に隠れていて見えません。
メスの腹部にはカンガルーやコアラのように、育児嚢(いくじのう)があり前方に開口しています。
そして前肢の指には鉤状の爪が生えているため、木登りが得意です。
後肢の第1趾には爪がなく、他の指と対向させることができるため、枝をつかみやすいようになっています。
クスクスの生態
クスクスはタウリン、疎林、ユーカリ林などに生息していて、主に木の上で生活しています。
木の葉を主食としており、果実、樹皮、卵なども食べます。
そんなクスクスの腸は、植物の葉を消化するために長くなっています。
また、単独生活が基本のクスクスは、夜行性で動きは緩慢です。
クスクスという不思議な名前

クスクスという名前はどのような意味があるのでしょうか?
笑い声のようなその名前の由来について見ていきましょう。
名前の由来
「クスクス」は、現地の言葉で『おなら』という意味です。
クスクスは臭腺を持っており、糞尿を使って臭いをつける行動をすることから、「クスクス」と名付けられたのではないかといわれています。
クスクスの別名
クスクスの別名は、「カスカス」や「ユビムスビ」と呼ばれています。
足の第2指と第3指が癒合しているところから、「ユビムスビ」とも呼ばれるようになったそうです。
クスクスの仲間たち

クスクスは総称名で、7~10種類に分類するそうです。この項目では、クスクスの仲間たちを紹介したいと思います!
ブチ模様がかわいい「ブチクスクス」

ブチクスクスは、ブチ模様が特徴的なクスクスです。
体形は原猿類、尾の形はリングテイルに似ており、顔は丸く、耳は小さいです。
尾はとても長く、ものに巻き付けることができます。
そして羊毛のような毛をしており、メスはオスよりも大型です。
体色はメスでは灰白色ですが、オスの背中にはブチの模様があります。
茶色い毛だけど「ハイイロクスクス」

ハイイロクスクスは、体長が32~65㎝で、尾長は24~61㎝のクスクスです。
名前は「ハイイロクスクス」ですが、実際の体毛は茶の毛をしています。
名前は違うけどクスクスの仲間「フクロギツネ」

クスクスという名こそついていませんが、フクロギツネはクスクスの仲間です。
三角形の大きな耳を持ち、キツネに似ていることから「フクロギツネ」と名付けられました。
オーストラリアやタスマニア島などに広く分布しており、体毛は厚くて密生しています。
毛色は、灰色、褐色、黒色、クリーム色など様々で、タスマニア島のフクロギツネは黒色や灰色になる傾向があり、オーストラリア本土よりも体が大きいです。
まとめ
クスクスは、カンガルーやコアラと同じように有袋類であり、夜行性特有の大きな目が特徴です。
その名前は、「おなら」が由来となっており、笑い声や食べ物の「クスクス」とは特に関係ありません。