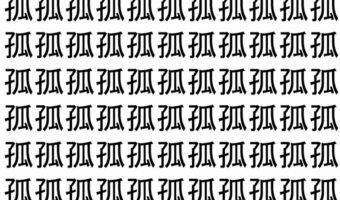太陽の光に関連する言葉として「ご来光」「初日の出」「ご来迎」があります。
これらはいずれも、太陽の光が差し込むことを意味する言葉です。
しかし、条件によって用いられる言葉が異なります。
そこでここでは、「ご来光」や「初日の出」、「ご来迎」の違いについて見ていきましょう。
対象となるもので違いで名称が変わってきているようですよ。
目次
「ご来光」とは

まずは、「ご来光」がどのような意味なのかを見ていきましょう。
「日の出」のこと
ご来光は、日の出のことです。
特に高い山の頂上などで見る荘厳な日の出のことを指します。
仏様の「後光」になぞらえられた「ご来光」
このご来光は、仏様の背中から放射されるとされる光の「後光」になぞらえた表現とされています。
そのため、日の出とともに仏様がやってくるという信仰に基づいているともされます。
「初日の出」や「ご来迎」との違い

ここからは、「初日の出」や「ご来迎」との違いを見ていきましょう。
「初日の出」とは
初日の出は、元日の日の出のことです。
日本では、年神様が初日の出と共にやってくると信じられていました。
その年神様の降臨を拝む文化の影響で、初日の出を拝む文化が広まったとされています。
元日の朝つまり元旦に天皇が年災消滅と五穀豊穣を祈るために行ってきた宮中祭祀「四方拝」が民衆に広まった行事と考えられています。
民衆による初日の出の風習は、江戸時代までは江戸周辺で行われ、明治以降に全国的に広まったとされています。
当時は、初日の出を目にして1年の健康と幸運を祈願していました。
ご来光は、時期を問わず、高い山で見る日の出です。
逆に初日の出は場所を問わず、元旦の日の出をあらわしています。
また、ご来光という名前は仏教に通じるものがありますが、初日の出は神道に基づく風習となっています。
「ご来迎」
ご来光に似た言葉で、「ご来迎」というものもあります。
ご来迎は、ご来光の意味で使われる事もありますが、主には違う意味で用いられます。
ご来迎とは、高山の山頂に足元に霧がかかった状態で背中に太陽の光を受けることで、映し出される自分の影ことです。
この現象は太陽が低い位置にある、日の出や日没の頃に発生しやすいとされています。
ご来迎は、まるで自分の影に後光が差し込んでいるかのような状況という事になります。
日の入りは怪しい時間?

日の出は何かと縁起が良いですよね。
しかし、日の入りは古くから怪しい時間とされてきました。
特に逢魔時や黄昏時と呼ばれ、日の出とは違う意味を持っていたそうです。
逢魔時
逢魔時は、夕方の薄暗くなる、昼夜が入れ替わる時刻のことです。
かつて、この時間帯は魔物や災禍に遭遇する時間と信じられていました。
そのため、この時間の行動は避けられていたとされます。
厳密にいうと「暮れ六つ」や「酉の刻」とも呼ばれる時間帯で、現在の時刻に換算すると18時頃のこととなります。
黄昏時
黄昏時は日没直後、夕焼けの赤さが残る時間帯のことです。
古くは顔の識別がつかなくなる暗さの夕暮れ時を指していました。
その由来は「誰そ彼」という言葉にあります。
この言葉は「あなたは誰ですか」という意味があります。
向こうから来る人の顔が見分けることができなくなる、という様子から生まれたのだとか。
知り合いの顔も分からなくなる時間ということで黄昏時と呼んだのです。
なお、対になる表現に夜明け前を表す「彼は誰時」などがあります。
まとめ
ご来光も初日の出もご来迎も太陽に関する言葉です。
しかし、それぞれ対象となるもので意味が異なります。
ご来光は、高い山で見る日の出を指します。
初日の出は、元旦の日の出のことです。
ご来迎は、ご来光と同じ意味で使われる事もありますが、背中に太陽の光を受けることで、山頂付近の霧に自分の影が映し出される現象です。