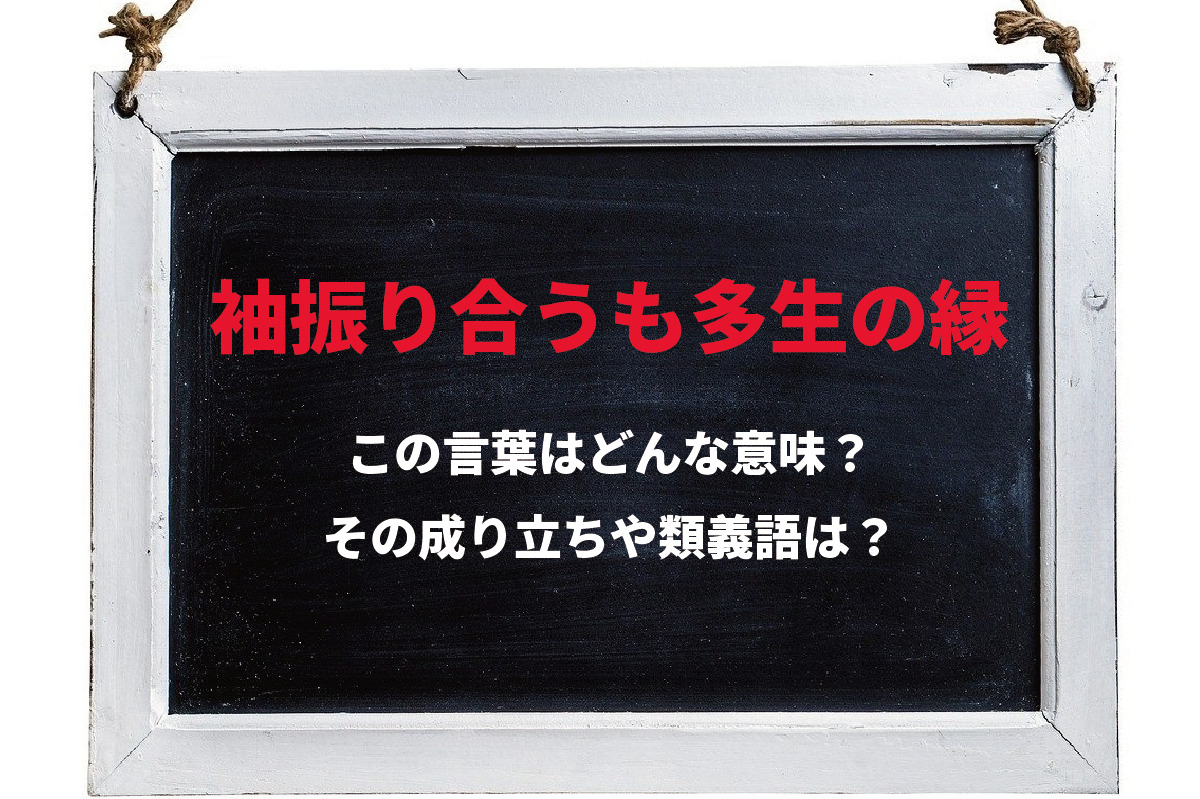
「袖振り合うも多生の縁」には、道をすれ違っただけ、なんていうなんてこともない事も、実は前世の因縁によるものだという意味合いがあります。
どのようなことも偶然ではなく、縁があって起きる出来事だということになります。
ここでは、そんな「袖振り合うも多生の縁」という言葉について、意味や成り立ち等について見ていきましょう。
目次
「袖振り合うも多生の縁」とは

まずは「袖振り合うも多生の縁」という言葉の意味について見ていきましょう。
「袖振り合うも多生の縁」の意味
「袖振り合うも多生の縁」とは、道で誰か見知らぬ人とすれ違うようなちょっとしたことさえも、前世からの因縁があるという考え方から来た言葉です。
ちょっとした出会いや些細な出来事も、偶然によって起こるのではなく、前世からの縁によって引き起こされている必然として起こるという意味合いが込められています。
せっかく出会得たのだから、その縁や絆を大事にしようという意味で用いられることもあります。
「袖振り合う」とはどんな状況?
袖振り合うも多生の縁にある「袖振り合う」というのは、江戸時代などの着物を身に着けていた時代に、すれ違った際に袖動詞が触れ合うという非常にちょっとした出来事を指しています。
人によっては次の瞬間には忘れてしまう、気付きもしない事かもしれませんが、その袖同士がぶつかりあった相手というのは、前世で何かしら結びつきがあった人物だという事になります。
「多生の縁」とは

ここからは「多生の縁」が指すものについて見ていきましょう。
「多生」は仏教用語
「多生」とは、仏教用語の1つから来ているとされています。
多生が多く生きると表記するように、輪廻転生つまり生まれ変わる事を指す表現となります
「他生」や「多少」と表記されることもあるけれど・・・
「多生の縁」は「他生の縁」と表記される事もあります。
これは輪廻を指すということであれば同じ意味となります。
ただし「他生」はこの世から見て過去および未来の生、つまり前世や来世を指す言葉となります。
しかしながら、今生きている今世を指す言葉ではありません。
なので、「多生」と「他生」はイコールの関係ではありません。
なお、「多少」は同音ではありますが、多い少ないだけをあらわす語句であって、「多生」とは大いに意味合いが異なりますので「多少の縁」と表記するのは誤りとなります。
「袖振り合うも多生の縁」の類義語

最後に「袖振り合うも多生の縁」の類義語も見てみましょう。
類義語としては、「躓く石も縁の端」や「一樹の陰一河の流れも他生の縁」などがあげられます。
躓く石も縁の端
「躓く石も縁の端」とは、すべての物事には前世からの因縁が関係しているということを強調した例えです。
偶然躓いた道端に落ちている石にさえ、その人とは何かの因縁があるという事をあらわしています。
一樹の陰一河の流れも他生の縁
「一樹の陰一河の流れも他生の縁」とは、前世の因縁をあらわす言葉です。
雨を避けるために同じ木陰に身を寄せあった知らない人も、たまたま同じ川の水を汲んで飲み合うのも、すべては前世からの因縁によるものだということを言った言葉となります。
まとめ
「袖振り合うも多生の縁」は、道端で袖が触れ合うような小さな出来事でも、その相手とは前世から何かしらの因縁があるといった意味があります。
そのため、縁を大事にしましょうという意味合いで用いられることもあります。
なお、この「袖振り合うも多生の縁」の「多生」とは、何度も生まれ変わる「転生」をあらわしています。




