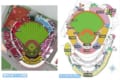百日紅(サルスベリ)は、夏から秋にかけて開花時期を迎える花です。
ピンク色の花を咲かせるこの花は、その非常に難読な漢字表記となっています。
ここでは、そんな百日紅の花の名前や花言葉などについて見ていきましょう。
目次
百日紅(サルスベリ)とは

百日紅は、ミソハギ科の落葉中高木で、別名はヒャクジツコウと呼ばれています。
特徴
百日紅(サルスベリ)は、紅色の濃淡色または白色の花を咲かせるのですが、その花びらは6枚あって縮れています。
鮮やかで美しいのはもちろん、病気にも強いこともあり、古くから庭園や公園などに植えられることが多い花です。
原産
百日紅(サルスベリ)は、中国南部原産と言われており、中国では唐代長安の宮廷に多く植えられていることから「紫薇」と呼ばれることもあります。
丈夫な植物ということもあり、日本でも多くのところで育てられてきました。
開花時期
百日紅(サルスベリ)は、夏から秋にかけて7月~10月に開花時期を迎えます。
百日紅(サルスベリ)は、中国では長い間紅色の花が咲くことがから百日紅と書き、日本でもサルスベリを漢字で書くと百日紅となります。漢字からは想像もできない読み方ということもあって、日本では難読漢字の1つとして知られていますね。
百日紅の花言葉

ここからは、百日紅にどのような花言葉があるかを見ていきましょう。
全般的な花言葉
百日紅(サルスベリ)が持つ花言葉は「雄弁」「愛嬌」「不用意」「潔白」などです。
「雄弁」は枝先に群がるように咲く華やかさが由来している他、枝を揺らすと花や葉が揺れて盛んに話しているように見えることも由来していると言われています。
「愛嬌」や「不用意」は樹皮が滑って猿も木から落ちる様子にちなんでいるのだとか。
「潔白」はある王子と恋人の伝説が由来しています。この伝説についての詳細は、後ほど詳しく見ていきましょう。
色別の花言葉はない
紅色ないしピンクといわれる百日紅の花に、色別の花言葉はありません。
そのため、どの色であっても同じ意味の花言葉を持っているということになります。
気になる百日紅(サルスベリ)の名前について

ここからは、サルスベリという名前と、百日紅という漢字表記の由来をそれぞれ見ていきましょう。
百日紅という漢字表記の由来
サルスベリは、中国では長く咲くことにちなんで百日紅と表記されます。
それが日本に伝来した結果、日本でも漢字表記では「百日紅」となっているのです。
花が長持ち説
サルスベリはとても花が長持ちします。
その花が100日にもわたり咲き続けるということから「百日」という名前が付けられました。
そこに、花の色である紅と後ろに付けて「百日紅」になったという説があります。
王子と娘の伝説
百日紅(サルスベリ)には、ある伝説があります。
その昔、ある国の王子が竜神退治の旅をしている途中、生贄にされようとしていた娘を助けました。
2人は恋に落ちたのですが、王子は「百日後に帰ってくる」と再会を約束して、旅立ってしまいました。
王子の恋人となった娘はその言葉を信じ、健気に王子を待っていたのですが・・・。
戻って来た頃には、その娘が亡くなっていたという悲しい結末を迎えました。
悲しみにくれた王子ですが、娘のことを思い埋葬してあげることにしました。
そして、その恋人が埋葬された場所に咲いたのが百日紅の花だったのです。
娘の墓所に咲いたその花には、王子との再会を誓った「百日」を由来として「百日紅」になったともされています。
サルスベリという名前の由来
日本語では、サルスベリ呼ばれているこの花の名前は、百日紅の樹皮がツルツルしているので、猿でも滑ってしまうという特性から来ています。
ところが、実際には猿は簡単に登ってしまうのだとか。
まとめ
百日紅(サルスベリ)は日本でも多くのところで植えられているため馴染みのある花です。
サルスベリという名前は、樹皮の特徴から来ているとされ、百日紅という絶対に読めないその漢字表記は中国におけるサルスベリの表記がそのまま入ってきたとされています。