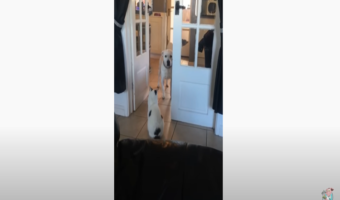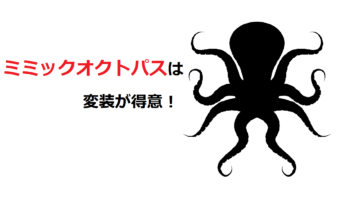野菜や果物を扱っているお店は普通、野菜屋や果物屋とは呼びません。
それらのお店は「八百屋」と表記されたり呼ばれるのが一般的です。
ではなぜ「八百屋」になったのかというと、もともとこの手のお店が青物屋と呼ばれていた歴史が関係しています。
その他、たくさんのものを扱っているところから八百という呼称が定着したという背景もあるとされています。
そこで、ここでは野菜や果物を販売するお店が八百屋を呼ばれる理由について見ていきましょう。
目次
「八百屋」という呼称が生まれるまで

八百屋とは、野菜や果物などを売るお店のことを指しています。
しかし、野菜屋や果物屋とは基本いいませんよね。
まずは八百屋という呼称が生まれた背景を見ていきましょう。
かつては「青物屋」だった
かつて、野菜や果物を扱うお店は「青物屋」と呼ばれていました。
なぜ青物屋なのかというと、野菜や果物のことを青物と昔は呼ばれていたからです。
青物を扱うお店なので、そのまま青物屋と呼ばれたというわけですね。
そしてこの青物屋、次第に省略されるようになり「青屋」と呼ばれるようになりました。
「あおや」が「やおや」に
八百屋は、「青物屋(あおものや)」と呼ばれていたものが「青屋(あおや)」となり、それが後に「八百屋(やおや)」となったと考えられています。
なぜ「やおや」と呼ばれるようになったのかというと、そこには以下のような理由があるとされます。
・藍染め屋と間違わないようにするため
・単にいいやすくするため
・扱う商品が多いため
上記のような理由から「やおや」と呼ばれるようになったと考えられてきます。
しかし。そうなってくると今度は漢字表記でなぜ「八百屋」と書くのか疑問に思う人も出てくるかもしれませんね。
そちらに関しては以下の項目で見ていきましょう。
漢字で「八百屋」と書く理由
なぜ八百屋には「八百」という漢数字が用いられているのでしょうか。
これは、日本では古くから八百という言葉には、とても数が多いという意味があるとされてきたことに由来するとされています。
代表的なものでは、八百万の神々という言葉がありますね。
この言葉は、神道における神についての考えです。
ありとあらゆるところに神々は宿っており、神は数えきれないほどいるという意味があります。
この言葉のように、八百は古くから数が多いことを指して使われてきました。
そして、野菜や果物を数多く取り扱うお店という事から、八百を用いて八百屋と称されるようになったのです。
東京の地名「青物横丁」の由来も八百屋の前身から

東京には、青物横丁という地名があります。
実は、この青物横丁という町の名前も八百屋の前身「青物」にあるとされているのだとか!
「青物横丁」という地名
東京には、青物横丁という地名があります。
「青横」と略されることもあります。
この青物横丁の歴史は古く、江戸時代に農民が青物を持ち寄って市場を開いたことがはじまりです。
その賑わいは、昭和時代の初期まで残っていたのだとか。
近年は再開発などによってその様相も変わってしまいましたが、それでも青物横丁という地名は今なお残っています。
青物横丁は歴史ある土地
この青物横丁があるのは、東京都品川区です。
この土地はかつて品川宿の南端にあたるとされていました。
ちなみに品川宿とは、東海道五十三次における最初の宿場町のことです。
かつては東海道の品川宿、中山道の板橋宿、甲州街道の内藤新宿、日光街道・奥州街道の千住宿と並んで江戸四宿と呼ばれていました。
そんな歴史ある土地にあったのが青物横丁で、古くから人々の台所として地域の食文化を支えていたわけですね!
八百屋に縁のある言葉「八百長」

日本語の中には八百屋が語源とされる言葉もあります。
それが、八百長です。
ここではそんな八百長について解説します。
八百長の意味
八百長とは、勝負事などにおいて裏で勝敗を打ち合わせておき、表では真剣勝負をしているように見せかけることをあらわす言葉です。
いわゆるヤラセ試合のことです。
八百長の2つの由来
そんな八百屋の由来には、長兵衛という人物に関する2つの説があるとされています。
1つ目の説は、長兵衛が囲碁の実力を隠していたことに由来するとされます。
かつて長兵衛という八百屋の店主がおり、趣味で囲碁を打っていました。
その実力はなかなかのものでしたが、囲碁仲間で相撲の年寄という役職を担っていた伊勢ノ海を相手にする際は機嫌を取るためにうまく負けたりしていたそうです。
それによって機嫌が良くなった伊勢ノ海に、自分のお店の商品を買ってもらっていたのだとか。
しかしある時、長兵衛が名人と囲碁を打った際、演技を忘れてつい本気になってしまいいい勝負をしてしまいました。
このことで、長兵衛の実力が周囲にばれてしまい、これまでの負けも仕組んだことだという事が露呈しました。
このことから、八百屋の長兵衛を略して八百長という言葉が生まれたとされています。
2つ目の説は、長兵衛が相撲で良いところを見せるために相手に相談を持ちかけて勝たせてもらった話から来たという説です。
花相撲と呼ばれる興行に参加した長兵衛は、どうしても身内にいいところを見せたいと思いました。
そこで、対戦相手に頼み込んで勝利を譲ってもらいました。
これが八百長のはじまりともいわれています。
この2つの由来から、勝ち負けをあらかじめ決めて試合を取り組むヤラセの勝負事を八百長という表現するようになったといいます。
しかしこの2つの由来、どちらも真偽は不明とされています。
まとめ
八百屋はもともと青物屋と呼ばれており、それが青屋と略されて、それが更に変化したことで「あおや⇒やおや」となったとされています。
なぜ八百という漢字が使われているのかというと、それは古くから日本では数が多いことを八百と表現していたことに由来しています。
そこから野菜や果物をたくさん扱っていたお店を八百屋と表記するようになったのだとか。