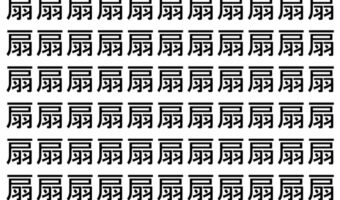「慣用読み」というのは、本来は間違った読み方のはずが、定着したことで新しい読み方として広まった一種の誤読のことです。
「言葉は生き物」と言われる事もあるように、意味や用い方だけでなく、読み方も変化することがあるのです。
そこでここでは、「慣用読み」がどのようなものなのかを見ていきましょう。
また、代表的な慣用読みや意外なことに慣用読みだったりする語についてもご紹介します。
目次
「慣用読み」とは

慣用読みとは、読みに慣用音を含む語句のことです。
漢字の音読みには、呉音・漢音・唐音という種類があるのですが、いずれにも属さない日本独自の音読みもあり、これを慣用音と言います。
もともとは誤読
この慣用音は、誤読から生まれたとされます。
例えば「お茶」、これの読みは一般的には「おちゃ」です。
ところがこれは、中国から伝来した音に由来する音読み「呉音・漢音・唐音」のいずれにも属しません。
呉音なら「ジャ」、漢音の場合は「タ」、唐音ならば「サ」となるはずなのです。
実際、「茶道」は「さどう」と読みますので、唐音が適用されています。
そのため、茶を「ちゃ」と発音するのは誤読となります。
間違いが普及したから正しいことにされた
しかし現在では「お茶のおかわり下さい」を「おさのおかわりください」と言う人はまずいません。
「ちゃ」という発音が正しいものとして広く定着しています。
このように間違いではありますが、間違いとも気付かれず正しいもとのして定着した発音または語句が「慣用音」や「慣用読み」となります。
代表的な「慣用読み」

代表的な慣用読みをまとめてみました。
私たちの日常になじんだ読みも多く、いずれも単純に誤読とは言い切れない語句となっています。
重複
重複は、「ちょうふく」もしくは「じゅうふく」と読まれます。
旧来は「ちょうふく」と読まれていましたが、日常では重力や重量など「じゅう」と読む語句が多かったこともあり「じゅうふく」と誤読されるようになりました。
そして、この読みが広まったため一概に間違いともいえなくなり、「じゅうふく」は慣用読みとなりました。
貼付
貼付の読みは、「ちょうふ」または「てんぷ」です。
「ちょうふ」という読みが正しかったのですが、「てんぷ」とも読まれることの方が多くなりつつあります。
この慣用読みが広まった背景には、似た意味を持つ「添付(てんぷ)」と混合されたことが原因なのではないかと考えられています。
「貼付」は封筒などに切ってを貼ることを指し、「添付」は書類などに資料を添えることを指しているため意味は若干異なりますが、確かに意味合いは似ていますね。
また、占の字に似た、点や店の読みである「てん」につられてしまったことによるものともいわれています。
出生
出生は、「しゅっしょう」もしくは「しゅっせい」と読みます。
「しゅっしょう」という読みが先にありましたが、生誕のように生を「せい」と読む後もあるため、「しゅっせい」と読む人が増えて慣用読みとなりました。
しかし、「しゅっしょう」という読みが廃れたわけではなく、公的な場などでは現在も「しゅっしょう」の読みは用いられています。
たとえば、子供が生まれた際に役所に出す「出生届」は、「しゅっしょうとどけ」と旧来の読みとなっています。
実はこれも「慣用読み」!

中には、旧来の読みがむしろ誤読なのでは?と感じてしまうほど慣用読みしか用いられていない言葉もあります。
情緒
情緒の旧来の読みは「じょうしょ」です。
ところが日常では、「じょうちょ」という読みしか使われていないのでないでしょうか。
由緒や端緒では「しょ」と読みますので、「緒」全ての読みが「ちょ」になっているわけではなく、情緒がイレギュラー的に慣用読みされているともいえるのかもしれません。
早急
早急は「さっきゅう」と読む語句です。
しかし、「そうきゅう」とも読まれることの方が多くなっています。
「さっ」という早の読みは常用漢字表にも載っていますが、実例は少なく「そう」の読みを用いた語の方が多いです。
そのため、「そうきゅう」の読みが定着したと考えられています。
ちなみに、「さっ」の読みの少ない実例として「早速(さっそく)」があります。
撹拌
撹拌には「こうはん」という読みしかありませんでした。
しかし、撹の「覚」から、「かくはん」という読みがされるようになりました。
近年では料理番組などでも広く「かくはん」の読みが使われていますよね。
むしろ料理番組の音声だけ聞いていたところで「たまごをこうはんしてください」と言われたらギョッとしてしまうかもしれません。
それほど定着した慣用読みとなっています。
消耗
消耗の一般的な読みは「しょうもう」です。
ところが、旧来の読みは「しょうこう」となっています。
消耗品を「しょうこうひん」と読むことは・・・そうそうありませんよね。
「しょうもうひん」と慣用読みを交えた読みの方が、よほど一般的です。
「毛」の音に引っ張られて誤読されたのが広まり、定着したとされています。
荒らげる
「荒げる」は「あららげる」と読む語です。
しかし現代では、「あらげる」の方が一般的です。
NKによるある調査によれば、8割近くが「あらげる」と読むと回答したのだとか。
そのため、正しい日本語を使う事を心掛けている放送でも「あらげる」の読みが使われるようになったそうです。
まとめ
日本には無数の慣用読みが存在します。
この慣用読みとなった語句の読みは、本来は誤読だったものかもしれませんが、普及しているためもはや間違いとも言い切れない存在になっています。
もともとの読み方も正しいですし、間違った読み方であっても多くの人が認識している読み方であれば正しいと言えます。
言葉は生き物と言われる事もあるように、読みも変化するものなのです。
とはいえ、ジェネレーションギャップなどにより「その読みは違う」と指摘を受けることもあるかもしれませんね。