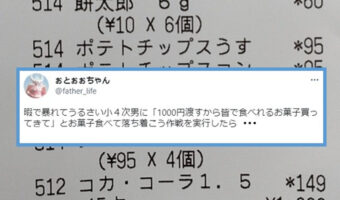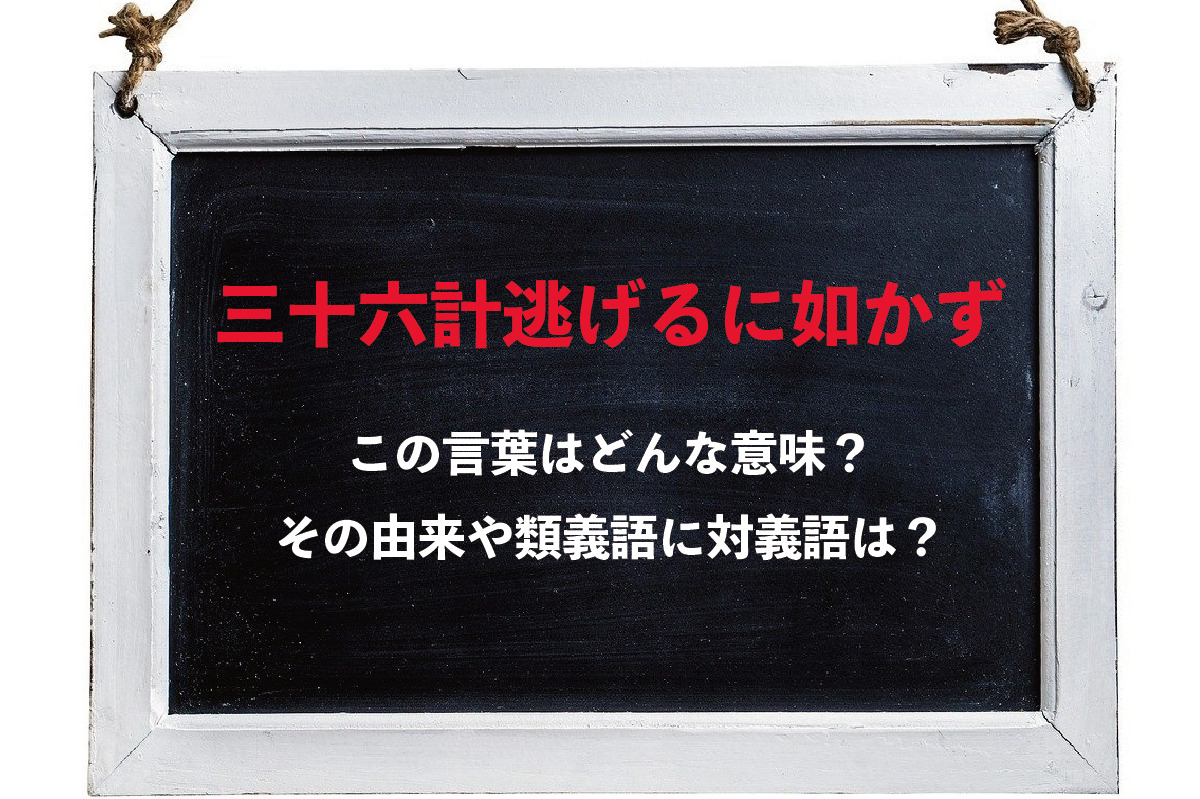
何かから逃げる際の口上として「三十六計逃げるに如かず」というものがあります。
これは、面倒事や手間のかかることが起きたなら、逃げるのが一番であるという意味でも用いられます。
ところで、この言葉に含まれている「三十六計」とは何をあらわすのでしょうか?
そこでここでは、この「三十六計逃げるに如かず」という言葉について見ていきましょう。
目次
「三十六計逃げるに如かず」とは

まずは「三十六計逃げるに如かず」という言葉の意味や用い方を見ていきましょう。
「三十六計逃げるに如かず」の意味
「三十六計逃げるに如かず」とは、形勢が不利になったときはあれこれ思案するよりも逃げてしまうのが一番である、という例えです。
それが転じたことで、自分にとって不利な面倒事などが起きた際は、そそくさと逃げるのが得策であるという意味で用いられるようになりました。
「三十六計逃げるに如かず」の用い方・例文
「三十六計逃げるに如かず」は、不利な状況で用います。
何かをやっておいて〜と頼まれた際に、それが自分の苦手なことであったり手間のかかることだった場合などに用いられます。
どうやっても上手くいくようには思えない物事を前に「状況は最悪、三十六計逃げるに如かず」と物事の中止に際して使用されることもあります。
「ここは三十六計逃げるに如かずだぜ」とその場から逃げるようにして去る際に、逃げ口上として用いることもあります。
「三十六計」とは兵法三十六計のこと

「三十六計逃げるに如かず」の「三十六計」とは古代中国でまとめられた『兵法三十六計』から来た言葉です。
「兵法三十六計」とは
「兵法三十六計」は、中国における南北朝時代に活躍した武将「檀道済(たん どうせい)」がまとめたとされる兵法書です。
その内容が、兵法つまり戦術を六系統・三十六種類に分類したものであることから来た名前となっています。
「逃げるに如かず」は兵法三十六計の最後の計
宋の建国期に活躍した檀道済がまとめた「兵法三十六計」の最後の計に「走為上」とあります。
これは、自軍が不利な際に用いる「敗戦計」の最後に載っている計でもあります。
その計の内容は、万策尽きて勝ち目が一切ない場合は逃げることこそが最善の策である、となっています。
ちなみに、勝てないと判断されたときに、自軍の損害を少なくして撤退するには、指揮をしているものが冷静な判断力を失っていない必要があるともまとめられています。
各々が三々五々に逃げ惑うのではなく、統制された撤退することを描写していたのですね。
「三十六計逃げるに如かず」の類義語

ここからは「三十六計逃げるに如かず」の類義語を見てみましょう。
逃げるが勝ち
「逃げるが勝ち」とは、無駄な戦いや愚かな争いなら、避けて逃げる方が結局は勝利や利益を得られるということを例えた言葉です。
その場は相手に勝ちを譲ることで、後々の勝ちに繋げたり利を得るという意味合いで用いられます。
「三十六計逃げるに如かず」の対義語

次に「三十六計逃げるに如かず」の対義語も見ておきましょう。
当たって砕けろ
「当たって砕けろ」とは成功するかどうかはわからないが、失敗を恐れずに思いきって行動をするべきだという意味があります。
結果こそ分からないけれども行動に出ることで状況の打破や事態の転換を図るという意図のある言葉です。
身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ
「身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ」とは、一身を犠牲にするだけの覚悟があってこそ、活路を見出して物事がうまくいくということを例えた言葉です。
窮地に陥っても事態を冷静に捉えて物事の見極めれば、活路を見出だせることを指すものでもあります。
災難に巻き込まれると人は抗おうとするものの、むしろ流れに身をまかせることが良い結果を呼ぶこともあることから来ています。
まとめ
「三十六計逃げるに如かず」は、面倒なことがその身に起きたら逃げてしまうのが得策である、ということを例えた言葉です。
逃げ口上としも用いられることがあります。
この言葉に含まれる「三十六計」とは、中国における南北朝時代、宋の建国期に活躍した武将の檀道済がまとめた兵法書の内容から来ているとされています。