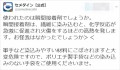独特な香りと風味豊かな「シソ」は、和食の食材としても人気です。
そんなシソですが、似たようなものに「大葉」と呼ばれるものもありますよね。一体何が違うのでしょうか?
・・・実はこの2つ、同じものだったりします。
ここでは「シソ」と「大葉」がなぜ違う名称で呼ばれているのか、その理由について見ていきましょう。
目次
シソと大葉について

シソと大葉は、基本的に同じものです。
名称が違うので別物だと思割れるかもしれませんが、イメージとしてシソが植物の種類で、大葉は商品だと思っておくとわかりやすいかもしれません。
どちらも同じ植物で、古くから活用されてきた歴史を持ち、重要な食材の1つとされてきました。
豊富なビタミンやミネラルが含まれているため、日本人の菜食重視の食文化には欠かせないものです。
シソとは
シソは、シソ科シソ属の植物です。
漢字では「紫蘇」と書き、種類で分類する場合は青紫蘇や赤紫蘇など色によって区別されます。
日本では主に青紫蘇と赤紫蘇がメジャーとなっていて、食卓に並ぶことも多いですね。
シソの葉は天ぷらにしても美味しいですし、他の料理に添えて香り付けするときにも使います。
実に汎用性の高い食材です。
大葉とは
大葉はシソの葉の部分にあたり、原則として商品名として使われる名称です。
基本的にはシソと同じ植物なので、特に大きな違いはありません。
シソと大葉の名前が違う理由

シソと大葉は、なぜ名前が違うのでしょうか?
これに関してはすでに結論が出ています。
特に難しいことはなく、単純に用途の違いがあるだけです。
大葉は商品名
大葉は、シソの植物の中でも"商品になる葉の部分を指す"のが一般的です。
というのも、シソは葉だけはなく、芽・花・実いずれも食用とされるからです。
シソだけではどの部位を指しているのか分かりません。
そこで、シソの葉は「大葉」、芽は「芽紫蘇・青芽」、花は「花穂」で、実を「穂紫蘇」と呼び分けるようになったのです。
大葉と呼ぶのにも地域差がある?
地域によってはどのような状態であっても、「シソは商品化されても"シソ"」と呼ぶこともあります。
葉・芽・花・実の中で一番量が多いのは、やはり葉の部分になるので、食材として一番目にするのは葉です。
そのことから、大葉と言わずにシソといえば葉の事だと、シソと呼んでいる人がいてもたしかにおかしくはありませんね。
また、使い分けないといけないというものでもないので、地域によってはその逆パターンもあり、シソ全体を指して「大葉」と呼ぶこともあります。
とはいえ、シソも大葉も結局は同じ植物を指すということは共通しています。
多くの活用方法が伝わっているシソ

シソや大葉は、ワサビのように"日本のハーブ"といわれるだけあって、古くから多くの活用方法が見い出されてきています。
ここからは、その活用方法について見ていきましょう
梅干作りに欠かせない赤紫蘇
和食の定番として知られる梅干は、赤紫蘇を使用して作られています。
梅干は熟した梅に赤紫蘇と塩を一緒に漬けて作りますが、梅干の独特な酸味や香味、そして色合いを出すためには赤紫蘇が欠かせません。
シソの一種から採れる「エゴマ油」
食用として販売されている「エゴマ油」は、シソ科植物であるエゴマの種子から採れる油です。
このエゴマ油は不飽和脂肪酸をたくさん含んでいるため、高級食用油として人気です。
その歴史は古く、平安時代までさかのぼるといいます。
当時は光を灯すために使われていたそうで、その後、室町時代に入って菜種油が普及するまでの間、古来の日本では油といえばこのエゴマ油を指していました。
シソには防腐殺菌効果がある?
古くからシソには、高い防腐殺菌効果があると考えられています。
シソの葉が刺身のツマとして使われるのは、刺身が傷むのを守るためとされています。
いまは刺身の下に1枚添える形が一般的ですが、この一枚によって刺身の鮮度を守っているわけです。
食欲増進効果
シソや大葉は、香りを嗅ぐだけで食欲が増してくる気がしてきますよね。
レモンのように酸味の強いものが食欲をそそるように、実は香味が強いものも食欲を増進してくれるのです。
これはシソに含まれる香り成分のペリルアルデヒドやリモネンによるものと考えられており、匂いを嗅ぐだけでよだれが出てしまう人もいるくらいです。
まとめ
シソと大葉は同一の植物のことを指すので、大きな括りで違いはありません。
厳密にいえば、シソが植物そのものを指すのに対して、大葉はシソの葉を指すというところでしょうか。
しかしだからといって、葉の事をシソというのも決して間違いではありません。
あくまでも商品にするにあたって、他にも食用にできる芽や花に実と区別するために生まれた言葉なのです。