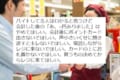思いがけないことによって良い方向に進んでいくことの表現のひとつに「牛にひかれて善光寺参り」という言葉があります。
この言葉には、なぜ牛が出てくるのでしょうか。
また、善光寺とはどこなのでしょうか。
ここでは、この「牛にひかれて善光寺参り」という言葉について、その意味や由来、そして類義語について見ていきましょう。
目次
「牛にひかれて善光寺参り」とは

まずは「牛にひかれて善光寺参り」という言葉がどのような意味なのかを見ていきましょう。
「牛にひかれて善光寺参り」の意味
「牛にひかれて善光寺参り」とは、思ってもいなかったことや他人の誘いによって、良い方向に導かれるという意味です。
何かのきっかけが縁となって、良い方向に導かれるという表現となります。
偶然が重なって変化が訪れることや何かしらのきっかけで自分が変わることもあらわします。
「牛にひかれて善光寺参り」の由来となった伝説

ここからは「牛にひかれて善光寺参り」という表現が生まれたのか、その成り立ちを見ていきましょう。
善光寺は長野県にあるお寺
善光寺というのは、長野県長野市に実際にある寺院のことです。
江戸・京・大坂で秘仏の公開をする「三都開帳」などが知られ、現在も観光地として多くの人が訪れています。
由来となった信心の薄いおばあさんにまつわる逸話
「牛にひかれて善光寺参り」という言葉は、信心の薄いおばあさんにまつわる逸話から来たとされます。
その昔、信濃国に信心の薄いおばあさんがいました。
ある日、布を干しているとどこからか牛がやってきました。
すると、この牛の角が布に引っ掛かり、そのまま走り去ってしまったのです。
おばあさんは、この牛の行動に大層腹を立て、後を追いかけました。
ところが牛の逃げ足が早くてなかなか追いつきません。
おばあさんが気が付いた時には、善光寺の金堂前まで来ていました。
それと同時に日が沈み、牛の姿も見えなくなってしまいました。
ところが次の瞬間、善光寺の仏像が輝きおばあさんを照らしました。
そこでおばあさんが足下を見ると、先ほどまでいた牛のよだれで「うしとのみおもひはなちそこの道に、なれをみちびくおのが心を」と書いていました。
この時、おばあさんは信心に目覚め、その夜一晩善光寺の如来像の前で念仏を唱え続けたというのです。
このおばあさんと牛の伝説から、何かのきっかけが縁となって良い方向に進むことを「牛にひかれて善光寺参り」と表現するようになったのです。
「牛にひかれて善光寺参り」の類義語

最後に「牛にひかれて善光寺参り」の類義語を見てみましょう。
るいぎごとしては「棚からぼた餅」「風が吹けば桶屋が儲かる」などがあげられます。
棚からぼた餅
「棚からぼたもち」とは、思いがけない幸運が舞い込むことの例えです。
これは、戸棚の下でのんびりしていたところたまたまぼたもちが落ちてきて口に入ったという偶然が重なったことから来た言葉とされています。
そこから、思ってもいないところで幸運に出会うことを言う表現となりました。
風が吹けば桶屋が儲かる
「風が吹けば桶屋が儲かる」とは、ある出来事がきっかけで、無関係と思われるところにまで影響が出ることの例えです。
また、あてにできそうもないことに期待をかけることの例えとなります。
強い風の日に砂埃が立つと、砂の影響で失明するが増えます。
この失明した人が今度は三味線で生計を立てようとすると、三味線が売れるようになります。
さらに、三味線の胴に張る猫の皮も売れるようになります。
それによって猫が減ってしまうので、数の減らなくなった鼠が桶をかじるようになります。
その結果、桶屋が儲かるようになる、そんな回り回ってという要素を重ねたのが「風が吹けば桶屋が儲かる」という言葉なのです。
まとめ
「牛にひかれて善光寺参り」は、偶然出会ったことによって、何かが良い方向へと変わっていくことを意味します。
思いがけないことで変化することに対して用いられます。
その類義語としては、「棚からぼた餅」「風が吹けば桶屋が儲かる」などがあげられます。