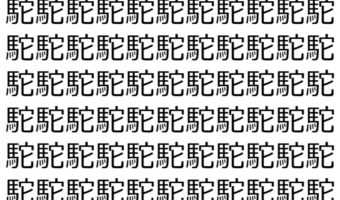料理に関する言葉のひとつ「アペタイザー」。
この言葉は、2つのシチュエーションで用いられることがあります。
ひとつは「前菜」、もうひとつは「食前酒」です。
食べ物と飲み物という大きく異なるものをさ指す「アペタイザー」について、ここでは解説します。
目次
「アペタイザー」とは?

アペタイザーとは、前菜の意味で用いられる事が多い言葉です。
しかし、もうひとつ意味があり、それは食前酒となります。
どちらの意味で用いても間違いということはなく、食前酒という意味で使っている人もいれば前菜という意味で使っている人もいます。
とはいえ、前菜の方が一般的に多用されている傾向にあります。
アペタイザーは英語
アペタイザーは、アメリカ英語”Appetizer”から来ています。
同じ意味のイギリス英語は”starter”です。
イギリス英語の同義語から見ると分かるように、食事を始める際に食べるもの、つまり英語では前菜という意味になります。
前菜
Appetizerは、食欲を増進させるものという意味があります。
スープやサラダが出てくる前にいただく一品である前菜という意味で用いられます。
Appetizerから来た「アペタイザー」は、前菜や食前酒を指して用いられますが、食前酒のことを指すならアペリティフと表現されることが多いです。
オードブル、アンティパストなどとの違いは?

西洋料理全般ではアペタイザーを使うのですが、伝統的なフレンチではオードブル、伝統的なイタリアンならアンティパストと使い分けがされています。
意味自体にはそこまで大きな違いはありませんが、料理の種類自体がそれぞれ異なるということになります。
よく聞くオードブルとの違い
アペタイザーとオードブルは、意味としてはほとんど同じです。
意味自体は基本的に同じですが、オードブルはフランス語です。
そのため、フランスもしくはフレンチではオードブルという言葉の方を耳にすることが多いと思います。
世界中で使う前菜の意味
オードブルは、世界中で前菜の意味で用いられています。
日本でも、アペタイザーよりもオードブルという表現の方がメジャーです。
ちなみに、オードブルはコースも含めて、スープの前に提供されるのが一般的です。
アンティパストとの違い
アンティパストもまた、アペタイザーと基本的には同じ意味です。
意味としてはほとんど同じで、アンティパストはイタリア語で前菜を指す言葉となっています。
生ハムやチーズが有名
アンティパストでは、スモークの香りが強さで食欲を増進させる生ハムやチーズが主に提供されます。
食事を本格的に進める前に、胃袋を刺激するわけですね。
日本でも近年はイタリアンの店が増えてきたことによって、アンティパストを提供しているところもあります。
使い分けは?

アペタイザーもオードブルもアンティパストも、それぞれの母国語に合わせるという使い分けが一般的です。
料理に合わせて使い分けよう
フレンチなら「アンティパスト」イタリアンなら「アンティパスト」と、料理に合わせて使うのが好ましいです。
ただし、フレンチで用いられるオードブルは全世界で使われる用語になっています。
前菜=アペタイザーでも問題ない
アペタイザーは、前菜と認識しておけば間違いないです。
とはいえ、前菜に何があるか聞こうとして「アペタイザーはなにになりますか?」と言っても通じないことがある、ということは意識に置いておいたほうがいいかもしれません。
まとめ
アペタイザーは、英語を由来とする前菜を意味する語句です。
お店などによっては、食前酒の意味で用いられることもあります。
同様に前菜を表す言葉としては、「オードブル」や「アンティパスト」などがあげられます。