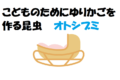ハンコを押すことを意味する捺印と押印という言葉。
これは意味自体は同じですが、使うシチュエーションが異なるという違いがあります。
では、どのようなシチュエーションでそれぞれ使うべき言葉なのかを、ここでは見ていきましょう。
目次
「捺印」と「押印」の意味は同じ

捺印と押印はどちらも「ハンコを押す」という意味です。
ところが、使うシチュエーションに違いがあります。
「捺印」と「押印」の使い分け

捺印と押印の意味は同じですが、原型となっている言葉が違うことから、それぞれ使用するシチュエーションが異なってきます。
捺印とは
捺印は「署名捺印」の略称です。
そのため署名がセットで必要になります。
署名には名前を表記するという意味があり、本人により手書きで書かれるのが一般的です。
捺印は、署名を書いた横にハンコを押す際に使われる言葉ということです。
押印とは
押印は「記名押印」の略称です。
そのためセットで記名が必要となっています。
記名も名前を表記するという意味があるのですが、こちらは印刷された名前でも許されます。
押印されたものより、捺印されたものが効力は上
契約書など重要度の高い書類には捺印するのが一般的で、確実に契約した証拠として残すのが常識です。
その一方で、重要性が低い書類であれば押印するのが一般的となっています。
なお、捺印の際には実印を使うのが普通で、押印の際は認印や三文判でも良いとされる場合が多いです。
認印や三文判はハンコ屋などで簡単に手に入れることができることから、大切な契約の場合は実印を使う方が安心安全という認識が一般的となっています。
社会的な信用度という点でも、「実印での捺印」が効力も強いということになります。
他にもある似た言葉「押捺」や「調印」との違い

捺印や押印には、他にも似たような言葉があります。
それが押捺や調印です。
しかし、これらの使われ方も、捺印や押印とはまた違ったものとなっています。
押捺とは
押捺は、捺印や押印と同じく、ハンコを押すという意味があります。
しかし、拇印(ぼいん)にも使えるという点が捺印や押印との違いです。
むしろ、ハンコや印鑑を使うシチュエーションよりも指紋を使うシチュエーションの際に用いる言葉となっています。
拇印でもいいというニュアンスが強いなら、捺印や押印よりも「押捺」を使ったほうが意図が通じるかもしれません。
調印とは
調印とは、ハンコを押すという意味がありますが、使われるシチュエーションが非常に特殊です。
とても大きなプロジェクトに関して、合意を示す際や閣下間の条約や協定を結ぶ際に使われます。
また、国家間で条約や協定などを締結すること自体も指します。
「ハンコ」と「印鑑」の違いは?

捺印や押印だけではなく、それを押す「ハンコ」と「印鑑」も違いが分かりにくいですよね。
この2つの違いについても見ていきましょう。
ハンコとは
ハンコとは、印材の平らな面(印面)に名前を彫刻した本体部分そのものです。
ハンコの原理は、版画のように本体部分を彫刻して印字するものです。
そのため、本体部分そのものを「版子」と呼ぶようになったのですが、それが転じて現在のように「判子」という漢字表記になったといわれています。
ちなみに正式名称は「印章」といいます。
また、出版物を印刷して発行するという意味をもつ「版行・板行」が転じて生まれたといわれています。
昔は今のようにプリンターなどの印刷機があったわけではないため、手作業で印刷物を作っていました。
その際に使われていた版行や板行が時代とともに変化し、判子と呼ばれるようになったとされています。
印鑑とは
印鑑は、市区町村などの役所や銀行などの金融機関に届け出て、登録された印影のことです。
印影とは朱肉などを用い、印章(ハンコ)で印を押したあとに残る文字や紋様のことを指します。
勘違いされがちですが、公的機関などに届け出している実印も銀行印も印鑑ではなく、あくまでも印章というのが正解です。
しかし、実印など印章自体のことを印鑑と呼称する方が一般的ですよね。
まとめ
ハンコや印鑑を押すことを、「捺印」「押印」と呼びます。
捺印は署名捺印で、押印は記名押印を略した言葉です。
捺印は手書きで名前を併記したもの、押印は手書き以外のものも含めた名前の併記があるものとなります。