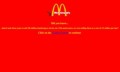素晴らしいおもてなしを受けて抱くことのある「いたれりつくせり」だな〜という感想。
同時に、満足した気持ちも抱く状況です。
ここでは、この「いたれりつくせり」という言葉の意味や類義語、由来について見ていきましょう。
目次
「いたれりつくせり」とは?

まずは、「いたれりつくせり」という言葉の意味について見ていきましょう。
「いたれりつくせり」の言葉の意味
「いたれりつくせり」を漢字を含めた表記すると「至れり尽くせり」となります。
「至れり」が最高の状態に至っていることを意味し、「尽くせり」は最善を期していることを意味しています。
つまり、最高の状態になるように最善を尽くしている状況ということですね。
では、「いたれりつくせり」が何に最善を尽くしているのかというと、それは対応や配慮です。
十分に心を込めて対応すること、すべてに細かく配慮が行き届いていることを表す言葉となっています。
サービスなどが完璧に提供されていて、申し分ない状態にあることを指しているということになります。
こちらが例文となります。
・「いたれりつくせりな温泉旅行だった」
・「実家に帰ると親が家事をすべてやってくれるので、いたれりつくせり状態である」
どちらもやってほしいことを、すべて思った以上に対応してくれているという状況ですね。
まんべんなく配慮されていて非常に良いと思ったかどうか、その感じ方は個人によって変わります。
そのため同じ状況にあっても、「いたれりつくせり」が使われることもあれば使われないこともあるので、感覚的な言葉ということになります。
「いたれりつくせり」の類義語
類義語としては「心尽くし」や「懇切丁寧」などがあげられます。
「親切」「気が利く」「気遣いができる」「粋な計らい」という言葉も類義語といえるかもしれません。
しかし、「いたれりつくせり」は受動的な状況、つまり自分が接待を受けたりサービスを施されている際に用いられる事が多いので、これらの言葉は表現として一致するわけではありません。
言い間違いや書き間違いに注意!
「いたれりつくせり」という言葉は、「いたりつくせり」や「いたせりつくせり」と間違えられることも多いです。
漢字を交えて表記すると「至り尽くせり」でも「致せり尽くせり」でもなく、「至れり尽くせり」です。
会話などで使う際には言い間違いをしないように注意したいですね。
「いたれりつくせり」の由来

「いたれりつくせり」という言葉は、どのようにして生まれたのかを見ていきましょう。
由来は中国の古典から
「いたれりつくせり」の由来は中国の古典にあります。
その古典とは荘子が残した「斉物論(せいぶつろん)」のことで、その書物の中で「いたれりつくせり」が使われています。
その書の中では「いたれりつくせり」を、「これ以上何かを加える必要がない完璧な状態」という意味で使われています。
荘子とは
荘子は、中国の戦国時代に産まれた思想家で、道教の始祖の1人として知られている人物です。
荘子は尊称であり、本名は姓が「荘」、名は「周」、字は「子休」です。
荘子とは尊称であるだけでなく、彼の書いた思想書そのものを指すこともあります。
斉物論もまた、荘子と呼ばれる著作のひとつですね。
そして、荘子も関わった道教とは中国三大宗教の1つであり、不老長寿の仙人になりたいと願う思想の神仙思想に、中国古代の世界観や宇宙観を説いた陰陽五行説を古代中国の学派である道家を加えたものとされています。
さらにそれが仏教の影響を受けて組織化されたものが、道教といわれる宗教になりました。
荘子の著作は、唐代以後に道教の経典に加えられました。
そして、道教が唐の時代に国教となったことから、荘周は皇帝「玄宗」により神格化されています。
道教といっても日本人には馴染みがないもののように思いますが、陰陽道や修験道の他、風水に非常に大きな影響を与えています。
まとめ
「いたれりつくせり」という言葉には、何から何まで行き届いていて、最高の状態になるように尽くすという意味があります。
行き届いたおもてなし、配慮のしつくされたサービスと、言い換えることもできますね。
「いたりつくせり」や「いたせりつくせり」と言い間違いをされることもありますが、漢字を交えた表記は「至れり尽くせり」となりますよ。