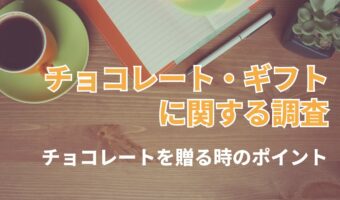どうとでもとれる、なんだか都合のいいあいまいな回答をすることを「玉虫色の答弁」などと言いますよね。
この表現で出てくる「玉虫色」とはどのような色なのかというと・・・、実は赤の一種や青に近い色といった特定の色では無いのです。
ではなぜ特定の色ではないのか、ここでは「玉虫色」についてみていきましょう。
目次
玉虫色とは

玉虫色とは光の加減によって色が変わり、特定の色を示さない不思議な色です。
逆に言えば「この色」という色を示すことのできない色なので、文章で表現するのも難しいです。
玉虫色はどんな色?
実際に玉虫色がどんな色なのか聞かれたら「光沢のある緑や紫といった光の具合で色調が変化する色」と答えることしかできません。
ふつうは色といったら「赤」や「青」といった原色を表現するの他、「あかるい赤」「黄味がかった赤」「暗い赤」といった形容詞などを付けて原色からどのような変化があるかを付けてあらわしますよね。
ところが「玉虫色」に限ってはそうではありません。
光の具合によってメタリックともいえる光沢を帯びた緑に見えることもあれば、紫のように見えることもあります。
そのため、玉虫色はこんな色と特定の色として表現するのが難しいわけですね。
ただし「玉虫色」の染色や織り色というものはあります。
これは光によって色合いが変わる染料や糸などが用いられています。
|
|
玉虫色の言葉の意味
この何色とも言い尽くせない曖昧な色の特徴が転じて「話し合いは玉虫色の結果となった」など、見方や角度によってどちらにも解釈できるような曖昧な表現として使われるようになりました。
他にも、都合の良い態度やどっちつかずという意味でも使われる言葉です。
タマムシの体色から付けられた玉虫色

玉虫色はなぜ「タマムシイロ」と呼ばれるのでしょうか。
そこで、ここからは玉虫色の語源となったとされている同名の虫について見ていきましょう。
タマムシとは
玉虫色の語源となったのは、タマムシという虫です。
タマムシは本州や四国や九州などに生息する昆虫で、光の加減によって緑や紫といった色に変わる光沢のある体色をしているのが特徴です。
主に平地から低山地に分布しており、日本は各地で見かけることができます。
日本では、ヤマトタマムシという種が最もポピュラーとなっています。
一般的にタマムシといったらこの種を指すのですが、この種類がタマムシの中でも最も美しい種類だとも言われています。
タマムシは、日本だけで約200種類以上もおり、その中には濃褐色の体で玉虫色をしていないものもいます。
全ての種類が美しい体の色というわけではないんですね。
主に6月~8月など夏に見られる虫となっています。
光によって体の色が変化するタマムシ
タマムシは、背中に虹を描いたような色合いをしています。
光に照らされると見方や角度によって色が変わります。
光の加減で体の色が変化するのは、タマムシが構造色と呼ばれる特殊な構造の持ち主だからだと考えられています。
構造色の生き物は、実際に体そのものに色が付いているのではありません、
タマムシの場合は、透明な層が何枚も重なることで生み出される色だという事が分かっています。
仕組み自体は異なるのですが、CDの読み取り面やシャボン玉も光の具合で色が変わって見えますよね。
これも両者が構造色なのが理由です。
ちなみに、海外ではこの構造色により宝石ようも見えるその外見から、ジュエルビートル(Jewel beetle)と呼ばれています。
タマムシに関する豆知識

不思議な体色をしているタマムシの豆知識をご紹介します。
タマムシにちなんだもう一色「虫襖色(むしあおいろ)」
タマムシには実はもう一色、由来となった色があります。
その名も「虫襖色」です。
これはタマムシの翅(はね)の色味が名前の由来とされています。
暗く青みのある緑のこと指し、こちらは玉虫色とは違い特定の色を指します。
別名では夏虫色(なつむしいろ)とも呼ばれ、以下のような色のことを指します。

普通の緑に比べると確かに青みがかっていて、和風な色合いですよね。
国宝に使われているタマムシ
タマムシは美しいその体の色が昔の人の心も捉えたようで、奈良にある法隆寺所蔵の国宝「玉虫厨子(たまむしのずし)」に材料としてタマムシを象徴するその翅が使われています。
しかし、この玉虫厨子が作られたのは飛鳥時代と1300年ほど昔です。
そのため製作時当時のタマムシの翅はすでに朽ち果ててしまっており、現物からはもうほどんどなくなってしまっています。
ちなみに、厨子とは仏像や仏画、舎利や経典を安置する屋根付きの入れ物のことです。
宗教的に非常に重要なものを納めていたわけです。
まとめ
曖昧なことを表現する際に使われる玉虫色という言葉は、文字通りタマムシという虫にちなんでいる言葉です。
その色は、光の加減で光沢のある緑とも紫にも見えるという特徴を持ち、他にはない美しさという事もあり国宝にも材料として用いられています。
このタマムシには元となった色がもう一つあり、そちらは「虫襖色」という暗く青みのある緑となっています。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c961d0f.143815e9.1c961d10.49d2b4bd/?me_id=1226832&item_id=10024250&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-darumaya%2Fcabinet%2Fimg56646769.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)