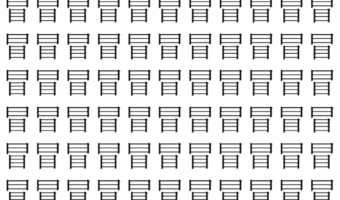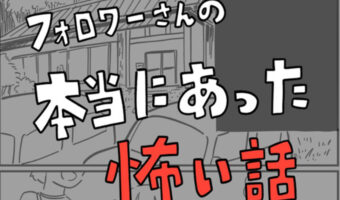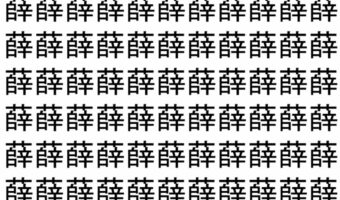何もかも投げ出して自暴自棄になったりヤケになったりすることを指す「捨て鉢」という表現。
この「捨て鉢」の鉢とは、どういう鉢を指しているのでしょうか。
これに関しては、修行中のお坊さんに関係しているとされており、お坊さんが途中で修行を断念したことから生まれた言葉とされています。
ここでは、そんな捨て鉢という言葉について見ていきましょう。
目次
捨て鉢とは

「捨て鉢」とは投げ出すこと、つまり何かをやっている途中でやめてしまうことを意味します。
捨て鉢の意味
「捨て鉢」とは、自分の思い通りにならない状況からやぶれかぶれな気持ちになることを意味します。
頑張ってはいても、耐え難い苦痛などによって途中で投げ出してしまうことを捨て鉢と言います。
「もうどうにでもなれ」という、投げやりな心境のことをあらわしているということになります。
捨て鉢の類義語
捨て鉢の類義語としては、「自暴自棄」や「ヤケ」などがあります。
素地らも後先を考える余裕もなく、すべてを投げ捨て逃げ出す状況において用いられる言葉となります。
その対象となるのは、他人ではなく、失望した自分自身となります。
捨て鉢の由来はお坊さんから?

「捨て鉢」という言葉は、お坊さんが関係しているとされています。
捨て鉢の「鉢」とはお坊さんなどが持っている托鉢を指しており、修行が辛くて断念してしまうことを「鉢を捨てる」と言います。
それが転じて、物事を諦め投げ出すことを捨て鉢と呼ぶようになったとされています。
仏教から生まれた言葉

「捨て鉢」だけではなく、実は仏教から生まれた日本語はたくさんあります。
ぜいたく「三昧」
「三昧」とは、熱中したり思う存分何かに没頭したり、思う存分にふるまう様子を指す言葉です。
周りの音が耳に入らないくらい集中して読書することを「読書三昧」と表現するのは前者となります。
「ぜいたく三昧」は、贅沢を思うが儘にする様子ですので後者となります。
この三昧という言葉はもともと仏教から生まれた言葉であり、「瞑想により心を1つのことに集中することで同様しない安定した精神状態になること」を意味しています。
現在の意味は、この仏教用語が転じたことで生まれたものです。
周りが見えなくなるほど物事に集中している状態や周りの声が聞こえなくなるほど熱心になっている様を指す言葉として使われるようになったとされています。
「阿吽」の呼吸
「阿吽」とは、「何か共同で物事を進める際にお互いの気持ちをぴったりと一致させる」こと、もしくは「息を合わせて行動する」ことを指します。
これも仏教から生まれた言葉で、「阿」が世界の始まりを表しており「吽」が世界の終わりを表しているとされています。
最初と最後が組み合わさったことで、終始呼吸などが合っている関係などを意味する言葉として使われるようになったのだとか。
諸悪の「権化」
「権化」も仏教から生まれた言葉です。
如来や菩薩と呼ばれる現世から乖離した存在である仏が人々を救うために、この世に仮の姿となって現れることを意味します。
また、形のない概念や思想が具体的な形となって現れたかのように思える人や物のことも指したりするのが特徴です。
近年では、「悪の権化」など悪い意味で使われることも多いですが、仏教の世界では神や仏や菩薩などを表すので、本来は良い意味で使われるべき言葉という事です。
まとめ
何かを投げ出して投げやりになっている人のことを「捨て鉢」と表現することもありますよね。
この言葉には、自暴自棄やヤケになるといった意味が含まれています。
その語源や由来は仏教にあり、もともとはお坊さんが修行を諦める際に托鉢を捨てたことから来ているとされています。