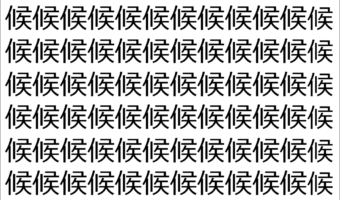春になるとピンクや赤、白などの美しい花を咲かせる「つつじ」。
このつつじ、その漢字表記は「躑躅」となります。
他に使われているのを見かけることのない漢字なこともあり、難読漢字でもあり書くのもとても難しい漢字となっています。
実はこの漢字表記は、「躊躇(ちゅうちょ)」に由来すると言われているんです。
ここでは、この「躑躅(つつじ)」の漢字表記の由来について解説していきます。
目次
躑躅と書く由来

つつじの漢字表記は、「躑躅」という画数も非常に多い難しい漢字となっています。
ここからは、なぜこの表記となったか、その由来について見ていきましょう。
「躊躇」からきたとされる漢字表記
「躑躅」という漢字表記は、ためらうことを意味する「躊躇(ちゅうちょ)」から来たとされています。
つつじの花と躊躇、その間にはどのような関係があるのでしょうか。
美しさに立ち止まる
つつじの花はとても美しく、ついついその美しさに見惚れて立ち止まってしまうことがあります。
この様子から、ためらうことを意味する躊躇の語が当てられて、のちに「躑躅」という表記に至ったとする説があります。
毒を持ったつつじを羊が食べると歩けなくなる
つつじの中には、なんと毒を持った品種もあります。
その毒を有するつつじの葉っぱを食べた羊が、歩けなくなって死んでしまった様子が「躑躅」の由来になっているともされています。
もう一つの読み「てきちょく」
「躑躅」は「つつじ」だけでなく、もう一つ読み方があります。
それが「てきちょく」です。
躑躅(てきちょく)とは足踏みしてなかなか進まないこと、立ち止まること、躊躇しながら進むことなどを意味します。
前述の羊が食べると〜、というのも足を止めて死んでしまうということから付けられた名称ともいわれています。
羊が食べると躑躅したように足踏みをした後死んでしまう葉がある植物、という事ですね。
つつじとは

漢字表記の成り立ちについて見てきましたが、つつじは庭木としてよく用いられている植物です。
このつつじの特徴も見てみましょう。
つつじの特徴
つつじは、日本に自生している野生種からたくさんの園芸種が生まれました。
大きくなりすぎず、栽培しやすいのが特徴で、庭木としてよく用いられています。
強健な性質で、美しい花を咲かすつつじにはたくさんの品種が存在しており、野生種だけでも50種以上存在するといわれます。
その花の色や形、葉の大きさ、形などは品種によってまちまちです。
つつじは日本に自生しているため、環境面で言えば育てるのは難しい植物ではありません。
あまり手間をかけなくても、毎年綺麗な花を咲かせてくれるなんてことも。
ただし、アブラムシや毛虫のような害虫は付きやすい植物となっています。
被害を受けると花付きが悪くなるさえあるのです。
日当たりと水はけがよく、肥沃な土の場所であればどこでも育てることができるでしょう。
開花時期
つつじの開花時期は、4月中旬~5月中旬頃です。
春から初夏にかけて多くみられ、国内でも場所によっては5月下旬まで咲いているところもあるようです。
つつじの満開時期は5日~1週間程度、それほど長く咲き続けるわけではありません。
名前の由来
つつじという名前の由来とされる説に関してはいくつかありますので、それぞれご紹介します。
花が筒状になっている
つつじの花は、筒状になっています。
この花の形状から「つつじ」と呼ばれるようになったといわれています。
「続き咲き木」という意味
つつじの花は、次々に連なり咲います。
その様子は「ツヅキサキギ(続き咲き木)」と言われており、ツヅキサキギが省略されて「つつじ」になったともいわれています。
「続き茂る」という意味
つつじの花は、次々に重なり咲く様子から「ツヅキシゲル(続き茂る)」とも言われています。
このツヅキシゲルが、省略されて「つつじ」になったともいわれていますよ。
つつじと日本文化

古くから日本に自生しており、人々に親しまれている花木であるつつじは日本文化との深い関係にあります。
ここでは、つつじと日本文化の関係性についてもご紹介します。
和歌や俳句に使われるつつじ
つつじは、大昔から日本の野山に咲いていたため、桜の終わった後に山吹や藤と並んで晩春を彩る花木の象徴とされてきました。
それもあってか、万葉集、古今集の時代から数多く詠まれています。
また、「つつじ」は俳句における春の季語でもあり、「躑躅花(つつじばな)」は短歌における枕詞として使用されています。
枕詞とは、、特定の語の前に置くことで続く言葉を修飾する他、語調を整える役割のある言葉のことです。
つつじは美しい花を咲かせることから、「花のように美しい女性」という意味を込めて用いられます。
そしてその後には「にほふ」や「にほえをとめ」が続きます。
つまり、つつじは「にほふ」「にほえをとめ」の枕詞ということです。
例えばつつじを使った有名な和歌として、歌聖と呼ばれる柿本人麻呂の「つつじ花 にほえ娘子(をとめご) 桜花 栄え娘子」などがありますよ。
つつじの専門書が江戸時代に出される
非常に人気の高い花と言えるつつじは、その専門書がなんと江戸時代に刊行されているんです。
元禄5年(1692年)に江戸染井村で植木屋を営んでいた伊藤伊兵衛が刊行した「錦繍枕(きんしゅうまくら)」が、世界最古のつつじの専門書であると言われています。
この専門書、つつじやサツキを図入りにした解説書でとなっているのですが、175種のつつじ、161品種のサツキが紹介されています。
江戸時代には、それほど多くのツツジの品種があったというののは驚きですね。
これだけ品種が豊富にあった背景には、元禄年間につつじのブームが来たことが影響を与えています。
武士や町民などといった身分を問わずにこのつつじブームは広がり、園芸品種の開発がすすめられていたのだそうですよ。
まとめ

日本古来の花であるつつじは、古くから日本人にとってはなじみ深い花です。
漢字表記にすると「躑躅」となるのですが、これはためらうことを意味する「躊躇」が由来とされています。
色とりどりに咲いたつつじ花は、思わず進むのを躊躇って見入ってしまうほどの美しさがありますよね。
そこからこの難しい漢字表記は来たともいわれていますよ。