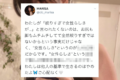ペンギンが移動する際、よちよち歩きをしているだけではなく、たまに地面を滑って移動することがあります。
これは「トボガン」と呼ばれる移動方法で、体力を温存するための移動方法だとされています。
トボガンをはじめ、ペンギンの習性には面白いものが多くありです。
そこでここでは、トボガンをはじめ、ペンギンにまつわる豆知識を見ていきましょう。
目次
トボガンとは

トボガンとは腹ばいになって滑るペンギンの移動方法です。
歩いて移動を続けるのは疲れるため、ペンギンたちは体力温存のためにトボガンをすると考えられています。
陸上での腹ばい移動のこと
トボガンとは氷塊や砂浜で腹ばいになって移動することであり、よくペンギンがよちよち歩きしているのとは別の移動方法となります。
トボガンをする理由
多くのペンギンは。水中だと翼を羽ばたかせて泳ぐことができるのですが、陸上では上手に移動できないからこそ腹ばいになって移動していると考えられていますが、実際のところは、体力温存のために行われています。
ペンギンの骨格の構造上、歩くことは体力を無駄に消費してしまうことがあるため、滑って移動できそうなところでは腹ばいになって移動するわけです。
ペンギンは、餌を採りに行くために巣から海まで100kmも移動するような種もいます。
体力を消費すると命取りとなる厳しい自然界だからこそ、体力温存のために生まれた習性ということですね!
語源は木ソリから
「トボガン」というのは。木ソリの事を指す言葉です。
カナダの先住民族の一部が用いていたソリで、雪上遊具として雪の上を滑って遊ぶことができるものがあります。
オリンピック競技でもあるウインタースポーツのスケルトンの原型ともされています。
この木ソリの形状を彷彿させるペンギンの姿から、トボガンという言葉が用いられるようになったとされています。
他にもあるペンギン生態や姿にまつわる豆知識

トボガン以外にも、ペンギンには生態などにまつわる秘密があります。
そこでここではペンギンの生態や姿にまつわる豆知識をご紹介します。
赤道直下に生息するペンギンもいる
ペンギンといえば南極など寒いところにいるというイメージがありますよね。
ところが実は、赤道直下に生息するペンギンもいます。
そのペンギンこそ「ガラパゴスペンギン」です。
ガラパゴスペンギンは、赤道直下に生息するペンギンで、赤道に接するガラパゴス諸島に分布しています。
極寒の地にいるペンギンに比べて羽毛が短く、ペンギンの中でも非常に小さい種類とされています。
とはいえ、生息している灼熱の地に適応しきれていないらしく、太陽光を避けて日陰で暑さをしのぐ姿なども確認されています。
かつて人間並みに大きいペンギンもいた
ペンギンは小さいものが多く、現代に生息しているペンギンの多くは人間の膝下ほど、ないしは腰下程度の大きさが一般的です。
一番大きいコウテイペンギンでもその大きさは体長130cmほど、体重が45kg程度です。
しかし、化石で発見されている太古のペンギンの中には、人間並みに大きい種類もいたことがわかっています。
中でも「ジャイアントペンギン」と呼ばれる種類は最大160cmほどあったとされています。
体重も約80kg~90kgほどあったと推定されることから、現在地球に生息しているコウテイペンギンよりも大柄だったようです。
ペンギンの名前にまつわる豆知識

ペンギンという名前にはどのような意味でしょうか。
実は、ペンギンというのは実は違う動物の名前だったんだとか。
ペンギンの名前の由来
ペンギンの名前は、その体格に由来するとされています。
ラテン語で「脂肪」や「太っていること」を指す"Pinguis"という言葉から、スペイン語で太っちょを意味する"penguigo"という言葉が派生して生まれたとされます。
この"penguigo"が訛ってペンギンになったとされています。
ペンギンは本来別の動物の事だった
ところが、このペンギンという名前。
最初に呼ばれていたのは別の動物でした。
かつて北極圏や北大西洋に「オオウミガラス」という海鳥がいました。
この鳥の名前の由来とされる説が2つあります。
1つは前述のラテン語を由来とする説。
もう1つはケルト語を起源とする説です。
このオオウミガラスには頭に白い斑点があったことから、ケルト語で「白い頭」を意味する"Pen-gwyn"と付けられたとされています。
このオオウミガラスが、先にペンギンと呼ばれていたとされまていす。
大航海時代になると、ヨーロッパの人たちは様々な航路を開拓する中でオオウミガラスにそっくりな鳥を見つけました。
オオウミガラスの仲間と思われたこともあって、その鳥もまたペンギンと呼ばれるようになりました。
一説には「南のペンギン」や「南極ペンギン」という呼び分けがされていたともいわれています。
しかし、オオウミガラスは後に乱獲などの理由から絶滅していしまいました。
その結果、ペンギンはオオウミガラスを指す名前ではなく、後から発見されたペンギンを指す名前に変わったのです。
まとめ
トボガンはペンギンが腹ばいになり、地面をすべるように移動する、ペンギン特有移動方法です。
これは体力温存のために行われていると考えられています。
ペンギンの母親は子供のために餌をとるために、巣から海まで何十kmも歩くことがあります。
海に着いたら今度は餌を採るために海に潜らないといけないので、移動に際しても体力を温存する必要があることから生まれた移動方法とされています。