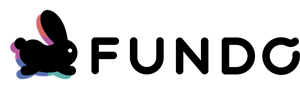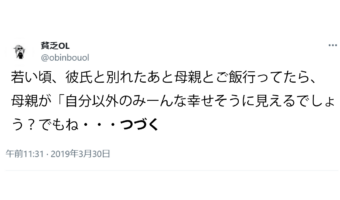野球ではピッチャーがバッターを打ち取ることを、三振と呼びます。
そしてこの三振、スコアボードには大きく「K」と表記されます。
三振は英語で「Strikeout」もしくは「Strike」なので、「S」なのでは?と思う人も多いと思います。
ところが「K」と書かれる由来もまた「Strike」にあるそうです。
そこでここでは、野球の三振がなぜ「K」と表記されるのかについて、その理由とともに見ていきましょう。
目次
「Strick」の「S」だとダメな理由

野球で、三振は「strikeout」といいます。
なのでスコアボードに表記する際も「S」や「SO」もしくは「O」でいいように思えてきますが、実際に用いられているのは「K」です。
なぜ「S」を始めとする他の表記が採用されなかったのか。
それは、「S」から始まる野球用語が多いため、用いない方が良いとされたからといわれています。
他の野球用語でSから始まる単語は確かに多く、「犠打(Sacrifice)」や「盗塁(Steal)」などが挙げられます。
そのため、三振を「S」の表記にしてしまうややこしいとされ、「K」が採用されたとされます。
三振が「K」になった理由

三振を意味する「K」は、単純に三振数をカウントするための単位としても用いられています。
例えば1試合で10三振をとれば「10K」と表記されます。
多くの奪三振を誇る投手が「ドクターK」などと呼ばれることもあります。
では、なぜ「K」が三振を意味する文字に採用されたのでしょうか。
「Struck」の「K」からきた
三振は「Struck」の「K」が由来とされています。
これは、19世紀のスポーツライターのヘンリー・チャドウィックが考案したものとされます。
野球には当時から、「犠打(sacrifice)」や「盗塁(steal)」など「S」表記の言葉が多くありました。
そこであえて「Strike」の過去形「Struck」で、一番イントネーションの大きい「K」を採用したとされています。
「K」が三画だから
日本では、数を数える際に「正」などの画数で数える文化があります。
同様に、世界にも数字をカウントする際に文字を使うという風習はあります。
そして「K」は直線三本の構成なので、三振を数えるのにちょうどいい文字でした。
三振だからこそ、三画の「K」を用いたというわけですね。
ただし、「A・F・H・N・Y」なども直線3本を組み合わせたアルファベットです。
そのため、なぜ「K」になったのか、という理由の解消には結びつかないかもしれません。
スコアボードに関する豆知識

ここからは野球のスコアボード、そこでの表記に関する豆知識をご紹介します。
アルファ勝ちは勘違いから生まれた
野球では、9回表が終わった時点で後攻チームが先攻チームをリードしていれば、9回裏の攻撃は行われずにスコアボードには「X」が記入され試合は終了となります。
この「X」は「もうこれ以上攻撃はない」「試合終了」という意味で「×(バツ)」・・・ではなく、本来は未知数を表す「X(エックス)」のことだといわれています。
この「X」という表記、かつては「α」でした。
そこから9回裏が無い試合は、アルファ勝ちと呼ばれてました。
なお、「α」と書かれていたのは、単なる勘違いから生まれたという話があります。
アメリカで使われていた手書きの「X」を、ある人が「α」と見間違えて導入したのだというのです。
ボールカウントの表示順に変更が加えられていた
日本において「ボールカウント」は、長い間「ストライク⇒ボール⇒アウト」の順のSBO式で読み上げられていました。
しかし国際慣習に従い、日本高等学校野球連盟は1997年の選抜大会から、球審が「ボール⇒ストライク」のBSO式で読み上げるように変更されました。
それに対し、日本プロ野球界では慣習に従い、2010年までSBO式が採用されていました。
しかし現在は、日本プロ野球も国際慣習に沿ってBSO式で読むのが普通となっています。
この変更に伴い、プロ野球本拠地球場におけるボールカウントの表示もSBO式からBSO式に変更されています。
また、地方球場でも当然BSO式にスコアボードが変更されている場所はあります。
まとめ
野球の三振はスコアボードなどに「K」と表記されるのですが、これは英語の「struck」から来ているとされています。
なぜ頭文字の「S」ではなく、おしりの「K」なのかと言えば、「S」から始まる野球用語が他にもあるからだ、とされています。
他には、「K」が三画だったことから、三振カウントするのに用いられたのではないかという説もあります。