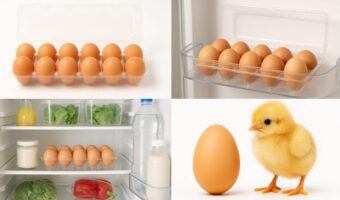薬味として使われる「わけぎ」と「ねぎ」はとても似た野菜なのですが、実は染色体の特性などから別物だと判明しています。
実は「わけぎ」と「ねぎ」では、原産も異なります。
そこで、ここでは「わけぎ」と「ねぎ」がどのような違いがあるのかを見ていきましょう。
また、東日本と西日本で「わけぎ」といわれるものは別物だったりするようですよ!!
目次
「わけぎ」と「ねぎ」の違い

まず「わけぎ」と「ねぎ」の違いについて見ていきましょう。
「わけぎ」とは
「わけぎ」とは、ネギとタマネギもしくはエシャロットの雑種に当たる野菜です。
ねぎの一種と考えられていた時代もありましたが、近年の研究により染色体の特性などが違うことが判明しました。
「ねぎ」とは
「ねぎ」は、中国西部もしくはシベリア周辺が原産とされる野菜です。
紀元前200年頃にはすでに中国各地で栽培されており、食材としてもとても古い歴史を持っていることがわかっています。
ちなみに、日本には奈良時代に伝わったそうです。
「ねぎ」は関東と関西で姿が異なる
「ねぎ」といっても、実は関東と関西で姿が異なります。
関東では「長ねぎ」「白ねぎ」と呼ばれる土中にある白い部分の多い「根深ねぎ」が主流とされています。
代表的な品種として、下仁田ねぎ・深谷ねぎ・矢切ねぎがあります。
関西でねぎというと、緑の部分が多い「葉ねぎ」が主流となっています。
代表的な品種に、九条ねぎ・観音ねぎ・難波葱などがあります。
これは姿ではなくて呼称なので余談となるのですが、「ねぎ」は収穫時期によってもそれぞれ「夏ねぎ」「冬ねぎ」と呼び分けることもあります。
西日本と東日本とでは「わけぎ」の指す野菜は異なる

東日本の「白ねぎ」と西日本の「葉ねぎ」で主流となっているものが違うように、「わけぎ」もまた西日本と東日本で違うものを指します。
特にわけぎの場合、ネギと違い、別種の野菜を指しています。
西日本における「わけぎ」
西日本では、上記のねぎとたまねぎの雑種のことを「わけぎ」と呼ぶのが主流となっています。
ちなみに、このタイプの「わけぎ」は、広島県三原市佐木島が全国出荷量日本一とされています。
東日本での「わけぎ」
東日本では、葉ねぎの一種である「分けねぎ」のことを「わけぎ」と呼ぶことが多いです。
「分けねぎ」は、埼玉県や千葉県などが主要生産地です。
「もてねぎ」や「あじさいねぎ」など品種改良で生まれた品種もあります。
2017年には「東京小町」などの新たな品種も登録されており、この「分けねぎ」が関東では「わけぎ」として流通しています。
「わけぎ」に似た野菜の「あさつき」とは」

そんな「わけぎ」には、もうひとつ似た野菜があり、「あさつき」といいます。
ここからは、そんな「あさつき」について見ていきましょう!
ねぎの中で最も細い葉をした「あさつき」
「あさつき」は、ヒガンバナ科ネギ属の球根性多年草です。
通常の「ねぎ」よりも色が薄く、食用とされる「ねぎ」の中では最も細い葉をしています。
この「あさつき」は日本では野草の一種とされており、山野で自生している姿が見られることもありますよ。
「あさつき」はハーブの「チャイブ」の変種
「あさつき」は、ハーブの「チャイブ」の変種とされています。
「チャイブ」はいわゆる「ねぎ」の仲間で、和洋中どんな料理にも合う万能なハーブです。
西洋の飲食店では「チャイブ」を使っているところも多く、料理に入れることで風味を際立たせるために用いられています。
また、マイルドな「ねぎ」の風味があるため、卵料理やじゃがいも料理にぴったりだとされています。
本来の「ねぎ」が持つ、独特の臭みがマイルドになっていることから、多種多様な料理に使用できます。
まとめ
「わけぎ」も「ねぎ」も薬味として使われることが多いですが、実際には姿も違えば原産も違います。
西日本では、ネギとタマネギもしくはエシャロットの雑種であるところの「わけぎ」が利用させますが、東日本で「わけぎ」と呼ばれるのは葉ねぎの一種「分けねぎ」です。
関東で目にする「わけぎ」は、本来の意味でのわけぎとはまた別物の「分けねぎ」という事も多いかもしれません。