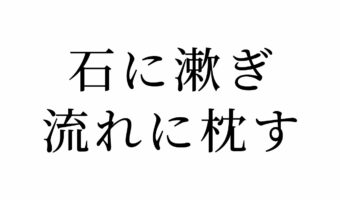「遮二無二」は、物事に必死に取り組んでいる様子をあらわす言葉です。
何かに夢中になっている様を指すこともあります。
ところがこの「遮二無二」、もともとは違う表記がされていたのだとか。
そこでここでは、「遮二無二」という言葉について解説します。
また、類義語が数多くあるのですが、その中からいくつかピックアップしてご紹介します。
目次
「遮二無二」とは

まずは、「遮二無二」という語の意味について見ていきましょう。
「遮二無二」の意味
遮二無二は、他のことを考えずひたすら熱中することをあらわす言葉です。
また、1つのことを強引に行う様子という意味でも用いられます。
どちらも前後の見通しも考えずに行うことという意味があり、無暗に、無性に、やたらとという意味もあります。
「遮二無二」の由来

次に、「遮二無二」という言葉の成り立ちを見ていきましょう。
遮二と無二のそれぞれの意味
遮二無二は、遮二と無二に分けることができます。
「遮二」は、二を断ち切るという意味があり、「無二」は二がないというようすをあらわしています。
つまり、どちらもなにか一つの事にのみ目を向けている様子をあらわしている言葉になります。
もともとは「差理無理」だった?
遮二無二は、もともと「差理無理(しゃりむり)」という言葉だったとされています。
江戸時代前期には、「差理無理」という言葉はすでにあったとされています。
この「差理無理」自体の意味は、遮二無二と同様とされていますが、言葉の由来は判明していないようです。
差理は、道理との差と表記することから道理との食い違いを、無理は現在と同じ道理に反することをあらわしているという説もあります。
遮二無二という語が出てくるようになるのは、差理無理の後とされることから、差理無理の派生で生まれた語と言われる事もあります。
「遮二無二」の類義語

ここからは、遮二無二と同様の意味のある言葉についてご紹介します。
無二無三
無二無三とは、ただ1つしかなく代わるものがないことをあらわしています。
これが転じて、ひとつの物事に心を傾けて打ち込む様子のたとえともなっています。
この無二無三は、仏教に由来する言葉です。
法華経で説かれている、仏になるための道は「一乗」のみとされています。
仏になる道に二乗も三乗もありません。
つまり、無二無三は2つとない唯一のことを指す言葉なのです。
そこから、他に代わるものが無いという意味を持つ言葉となりました。
これが更に転じて、物事に熱中している様子としても用いられるようになりました。
一心不乱
一心不乱とは、何か1つのことに心を集中することを指します。
特に他のことに心を奪われない様子や注意をそらさない様子を意味します。
「一心」は、心を一つにして集中することを、「不乱」は心を乱さないことをあらわしています。
しゃかりき
しゃかりきは、夢中になって何かに取り組む様子を指します。
もともと仏教用語とされ、漢字では釈迦力と書かれます。
その昔、お釈迦様が人々を救うために教えを説くことに力を注いだことにあやかって、この言葉が生まれたとされます。
仏教にまつわる言葉というと昔から使われていそうですが、このしゃかりきという言葉が全国的に広まったのは戦後になってからとされています。
まとめ
遮二無二は、物事に必死に取り組む様子を指す言葉です。
遮二が二を断ち切ること、無二が二がないことをそれぞれ指しあらわしています。
どちらも1つしかないことを意味しています。
これが転じて、1つのことに取り組むことを遮二無二と表現するようになったとされています。