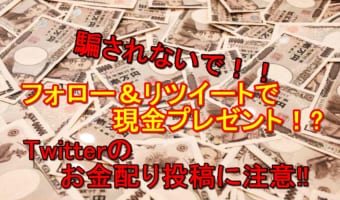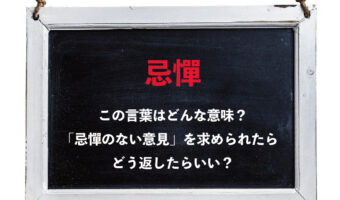ふざけた振舞いをすることを指す「茶番」。
また、馬鹿げた演技や見世物のようなやり取りのことを「茶番劇」などと表現することもあります。
ではなぜ、それらの行為が「茶番」と呼ばれるのでしょうか?
そこでここでは、「茶番」意味や由来についてご紹介します。
目次
「茶番」とは

まずは、「茶番」がどのような意味を持つ言葉なのかを見ていきましょう。
「茶番」の意味
茶番とは、底の見え透いた馬鹿げた振る舞いのことを指します。
下手な芝居を打つようなことをあらわします。
思惑が誰でもわかるほど浅はかなことを演技することから「茶番劇」という表現もあります。
いずれも揶揄する際に用いられる言葉です。
「茶化す」との違い
「茶化す」は、真剣な話でも冗談めかしてからかうことをあらわします。
もともと人をからかうことをあらわす言葉だったとされる「茶にする」。
これが一部変化したことで「茶化す」になったとされます。
茶番と同様、揶揄する際に用いられる事もありますが、茶化すは揶揄する動作や発言自体になります。
「茶番」の由来

ここからは茶番という言葉の由来について見ていきましょう。
実は「茶番」は。もともとある役割のことをあらわしていたのだとか。
もともとは「お茶当番」のこと
茶番はもともと「お茶当番」の人を指す言葉でした。
江戸時代の芝居小屋では、役者見習いは下働きとしてお茶くみ係を担っていました。
そして、その人たちは茶番の合間に、演技の稽古がてら即興劇を行っていました。
この稽古の一環として行われていた即興劇自体の事が後に「茶番」と呼ばれるようになりました。
役者見習いという事でうまくない即興劇なことから、「馬鹿馬鹿しい振舞い」や「見え透いた下手な芝居」「浅はかな行為」などをあらわすようになったとされます。
民衆に広まった「茶番」
最初は役者見習いによる即興劇の事だった「茶番」は、その枠を超えて一般大衆にまで広まりました。
そして、芝居のジャンルとして成立したのです。
しかも、芝居小屋で演じられる「茶番」は2種類。
立茶番(茶番狂言)と口上茶番(見立茶番)です。
立茶番は、京坂の「俄(にわか)」と似た茶番狂言のことを指します。
かつらや衣装を着けて芝居をもじるような滑稽な芝居を演ずるというもの。
口上茶番は座ったまま、セリフだけでダジャレたり、滑稽なオチをつけるものだったとされます。
「茶番」の類義語

ここからは「茶番」の類義語を見ていきましょう。
似たような言葉には八百長や安直、こどもだましなどがあげられます。
八百長
八百長とは、事前に勝ち負けや進行を打ち合わせておき、表面上は真剣に勝負しているように見せかけることです。
結果が決まっている勝負事そのものを指すこともあります。
これが転じて、馴れ合いで物事を運ぶことを「八百長」と表現するようになりました。
安直
安直とは、簡単で気楽な様子やいい加減なことをあらわす言葉です。
また、お金がかからず手軽な様子も指すこともあります。
こどもだまし
こどもだましとは、子供でないと騙すことができないくらい幼稚であることを指す言葉です。
特に仕掛けやネタのレベルが低いことをあらわす際に用いられます。
程度の低さをあらわすという点が「茶番」と共通しています。
まとめ
茶番という言葉は、もともとお茶当番を指す言葉でした。
江戸時代の芝居小屋では、役者志望がお茶くみなどを担当しており、時折稽古がてら即興劇を行っていたというのが始まりとされています。
この即興劇がとても見られたものでは無かったことから、程度の低い底の見え透いた馬鹿げた振る舞い指す言葉として用いられるようになったのだとか。