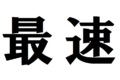比較にならないほどの差があることを「月とすっぽん」と表現することがあります。
しかし、なぜ「月とすっぽん」を比較しているのでしょうか。
そこには、一応理由があるのだとか・・・。
そこでここでは、この「月とすっぽん」という言葉について、その意味や由来、類義語について見ていきましょう。
目次
「月とすっぽん」とは

まずは「月とすっぽん」という言葉について、その意味や用い方について見ていきましょう。
「月とすっぽん」の意味
「月とすっぽん」とは、比較にならないほどその違いが大きいことを例えた言葉です。
特に比較対象となる2つのものが差が大きく違っていることを例えです。
2つのものの隔たりが大きすぎて、比べ物にならないことを言う際に「月とすっぽん」と表現します。
また、釣り合いが取れないことの例えとしても使用されます。
「月とすっぽん」の用い方・例文
「あなたと私では月とすっぽん」という表現がされることがフィクション作品などでありますが、これは私とあなたを対比して大きな違いがあることをあらわしています。
代表的な比較としては、恋愛者ならば2人の身分があげられますが、時には美醜についての比較がされることもあります。
この場合、優れたものが月、劣っている方がすっぽんに例えられるのが通例です。
「月とすっぽん」の成り立ち

「月とすっぽん」という両者を比較する言葉はどのようにして生まれたのか、その成り立ちについて見ていきましょう。
2つとも「丸い」ことが由来!
「月とすっぽん」は2つとも丸いことに由来しています。
月は、月齢が満月のときならほぼ真円ですし、すっぽんもまたその甲羅は円形です。
優劣の対象とされる両者は丸いという点は共通しています。
しかし、両者を比べるとまったくの別物と言えます。
月は天にあって清らかで美しい風情のあるものです。
一方、すっぽんは泥を這いずり回って食らいついたら離さない獰猛さのある生き物です。
それらを比較することで「月とすっぽん」という表現が生まれたともいわれています。
また、空にある丸い月と、地にある丸いすっぽんが天と地ほど離れた場所にある存在ということも関連しているとされることもあります。
すっぽんではなく「朱盆・素盆」だったとも
「月とすっぽん」のすっぽんはもともと「朱盆(素盆)」つまりお盆のことだったという説もあります。
確かに「朱盆(素盆)」も丸いので、音が訛ってすっぽんに変化し定着したのかも・・・しれません。
「月とすっぽん」の類義語

「月とすっぽん」の類義語には、「雲泥の差」「提灯に釣り鐘」「鯨と鰯」などがあげられます。
雲泥の差
「雲泥の差」とは、天と地ほどの隔たりがあることの例えです。
これは、人物や物事において両者の間に非常に大きな違いがあることを指します。
雲は雲上の素晴らしい生活を、泥は俗世間での生活をあらわしているとされます。
提灯に釣り鐘
「提灯に釣り鐘」とは、物事の釣り合わないことの例えです。
提灯と釣り鐘は形は似ていますが、重さがまったく異なります。
この提灯と釣り鐘の比べ物にならないほどの重量差から来た言葉とされています。
鯨と鰯
「鯨と鰯」は、極めて差が大きいことを意味します。
地球上の生き物の中でもトップクラスに大きいクジラと小魚のイワシでは大きさが比べ物になりません。
このサイズ差から生まれた言葉となっています。
まとめ
「月とすっぽん」は、比べることができないほどの差があることを例えた言葉です。
月もすっぽんもともに形は円形という共通点がありますが似ても似つかぬ存在です。
そこから、天と地ほどの違いがあることを「月とすっぽん」と表現するようになったとされています。