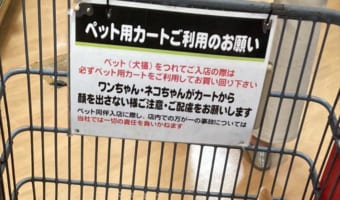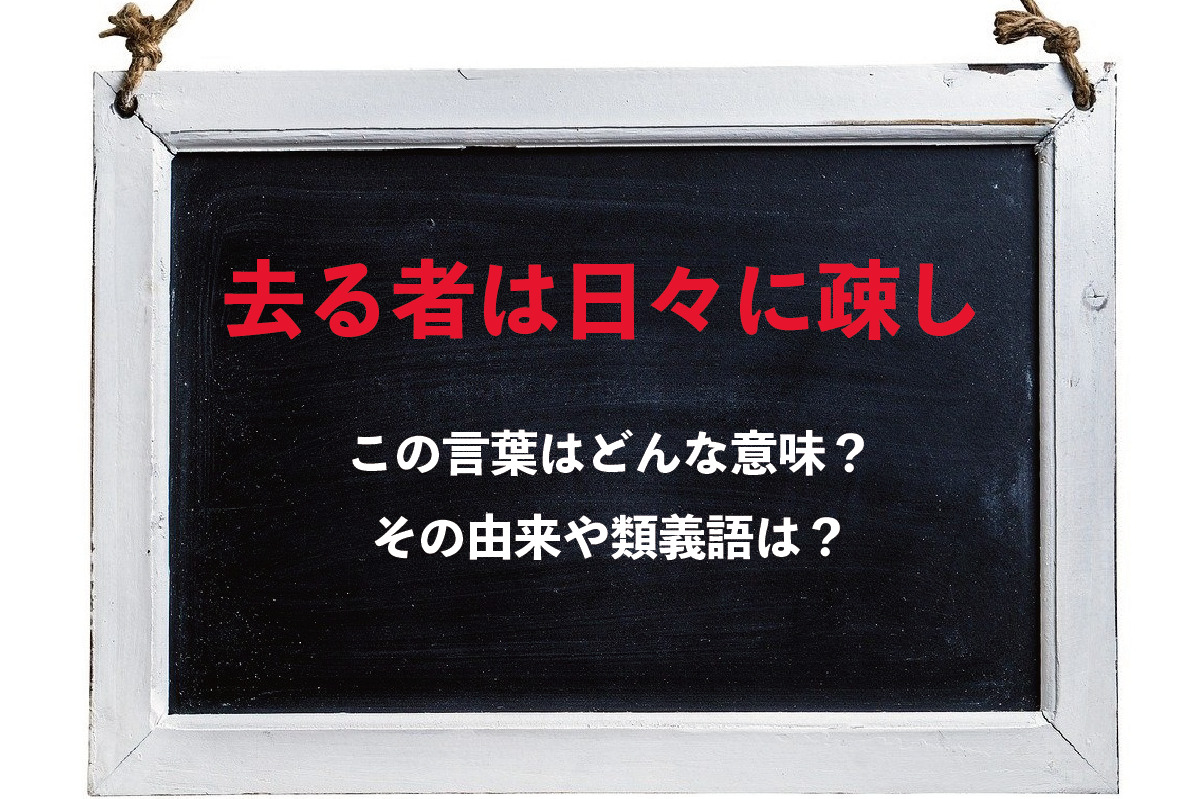
親交のあった人も時間が経てば自然と関係が薄れてしまうことを言った例え、それが「去る者は日々に疎し」です。
この言葉は、古代中国の詠み人知らずの詩から来ています。
ここでは、この「去る者は日々に疎し」という言葉について、その意味や用い方、由来に類義語について見ていきましょう。
目次
「去る者は日々に疎し」とは

まずは「去る者は日々に疎し」という言葉について、その意味や用い方を見ていきましょう。
「去る者は日々に疎し」の意味
「去る者は日々に疎し」は、親交のあった人も時間を経れば関係が薄れていくことを例えた言葉です。
深い交流があった人であっても、関わる機会が減っていけば親しさも失われてしまいます。
そういった人間関係の儚さを言った言葉です。
「去る者は日々に疎し」の対象となるのは『人間』
「去る者は日々に疎し」は、主に人間を対象として使用します。
仲が良く、交流を深めていた相手でも、顔を合わせなくなると疎遠になってしまいます。
人間特有の感情について言った表現なので、物事に対してはあまり使用されません。
「去る者は日々に疎し」の語源

ここからは「去る者は日々に疎し」という言葉の由来を見ていきましょう。
由来は古代中国の詩の一節から
「去る者は日々に疎し」は、古代中国で作者不詳の詩を集めた「文選‐古詩十九首」に出典があります。
その十四首目に「去者日以疎」という詩があります。
この詩には「去者日以疎、生者日以親」という一節があります。
亡くなった人は日に日に忘れられていき、生きている人たちは日を重ねるごとに仲良くなっていく、という内容になっています。
この詩は墓のそばを通りかかった旅人が、望郷の念を詠ったのではないかと考えられいます。
「去る者は日々に疎し」の類義語

最後に「去る者は日々に疎し」の類義語を見ていきましょう。
その類義語としては「間が遠なりゃ契りが薄い」「遠ざかるは縁の切れ目」などがあげられます。
間が遠なりゃ契りが薄い
「間が遠なりゃ契りが薄い」とは、親しい者同士であっても遠く離れれば関係は薄れていってしまうことをあらわしています。
特に、男女の間柄を例えた言葉とされています。
遠ざかるは縁の切れ目
「遠ざかるは縁の切れ目」とは、遠ざかることは縁の切れ目であることの例えです。
親友であろうとも、永らく会っていなかったり、住まいが遠くになったりすることで関係性が薄くなると疎遠になってしまうということを例えた言葉です。
忘れてしまうというよりも、繋がりがなくなるというニュアンスが強い言葉となります。
まとめ
「去る者は日々に疎し」は交流があった人でも、離れてしまえば関係が薄れてしまうということを意味しまうs。
単に人間関係が壊れるというよりは、忘れ去られていくものだという哀愁が込められた言葉となります。
離別はもちろん死別にも使用されます。
類義語としては、「間が遠なりゃ契りが薄い」「遠ざかるは縁の切れ目」などがあげられます。