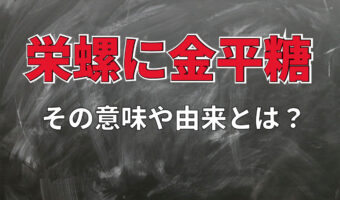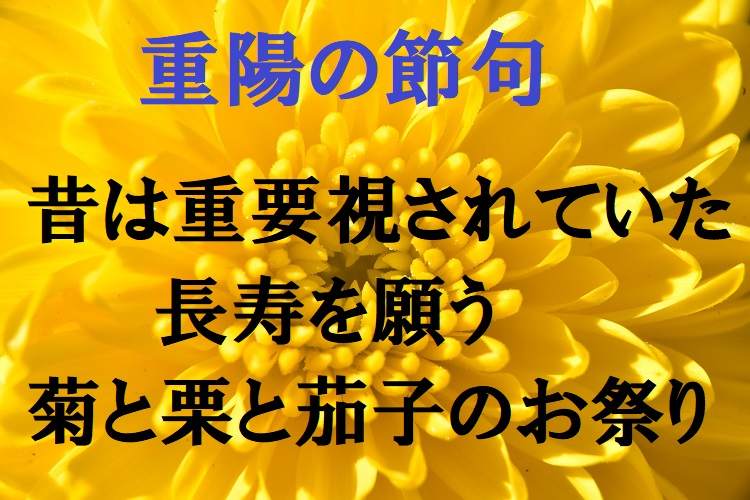
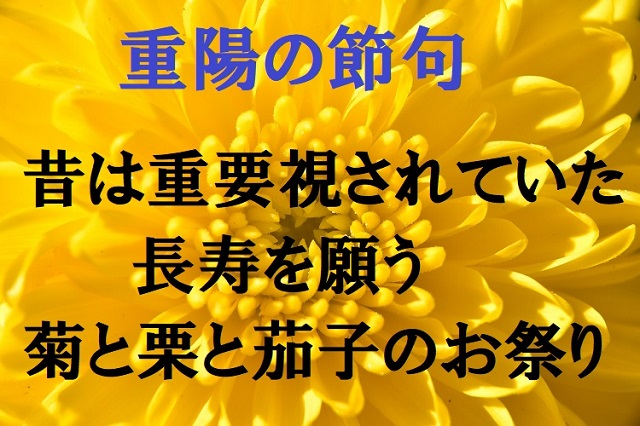
節句の一つ「重陽の節句」を耳にしたことはありますか?
お雛様を飾る桃の節句や、五月人形を出す端午の節句と違い耳にすることのない行事かもしれません。しかしその歴史は古く、日本では平安時代の宮中行事にもなっていたそうです。
また、年五回ある節句の中で最も大切な行事とも考えられていたそうです。かつては重要視されていた節句行事の一つ、重陽の節句をご紹介します。
目次
重陽の節句は菊のお祭り

節句は中国の陰陽思考から始まったもので、奇数の月は陽の気を生むという考えから始まりました。昔は多くの節句があったとされますが、現在日本に伝わっているのは5つ、1・3・5・7・9の月の節句です。
元来、奇数月の同日は陽の気が高まりすぎるため不吉なので、不吉を払うための節句の行事は始まったとされていますが、時が経つにつれ、陽の重なりを吉事とみなされるようになり、現在のように祝われるようになったそうです。
重陽の名前の由来
節句行事は年5回、1・3・5・7・9月にあります。1月は1日が元日であることから7日に人日の節句、または七草の節句と呼ばれています。3月・5月は馴染み深い桃の節句と端午の節句です。7月は節句とは一般的につけませんが七夕の節句で、9月が重陽の節句です。9月の節句がなぜ重陽と呼ばれているかというと、"陽"の気が高まる奇数の最大数9が"重なる"日という点から付けられたとされています。
重陽の節句は最大の奇数9月の節句であり、健康と長寿を願う日でもあったので重要な節句行事とされていました。
菊の節句

節句の行事は奈良時代に日本に入ってきて、平安時代には宮中行事として定着していました。そして奈良時代の訪販から平安時代のはじめにかけて日本に伝わってきたとされる菊の開花時期は旧暦の9月、現在の10月にあたりちょうど時期が重なるため菊を用いて節句のお供えになったことから重陽の節句は菊の節句とも呼ばれています。
菊の花
菊の花は中国において仙人の住む世界に咲く、邪気を払い長寿をもたらすめでたい花とされてきました。「観菊の宴」という宮中行事も古くは行われていました。
菊酒
日本酒に菊の花弁、もしくは漬け込んだ菊の花弁を浮かべたものを菊酒といいます。長寿の効果があるとされたこの酒を飲みながら菊の花を観賞するのが「観菊の宴」です。
菊の着せ綿
これも平安時代の貴族の風習で、前日に菊の花に黄色く染めた真綿を被せておくことで、翌朝に菊の露や香りが綿に移ります。この菊の露や香りがしみ込んだ綿で体を清めると無病で過ごせると考えられていました。
菊湯
菊の着せ綿が民衆に伝わったのが、細かく刻んだ菊の花弁を麻袋に入れて浸かった菊湯です。菊の花弁を直接風呂に浮かべて浸かる場合もあるそうですが、菊には血行の促進と高い保温効果があるので季節の変わり目でもある重陽の節句のころには非常に効果的であったと考えられています。
菊枕
換装させた菊の花弁を枕に入れて作ったのが菊枕です。菊の香りで頭痛や目の痛みに効果があるとされていました。
菊合わせ
江戸時代の中期になると貴族や大名、武士だけでなく民衆にも菊が入手できるようになり、結果、菊の栽培が流行しました。重陽の節句のころになると「菊合わせ」という菊の品評会が行われるようになりました。特に京都や江戸で活発で菊合わせで評価が高かったり新種を発表すると高値が付くという事もあったそうです。
重陽の節句は収穫祭

重陽の節句は菊が開花するだけでなく、実りの秋の時期でもありましたので、民衆の間では収穫祭としてのお祝いがされていました。
七草の節句では"七草がゆ"、桃の節句ではクチナシと菱の実を入れた"菱餅"、端午の節句では柏の葉をつかった"かしわ餅"と菖蒲湯といった行事食や節句料理と呼ばれる食事がありますが、重陽の節句も秋の実りを用いた節句料理があります。菊酒も行事食ではありますが、民衆にはあまり普及しなかったようです。
栗

江戸時代から民衆の間では重陽の節句では栗ご飯を炊いて食す風習がありました。栗もまた聞くと同じころに実る秋の味覚です。栗ご飯を食べる風習から「栗の節句」とも呼ばれていたそうです。
茄子

また、重陽の節句の時期は秋茄子がおいしい時期でもあります。その為、行事食として焼き茄子や煮浸しも食されました。「くんち(9日)に茄子を食べると忠風にならない」とされ、健康のためにも食されていたそうです。
重陽の節句の文化
くんち

九州北部で現在も行われている秋祭り、収穫祭は「くんち」と呼ばれています。これは重陽の節句のがおこなわれる9月「9日」から転じて定着したともいわれています。特に「博多おくんち」「唐津くんち」「長崎くんち」が有名です。
松尾芭蕉がいくつも

有名な江戸時代の俳人、松尾芭蕉も重陽の節句に関する俳句を残していますのでいくつかご紹介します。
十六夜の 月を見はやせ 残る菊
十五夜の翌日の月、重陽の節句の翌日の菊、どちらも余りものや見るまでもないものとされているけれども、決して前日の月や菊に比べて見劣りするものではない。と詠んでいます。
草の戸や 日暮れてくれし 菊の酒
重陽の節句を祝う菊酒が届いた、という句です。しかし日中にではなく「日が暮れてから」届いたとあることから、一種の切なさを感じる句になっています。
菊の香や 奈良には古き 仏達
菊の香や 奈良は幾世の 男ぶり
菊の香に くらがり登る 節句かな
この三句は同日、1694(元禄7)年の重陽の節句の日に詠まれました。特に3句目の「菊の香に くらがり登る 節句かな」は中国では重陽の節句の時は近くの山に登るというが、私はいま菊の香りを頼りに暗い峠を登っている。と詠んた一句です。
まとめ
松尾芭蕉がいくつもの句を残している事から、江戸時代は確かに重陽の節句は広く民衆に根付いた節句のお祝いだったようです。現在では9月で健康長寿というと「敬老の日」しか思い浮かべませんが、せっかくの古くからある風習なので、栗ご飯と茄子の煮浸しを食べ、菊の花弁を浮かべた日本酒と堪能する日を実践するのも面白いかもしれませんね。