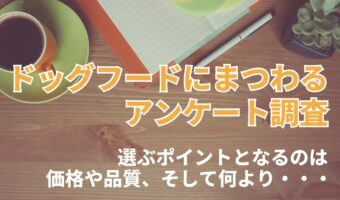犬の鳴き声と言えば「わんわん」。猫の鳴き声と言えば「にゃーにゃー」などが一般的ですよね。ところが、時代によって動物の鳴き声の表現の仕方が違っていたようです。皆さんは鳴き声で動物がわかりますか??
目次
時代で変わる動物の鳴き声クイズ
これから昔の表現で動物の鳴き声を表記していきます。その鳴き声の動物が何なのか考えてみてください!
Q1.「ひよ」「びよ」「びよびよ」
「びよびよ」鳴き声がこう表現されたどうぶつはなんでしょう?これは狂言などでも有名ですね!身近なあの動物ですよ!

平安時代の文献「大鏡」には「ひよ」と表記されているようです(当時は濁音と清音を明確に区別する習慣がなく、全て清音で記載)。江戸時代の初期には「びよ」「びよびよ」などと表記。その後、江戸時代の途中から「わんわん」に。
答えは犬でした

犬の鳴き声が「びよびよ」と聞こえたことってあります?自分は一度もないですが、昔の犬って鳴き声違ったのかな??って思うくらい今とかけ離れていますよね!
Q2.「ねうねう」
「ねうねう」と鳴く動物は何でしょう?これは確かにそう聞こえなくもないので、よーく考えればわかるかね
鎌倉時代までは「ねうねう」と表記されていたようです。こちら答えは猫でした

猫の鳴き声は確かに「ねうねう」と言われればそう聞こえますよね。
Q3.「しうしう」「ちうちう」
「しうしう」や「ちうちう」と鳴く動物はなんでしょう?「ちうちう」の方がより現代に近いかな
室町時代頃までは「しうしう」と表記されていたようです。江戸時代頃から「ちうちう」に。

正解はスズメです時代とともに徐々に変化したのがなんとなくわかりますね。
Q4.難問「ここ」
「ここ」と鳴く動物は何でしょう?現在の鳴き声とは全く異なっており、これは想像できないかもしれませんね。
奈良時代には「ここ」と表記されていたようです。室町時代以降、「きゃーきゃー」に変化していきました
正解は猿です

これは難しいですね!現代では「キーキー」や「ウキー」などと表すことが多いでしょうか。室町時代以降には「きゃーきゃー」となっており、狂言では猿の鳴き声は「きゃーきゃー」と表現します。「きゃーきゃー」はわかりそうですが「ココ」は全く想像もつきませんでした。
Q5.「しうしう」
あれ?これはさっきもあったスズメでは?と思うかもしれませんが、別の動物です。他にも「ちうちう」や「ちいちい」と表現されることも
室町時代までは「しうしう」、江戸時代になると「ちうちう」「ちいちい」に、この動物はねずみでした。

すずめとほぼ同じような表現をしていたんですね!でもこれは現代でも「ちゅうちゅう」ですので、昔から割と変わってないんですね!
Q6「ころ」「から」「ころく」
、
「ころ」「から」「ころく」は奈良時代の表現らしいです。この動物はいったい何?
鎌倉・室町時代には「こかこか」と変化していき、江戸時代には「かあかあ」に!こうなるともうお分かりですね!そうこれはカラスでした

カラスは江戸時代ごろには既に今と同じ表現になっていました。
なぜ表現が変わった?
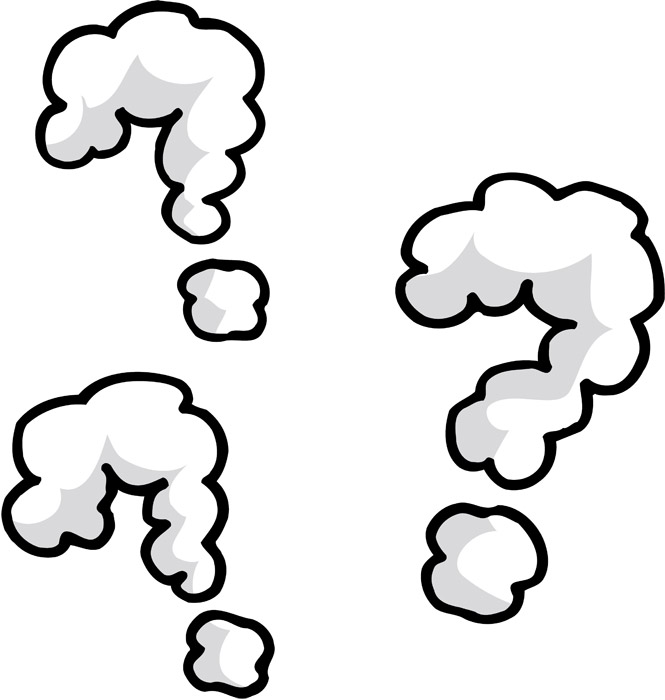
様々な動物の鳴き声は昔から変化してきました。でもなぜ同じ動物の鳴き声なのに表現が全く異なるのでしょうか?それには人間とその動物の距離感が変わるからという説があります。
犬は江戸時代途中から鎖をつけて人に飼われるようになり、猿は室町時代以降に飼われるようになったとされています。ちょうどその頃から鳴き声の表記が変わっていることからも、ペットとして飼うこと(ご主人に懐いたり?)による影響もあったのでしょうか(そういう説もあるようです)。
単にその時代の言葉の表記の違いと言えばそれまでですが、人間と動物との関係の変化によって鳴き声も変化したのか、まさか動物の鳴き声自体が時代によって変化したのか…などと考えると奥が深いですね!