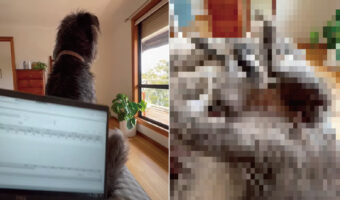日本人にとってもネズミは馴染み深い動物ですが、英語ではこのネズミはラットやマウスと呼ばれますよね。
では、このふたつの呼び方はどのような違いから来ているのでしょうか。
ここでは、このラットとマウスが持つ英単語の違いはもちろん、それぞれの意味についても見ていきましょう。
目次
ラットもマウスもネズミのこと

ラットやマウスも大枠ではネズミを指します。
このネズミは、種類だけで見れば世界に1,000種類以上いるのだとか。
日本での認識
日本ではネズミとしてまとめてしまっているため、野ネズミも家ネズミも全部ネズミという枠で考えます。
干支のネズミもペットとなるネズミも害獣のネズミもまとめてネズミと呼ぶため、その違いについては明確にされていません。
種類だけで見ればそれぞれの個体に名前があり、細分化されてはいます。
しかし、呼称としての呼び名としてはネズミのみを使うことが一般的です。
英語圏では大きさで区別

日本に比べると英語圏では大きさで区別することが多いです。
日本では全部ネズミなのですが、英語圏ではサイズでつかいわけがされているのです。
小さいのはマウス
英語圏ではハツカネズミなどの小型の個体をマウスと呼びます。
主に体長5cm~10cmほど、体重16g~28gほどの小さなネズミが該当します。
大きいものはラット
英語圏ではドブネズミなどの大型の個体をラットと呼びます。
体長18cm~28cmほど、体重200g~700gほどのネズミを指すことになります。
英語圏のイメージは
あくまでも英語圏のイメージであるものの、小柄で愛らしさを感じるのがマウスで、大きくときに汚らしさを感じるものがラットとなるという認識もあります。
ちなみに英語圏のスラングではマウスを臆病者、ラットは裏切り者や卑怯者という位置づけで使うことが多くあります。
実験動物としてのラットとマウス

ネズミは動物実験としても長く使用されてきています。
そして、この場面でもラットとマウスが使い分けをされています。
実は明確な違いが!
ネズミは人の遺伝子構造とほぼ同じで、安価かつ繁殖させやすいため、実験に用いられることが多いです。
実験用ドうつとしてのネズミは、ラットとマウスで違いが明確だと言われています。
マウス
マウスは主にハツカネズミを改良したもので、歯は先端に向けて細く成長します。
アルビノで白い個体が多く、見た目は美しいですが、ただ、尿の匂いが強いという特徴があります。
ラット
ラットはドブネズミを改良したもので、その歯は鋭く成長すると2段階に厚さが変わるという特性があります。
主にブラックやブラウンなど黒い個体が多いこともあって、見た目も良いとは言えません。
モルモット
日本で医学実験用のネズミとして用いられるのは、テンジクネズミが一般的となっています。
モルモットは、ラットやマウスとは違い、顔が丸いこともあってウサギやカピバラやフェレットを思わせる外見をしています。
比較的身体は大きく、実験にも用いやすいことから日本でも使われるようになりました。
まとめ
日本ではネズミと呼ばれるものは、英語圏ではそのサイズ感などからラットだったりマウスだったりと呼び分けがされています。
小さなネズミがマウス、大きなネズミがラットと呼ばれていますよ!