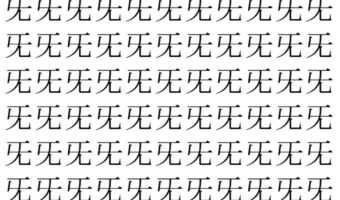「基準」と「規準」は、どちらも「きじゅん」と読みますが、違う意味を持っています。
同音のうえ、使われる場面も似ているため、会話の中で用いるときは勘違いを招かないような配慮をしなければなりません。
これらの言葉を頻繁に使う教育現場では、「基準(もとじゅん)」「規準(のりじゅん)」と読み、誤解がないよう区別をしているんですよ。
今回は、どちらも「きじゅん」と読む同音異義語の「基準」と「規準」の違いについて見ていきましょう。
目次
「基準」とは

「基準」の意味と使用例を見ていきましょう。
基準の意味
「基準」とは、物事を判断する際に基礎とする標準、満たすべき要件のことです。
類語として、水準・目安・物差し・標準などが挙げられます。
基準の使用例
例1:良い人材を雇うための採用基準を設けた。
例2:近年の建物は厳しい耐震基準をクリアしているため、耐震性に優れている。
例3:採点基準は6項目あり、各10点満点です。
例4:漢検2~1級の合格基準は、200満点中160点です。
「規準」の意味

「規準」の意味と使用例について見ていきましょう。
規準の意味
規準は、物事を判断する際の守るべきルールや手本、定められた規範や規則のことを意味します。
類語として、規範・規定・定め事・規律などが挙げられます。
規準の使用例
例1:企業イメージを高め、社会的な信用を獲得するためにも、コンプライアンス規準を遵守する。
例2:企業行動規準を元に、社会人として守るべきルールを徹底する。
例3:書籍『鉄筋コンクリート構造計算規準』には、鉄筋コンクリート造の構造計算に関する、あらゆる規定が示されています。
例4:ごみのポイ捨てなど、道徳規準の低下が囁かれる。
基準と規準の違い

教育機関では「基準」と「規準」を用いる機会が多くあるため、誤解がないように「もとじゅん」「のりじゅん」といい、区別をしています。
学校では、授業や成績に関する言葉で「評価基準」と「評価規準」がありますが、この二つには大きな違いがあります。
評価基準と評価規準
学校で成績などの評価を決めるときに「評価基準」と「評価規準」が用いられます。
同音なのでややこしいですが、違う意味なんですよ。
評価規準
生徒につけたい力を具体的に定め、何を評価するか文章にしたものです。
各教科の目標や各学年の目標などがそのよりどころになり、質的なものを指します。
評価基準
「評価規準」で示されたつけたい力に対して、どの程度の習得状況であるかをはっきりさせたもの。
「A・B・C・D」の記号や「1・2・3・4」の点数で評価され、量的なものを指します。
法令用語としての基準と規準
法令用語としても、本来の意味と同様で「基準」は「標準、満たすべき条件」、「規準」は「手本とすべきもの」をあらわしています。
しかし、新聞誌上で使われるのは「常用漢字で二様以上の表記が慣用されている語の一方を統一的に使う」と決められていることから、厳密な意味に拘らず「基準」で統一されている事のが一般的です。
英訳での基準と規準の違い
英訳では、日本の専門研究者の間では、基準を「standard」「reference」、規準は「criterion」とすることで落着しています。
基準:(standard, reference) その達成目標の実現状況を判断する指標を指す
規準:(criterion) 達成目標を指す
しかし、漢字本来の意味と英語の語義の整合性の観点では、厳密に正しい英訳ではないと困惑している専門家もいらっしゃるようです。
例えば「standard」の和訳は豊富で、「基準」「規準」「標準」「水準」「規格」などと訳され、「criterion」は「尺度」という意味を持つからです。
意味を理解している言葉でも、専門用語を正しく翻訳することは、とても難しいことなんですね。
まとめ

「基準」と「規準」は、同じような状況で使われることがある言葉ですが、その意味は厳密には異なります。
「基準」は標準、満たすべき条件、「規準」は手本とすべきものといった意味があります。