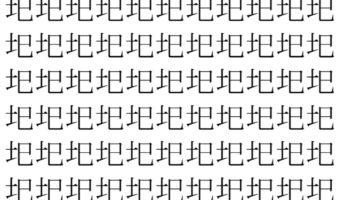青や紫色の小さな花をたくさん咲かせる「勿忘草(ワスレナグサ)」。
可憐で儚い雰囲気の花になぜ「勿忘草」なんていう切なげな名前が付いているのでしょうか。
そんな「勿忘草」という名前、そして花言葉は、ドイツに伝わる悲恋伝説に由来があるとされています。
ここでは勿忘草の特徴や花言葉、そして名前や花言葉の由来とされる悲恋伝説についてご紹介いたします。
目次
勿忘草について

一度聞いたら忘れられない名前の花「勿忘草」がどのような植物をご紹介いたします。
分布地
ヨーロッパ原産の勿忘草は、ユーラシア大陸・アフリカ大陸・オセアニアなど北半球の温帯から亜寒帯地域に、約50種類が分布しています。
小さくて可憐な花のイメージとは逆に、こぼれ種からも増えていくほど強い植物です。
開花時期
9~10月に種まきをして、3月下旬~6月上旬(冷涼地では4月~7月)に開花する春の花です。
春、散歩をしながら無数に咲いた勿忘草を見られるのは、とても素敵な光景です。
花の特徴
勿忘草の花の色には青や紫が多く、花径5mm~10mmほどの小花を土壌から20~50㎝くらいの高さに密集して咲かせます。
園芸品種では白やピンク色の花を咲かせるものもあります。
耐寒性に優れていて本来は多年草ですが、日本での栽培は暑さと過湿に耐えられないため、秋まきの一年草として扱われています。
しかし日本でも、北海道や長野県などの冷涼地では夏を越せる地域もあり、長い間楽しむことができます。
日本における勿忘草
ヨーロッパ原産の勿忘草が日本に渡来したのは、明治時代に園芸業者が「ノハラワスレナグサ」を輸入したのが最初だといわれています。
ワスレナグサ属の中で、唯一の日本在来種は「エゾムラサキ」です。
青や紫色をした小花は勿忘草と区別が難しいほどよく似ており、日本の園芸業界では勿忘草として流通しています。
現在では野性化した「エゾムラサキ」が、日本全国の日当たりの良い林や道端に自生分布しています。
勿忘草の花言葉と名前の由来

勿忘草の花言葉と名前の由来をご紹介します。
勿忘草の花言葉
勿忘草は、世界中に花言葉があります。
全般的な花言葉
勿忘草全般の花言葉は、「真実の愛」「誠の愛」「私を忘れないで」「真実の友情」です。
青や紫色、白やピンク色の花がありますが、色別の花言葉は付けられていません。
主に「愛」を表す花ですが、フランスでは「友情」の花ともいわれています。
世界の花言葉
『true love(真実の愛)』(イギリス)
『memories(思い出)』(イギリス)
『Du sollst an mich denken(汝、私について考えよ)』(ドイツ)
『Hore, was das Blumchen spricht.(花が何を話すか聞いて)』(ドイツ)
『souvenir fidele(忠実な記憶)』(フランス)
『amour veritable(真実の愛)』(フランス)
『amitie sincere(誠実な友情)』(フランス)
名前の由来
日本名の「勿忘草」や「忘れな草」は、1905年(明治38年)植物学者の川上滝弥さんにより、英語の名前や花言葉を由来にして名付けられました。
勿忘草の英名は「forget-me-not」、花言葉と同じく「私を忘れないで」という意味です。
花言葉と英語の名前両方から、「勿忘草」という和名が付けられたといわれています。
勿忘草(ワスレナグサ)にまつわる伝説

勿忘草にまつわる、悲しい恋の伝説をご紹介いたします。
中世ドイツのドナウ川悲恋伝説
勿忘草には、中世ドイツのドナウ川を舞台とした悲恋伝説があります。
若い騎士ルドルフは、恋人のベルタとドナウ川のほとりを散歩していました。
ドナウ川の岸辺に咲く可憐で美しい青い花に目を奪われたルドルフは、ベルタのために花を摘もうと岸を降りていきました。
ところが、ルドルフは花を摘んだ途端に思いがけず川へ落ちてしまったのです。
川の流れに飲まれていくルドルフは、最後の力を振り絞ってベルタへ花を投げ渡し「Vergiss-mein-nicht!(僕を忘れないで!)」という言葉を残して川底へ沈んでいってしまったのでした。
悲しみに暮れたベルタは、ルドルフの墓にその花を供え髪にも差し、彼を思いながら生涯を過ごしたといわれています。
この物語の、ルドルフ最期の言葉「Vergiss-mein-nicht!(僕を忘れないで)」から名前が付けられました。
勿忘草に秘められた悲しい恋の物語は、世界中で花言葉にまつわる話として今も伝わっています。
まとめ

小さくて可憐な雰囲気を持ちながらも、本当は強い花「勿忘草」。
その名前そして花言葉は、ドナウ川を舞台とした悲恋伝説から来たとされています。
花言葉としては、真実の愛や私を忘れないでなどがあります。