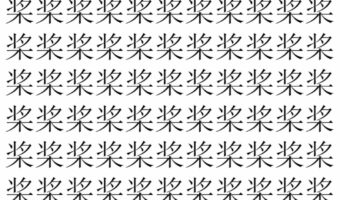江戸時代など昔の女性が、歯を真っ黒に染めた「お歯黒」を絵などで見たことがある人は多いでしょう。
歯が真っ黒になった様相はとてもインパクトがありますよね。
ではなぜ昔の人たちは、現代の私たちの意識では強烈なインパクトのある、お歯黒を施していたのでしょうか?調べてみたところ、実は非常に実用的な存在だったことが分かりました。
目次
お歯黒の目的

なぜ歯を黒く塗ったのでしょうか?その目的は主に下記の4つがあったとされています。
・成人の証
・既婚者の証
・口の健康維持
・美(化粧)
お歯黒は「大人の証」
現代では大人になった証というと、成人式くらいしかありませんが、かつての日本は大人であることを証明する通過儀礼が様々な形で行われていました。
例えば武士の元服も、大人になったことをあらわす通過儀礼のひとつです。そして、お歯黒もまた通過儀礼のひとつでした。
平安時代の貴族階級の中で、お歯黒は「成人の証」として行われていました。その当時は男女とも17~18歳が成人とされており、その年頃になった男女は歯を黒く染めることで成人であることを表していたそうです。
そしてその後、時代が進むにつれて成人する年齢は低くなり、戦国時代には10歳にも満たない子にお歯黒を付けて成人とみなし、政略結婚をさせていたといわれています。
さらに時代が下り、江戸時代になるとお歯黒文化は庶民にも広まっていき、多くの既婚女性がお歯黒をするようになったそうです。一方、男性のお歯黒文化は貴族や武士階級の中で消失してしまいました。
お歯黒で「口の健康が守られる」
お歯黒をする理由には「口の健康を守る」という目的もありました。
お歯黒の成分である「五倍子粉(ふしこ)」には、歯質を強化する作用があり、口腔内の悪臭・虫歯・歯周病の予防効果もあったそうです。
お歯黒は「化粧の一種」
お歯黒は当時の「美」であり、化粧の一部としても用いられてきました。つまり、お歯黒は今でいうベースメイクと同じだったわけです。
また、お歯黒は歯を目立たなくするためにも用いられていました。昔も今と変わらず、歯並びが悪いと美しいとはされていなかったため、歯並びの悪さを隠すためにお歯黒を塗っていたそうです。
その他にも、お歯黒を塗ることで「柔らかく、優しい表情に見せる」効果があったとも言われています。
当時はおちょぼ口が似合う人が美人とされていたため、お歯黒で歯を目立たなくさせることで、日本女性らしい奥ゆかしさを表現していたそうです。
お歯黒に関する勘違い
お歯黒はその異様な見た目から、外人にはわざとやっているように見えるそうです。
江戸時代末期、鎖国していた日本にやってきたアメリカやイギリスの西洋人たちは、お歯黒を塗って故意に女性を醜くすることで、女性の貞操を守る役割があったのでは?と勘違いによる推測も生まれました。
実際には、「美しさ」を表現するためにお歯黒がしているわけですから大きな勘違いですね。
現在でもテレビなどの演出道具でお歯黒が用いられる際は、醜悪さや滑稽さを演出する方向で使われることが多いです。しかし実際の意味は異なりますので、間違えないようにしたいですね。
お歯黒の歴史
お歯黒の歴史は非常に古く、日本には古墳時代から存在したとされています。明治時代末期まで見られたお歯黒の起源に関してはいくつかの諸説があるのでご紹介します。
お歯黒はどこからきたのか
お歯黒がどこからきたのか、その起源ははっきりとは分かっていません。現在推定されているお歯黒の起源は以下の3つです。
・日本にもともとあった「日本古来説」
・大陸(中国)からやってきた「大陸渡来説」
・南方民族が持ってきた「南方伝来説」
もともと草木や果実で染める習慣がありましたが、そこに鉄器文化が伝わって来たことで鉄を使う方法に変わったという複数の説の組み合わせもあり得るようです。
古代から用いられるお歯黒
古墳に埋葬された人骨や埴輪(はにわ)にはお歯黒の跡が見られることから、お歯黒は古墳時代にすでにあったともされています。
また、奈良時代に東大寺の大仏建立した頃、中国から来た僧侶「鑑真(がんじん)」が、質のよいお歯黒の製造法を伝えたともいわれています。
お歯黒は平安時代から流行り始める
お歯黒が流行し始めたのは平安時代のことです。
ただ平安時代にお歯黒を塗ることができたのは貴族や武士階級など上流階級のみ。庶民も行うようになったのは室町時代になってからでした。
明治時代、お歯黒廃止命令が出される
江戸時代になると男性がお歯黒をすることはほぼなくなり、既婚女性のみの化粧として定着しました。
しかし、明治3年には政府から皇族・貴族に対してお歯黒禁止令が出されます。それに伴って民間でもお歯黒文化は全国的に衰退し、明治後期になると東北など一部地域に限って利用されました。
昭和初期にはその東北など一部地域でも廃れたことで、お歯黒文化は完全になくなりました。
お歯黒はなにでできているの?
お歯黒は、イカ墨を食べた時のように歯が真っ黒になります。白い歯が真っ黒になるお歯黒は、何で出来ているのかとても気になりますよね。
一般的なお歯黒の原料と成分
お歯黒の一般的な原料は「鉄漿水(かねみず)」と呼ばれる酢酸に鉄を溶かした溶液です。
鉄漿水は茶褐色で悪臭がありますが、これを楊枝で歯に塗った後に「五倍子粉(ふしこ)」と呼ばれるタンニンを多く含有する粉を上塗りします。
鉄漿水と五倍子粉を交互に塗り重ねることで、鉄漿水の酢酸第一鉄が五倍子粉のタンニン酸と結合し、非水溶性になることで黒変し、歯が真っ黒になるそうです。
鑑真が伝えたお歯黒は安心安全!だけど高い!
鑑真が中国から伝えたお歯黒は、五倍子粉・緑バン・カキ殻を合わせた粉末から作られました。
このお歯黒は拒否反応が少なく、安全性が高いというメリットがありましたが、鉄漿水と比べると高価だったそうです。
まとめ

自分の歯を真っ黒に染める「お歯黒」は、成人や既婚の証としてはじまり、後にメイクの一種として定着しました。表情を柔らかく見せる効果もあったそうです。
また虫歯など口腔病の予防効果もあるそうなので、実用的な存在だったようです。
お歯黒=醜い、滑稽というマイナスイメージがあるかもしれませんが実はそんなことはなく、当時のお歯黒は美の象徴でした。大衆に広く親しまれてきたお歯黒の歴史はとても興味深いですね。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
出典:Wikipwdia(お歯黒)