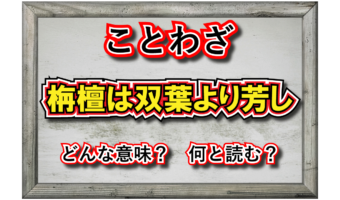勝敗を表すとき、勝った場合は「白星」、負けた場合は「黒星」と呼びますよね。
特にスポーツなどの勝負事で用いられることが多いです。
では、なぜ勝敗を表す際に白星や黒星と呼ぶようになったのでしょうか?
ここでは、その意味や由来などについて見ていきましょう。
目次
白星と黒星の意味

「日本代表が初白星をあげました!」などと使われる白星と黒星は、スポーツなどの勝負事でよく言われます。
では白星と黒星ではどちらが勝ちで、負けなのでしょうか?
勝ちが白で、負けは黒
白星は「勝ち」、黒星は「負け」を意味します。
主にスポーツで用いられる
この白星・黒星は主にスポーツで用いられています。
特に大相撲では力士の勝敗を白黒で表すので、馴染み深いですね。
また、将棋や囲碁などの勝負事でも使われています。
元は相撲から

この白星・黒星という表現は、相撲で用いられるようになったのが始まりです。
相撲の星取表
相撲では、勝敗結果が一目見てすぐ分かるように星取表が用いられています。
この星取表は白と黒の丸印で、試合の勝敗を示した表です。
勝ちを白丸、負けを黒丸で表し、それぞれ「白星」「黒星」と呼びます。
日本最古の星取表は1761年10月のもので、実に250年以上も前から使われていたんです。
なぜ丸なのに星?
なぜ白丸、黒丸を「星」と呼んだのでしょうか?
それは、江戸時代頃の日本では丸い印のことを「星」と呼んでいたことが由来しているのです。
江戸時代までの日本は、丸印が星に見立てられていたんですね。
白星・黒星の由来

白星・黒星の由来は、相撲にあります。
その由来は、相撲で使われていた星取表が由来となっています。
星取表から
相撲では、勝敗がすぐに見分けがつくよう星取表が使われています。
この星取表は「勝ち=〇」「負け=●」の記号で表しています。
そしてこの星取表から白星・黒星と言われるようになったとされています。
ただし、なぜ勝ち=〇、負け=●になったのかは定かではありません。
土が付くのが理由というのが有力
勝ち=〇、負け=●となった理由ははっきりとは分かりませんが、取り組みで負けて倒されると土が付きます。
その土がついた相撲取りの姿を黒と例えたことから来たのではないかとされています。
この説が有力ではありますが、はっきりとしたことは分かりません。
金星というのもある

相撲では、「金星(きんぼし)」という言葉も使われます。
ニュースで「〇〇関が金星をあげました!」と言っているのを聞いたことがある人もいるでしょう。
では、この金星とはいったい何のことでしょうか?
前頭が横綱に勝つこと
金星とは、前頭の力士が横綱に勝つことです。
相撲には10種類の階級があり、その中でも横綱、大関、関脇、小結、前頭は「幕内(まくうち)」と呼びます。
幕内の中で最も低い階級の前頭が、一番階級の高い横綱に勝つというのは凄いことなのです。
そのため通常の「白星」ではなく、「金星」と言います。
白よりもすごく価値がある星なので、「金星」と言われるようになりました。
ちなみに小結以上が横綱に勝っても、「金星」とは言わず、通常通りの「白星」です。
相撲から派生
この金星という言葉は、白星・黒星と同様に、相撲から派生して様々な場面で用いられています。
例えば、明らかに勝てないと思えた相手に勝利した場合、「大金星を上げた」という表現がされます。
まとめ

勝敗を表す白星・黒星は、白星=勝ち、黒星=負けを意味します。
これは相撲で使われる星取表が由来となっていて、現在でも大相撲では勝敗が一目で分かるように勝ち=〇、負け=●で表しています。
相撲では白星・黒星以外にも、大勝利を上げることを「金星」と呼んでおり、相撲用語以外でも用いられています。