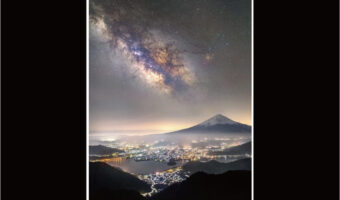「シュウカイドウ」という花を漢字で、「秋海棠」と書きます。
しかしこの花、実は夏に咲く花なんですよね。
夏に咲くのに、なぜ秋と名前に付くのでしょうか?
今回はそんな不思議な花「シュウカイドウ」について、花言葉なども併せて見ていきましょう。
目次
シュウカイドウとは?

シュウカイドウは、シュウカイドウ科の植物です。
シュウカイドウ属に分類されますが、この属名を英語では「Begonia」とされていることから、ベゴニア属ともいわれています。
特徴
シュウカイドウは、淡いピンク色の花びらと、黄色のおしべを持つ花です。
歪んだハート形になっている葉っぱがかわいさ抜群なうえに丈夫で繁殖も簡単なことから、日本各地で栽培されています。
各地で栽培されている他、野生化もしています。
主に湿気が多くて直射日光が当たらないような薄暗い場所で咲くので、機会があれば探してみるのもいいかもしれませんね。
原産
シュウカイドウは日本で野生化していることもあり、日本原産だと思われやすいですが、その原産地は中国です。
日本に来たのは江戸時代
現在では日本各地で野生化したシュウカイドウを見ることができますが、平安時代では見られない光景でした。
なぜなら、シュウカイドウは江戸時代に中国から伝来した花だからです。
江戸時代の初めに園芸用として持ち込まれたものが定着した、いわゆる帰化植物といわれる植物です。
シュウカイドウの花言葉

シュウカイドウの花言葉は、主に恋に関連する花言葉も多いので、その手の話が好きな人は要チェックですよ!
花言葉は4つ
シュウカイドウの花言葉は以下の4つとなっています。
片思い
恋の悩み
未熟
自然を愛す
片思いをしている人や恋の悩みを抱えている人には、ぴったりの花と言えるかもしれませんね。
では、なぜシュウカイドウがそのような甘酢っぱい恋に関する花言葉となったのでしょうか?
花言葉の由来
シュウカイドウの花言葉で、特に「片思い」に関してはハート形の葉の片方が大きくなるところに由来しているといわれています。
また、「恋の悩み」に関しては花やハート状の葉が垂れ下がっていてうなだれたように見えることに由来しているそうです。
シュウカイドウは秋を代表する花

シュウカイドウの漢字表記は「秋海棠」となりますが、夏に咲く花です。
ここからはそんなシュウカイドウの開花時期や名前の由来について見ていきましょう。
開花時期
シュウカイドウの開花時期は、7月下旬~10月となっています。
夏の盛りから秋の始まりにかけて咲く花で、主に林床など湿り気のある半日陰で茂るように咲きます。
名前の由来
夏から秋にかけて咲くシュウカイドウが、なぜ「秋海棠」と書くようになったのでしょうか。
これにはある理由があります。
「海棠(カイドウ)」という4月~5月に咲くバラ科の花があるのですが、シュウカイドウはそのカイドウに似ていることから名前が来ています。
春から夏にかけて咲くカイドウと区別するために、秋海棠(シュウカイドウ)と呼ばれるようになったわけです。
ではなぜ秋なのか、それは昔の暦に由来します。
旧暦では7月~9月は秋とされています。
ちなみにこの旧暦の7月~9月を新暦に換算すると、おおよそ8月~10月になり、ちょうどシュウカイドウの咲く時期となります。
まさしく秋に咲く花というわけですね。
なお、シュウカイドウは別名で「瓔珞草(ヨウラクソウ)」とも呼ばれます。
これは仏像の装飾具である「瓔珞」にちなんでいます。
「シュウカイドウ」は初秋の季語
8月から咲き始める、シュウカイドウは初秋の季語です。
花そのものを季語として使うことができるため、俳句や短歌を詠む際は、秋を表現するのに使えます。
松尾芭蕉や正岡子規なども、シュウカイドウをテーマに俳句を詠んでいます。
シュウカイドウという響きがまた美しいですよね。
まとめ
シュウカイドウの花言葉には恋愛に関するものが多く、「片思い」「恋の悩み」などがあります。
7月の終わりから咲き始めるのに、漢字で「秋海棠」と書くのは、旧暦では7月〜9月がちょうど秋にあたるからです。
そのため、シュウカイドウは秋の季語ともなっています。