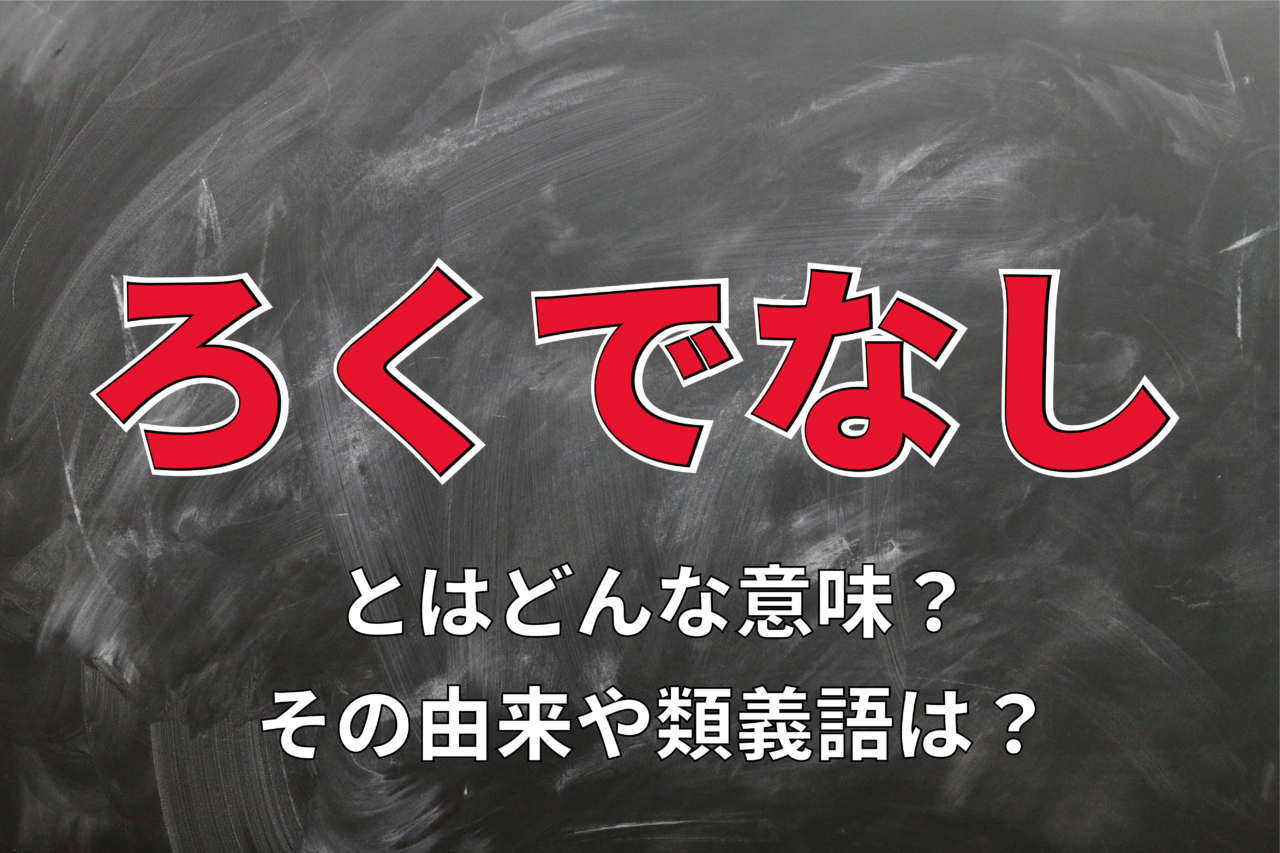
「ろくでなし」は、不真面目な人やどうしようもない人などを指して使われます。
その語源は、「まじめでない」につながりがあります。
そこでここでは、「ろくでなし」という言葉の意味はもちろん、どういう人を指して用いるのか、そしてその語源について解説していきます。
目次
「ろくでなし」とは

まずは、「ろくでなし」がどういう言葉なのか見ていきましょう。
「ろくでなし」の意味
ろくでなしとはのらくらしていて役に立たない人物のことです。
また、怠けている人や性根が歪んでいる人などを指して使うこともあります。
物事を指すことにはあまり使われず、主に人に対して使われる言葉となっています。
「ろくでなし」といわれる人
人に対して用いる「ろくでなし」という言葉は、役立たずと評される人や、くだらないことをする人、性根がねじ曲がっている人のことなどを指します。
怠け者やならず者を意味することもありますし、世間の常識を逸脱して不真面目なことをする人などを指したりもします。
対象となる人物を侮辱する他、軽蔑の感情を込めて使われます。
「ひとでなし」はまたニュアンスが異なることば
ろくでなしと同じような言葉に「ひとでなし」という言葉があります。
この「ひとでなし」とは、人道に反することをする人のことです。
恩義や人情を重んじない人、人間らしい心を持っていない人に対して用います。
その人の人生観であったり人格を強く否定する際に用いられるけいこうにあります。
「あなたはひとでなしよ!」というように、その人の存在を拒否する際などにも用いられます。
酷薄な人や冷酷非道な人という意味で使われる言葉です。
ろくでなしよりもひとでなしの方がより強い侮辱や軽蔑の意味が込められています。
また、優しさや思いやりがないという意味で使用されることもあります。
類義語としては「畜生」や「極悪人」や「鬼」などがあります。
どれも人を罵る際に使われる言葉です。
「ろくでなし」の由来

ろくでなしの「なし」は否定形というのが想像がつくと思います。
しかし、ろくでなしの「ろく」にはどのような意味があるのでしょうか。
ここからは、「ろくでなし」という言葉の成り立ちについて見ていきましょう。
「碌でなし」の「碌」は当て字
ろくでなしの漢字表記は「碌でなし」です。
しかし、本来は「陸でなし」と書くのが正しいとされています。
ではなぜ「碌」を使うのかといえば・・・、この漢字表記は当て字なんだとか。
「ろくでなし」の語源
「ろくでなし」という言葉は、「陸」という漢字からきています。
「陸」というのは、まさに陸地の事です。
そして、平らなこともあらわしています。
この意味から、人に対しては「真面目」をあらわす言葉として使われていました。
正常なことやまともなことを指しているのです。
また、気分の平らかなことや安らかなことも表現する際に用いられていました。
そして、「ろくでなし」は真面目ではない人という意味で「陸ではない」から変化して生まれたのです。
つまり、「陸」の否定形が「ろくでなし」ということになります。
なちなみに、「碌」はその当て字であると前述しましたが、「碌」単体であれば「陸」と意味は同じです。
ろくでなしの類義語とその由来

ろくでなしは役立たずなどのことを指して言うことが多く、その類義語としても「うどの大木」や「白豆腐の拍子木」などがあります。
ここからはこれら類義語についてもチェックしていきましょう!
うどの大木
「うどの大木」とは、体ばかり大きくて役に立たない人の例えです。
この言葉は、植物のウドの茎が持つ性質が起源となっています。
ウドの茎は、木のように長く成長します。
しかし、実際には柔らかいので木材としては使えません。
そこから、見た目ばかりで役立たないことをウドになぞらえて「うどの大木」と呼ぶようになったのです。
白豆腐の拍子木
「白豆腐の拍子木」とは、見かけは立派でも役に立たないものの例えです。
もし豆腐で拍子木を作ったとします。
真っ白で見た目はいいかもしれませんが、それを音を鳴らすために叩き合ったら・・・、もちろんすぐ弾けるように壊れてしまいますよね。
そこから、役に立つはずもないものの例えとされるようになりました。
まとめ
ろくでなしは、役に立たない人を指して言う言葉で、侮辱や軽蔑の意味が強い言葉となっています。
ただ、それよりもさらに相手を咎める言葉として、ひとでなしなど似たような言葉もあります。
「ろく」とは大地を指す陸の事で、平らなことから真面目な人を評する際に使われていました。
その経緯から、まじめではない人の意味で「ろくでなし」という言葉は生まれたとされています。
類義語としては、「うどの大木」や「白豆腐の拍子木」などがあります。




