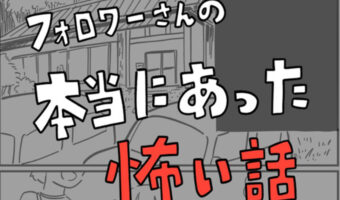そんな季節を分ける言葉の「雑節」。
これは、中国から伝わってきた暦では対応しきれない季節を把握するために、日本が独自で生み出した暦日です。
現在でもよく知られている節分や彼岸のようなものもあれば、あまり聞きなれない暦日もあります。
そこでここでは、「雑節」がどのような暦日を指すのかを解説します。
目次
中国から伝わった「二十四節気」

まずはじめに、日本の季節を分けるのに欠かせない、「二十四節気」について見ていきましょう。
「二十四節気」は、古代中国より伝わった季節の分け方です。
太陰太陽暦は季節とのズレが生じて不便
昔、日本では太陰太陽暦という暦の定め方を使用していました。
「太陰太陽暦」は太陽と月のめぐりを基準に暦を定めるものですが、厳密にいうと年ごとに季節と月日にずれがあり、年によってはひと月ぐらいズレてしまうのです。
そのため、「太陰太陽暦」は季節の移り変わりの目安になりにくくなってしまいます。
そこで、古代中国では季節を定める基準を設けました。
それが「二十四節気」です。
ズレを気にしないでいいように生まれたのが「二十四節気」
季節とのズレを気にしないために取り入れられた二十四節気。
これは、1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、それを更に6つに分けたもの。
1年を24に分けたので「二十四節気」というわけですね。
「二十四節気」で決められた季節の名前は、今でも「立春」や「春分」、「夏至」といったの季節をあらわす言葉として使われています。
日本で独自に生まれた「雑節」

そんな「二十四節気」を日本では使用するようになりましたが、日本にはそのほかにも季節を分ける言葉があります。
それが「雑節」です。
二十四節気の補足として生まれた「雑節」
二十四節気は、中国の気候に合わせて生まれた言葉です。
そのため、日本の気候に適したものではありません。
そんな二十四節気だけでは季節の変化を十分に読み取れなかったために設けられた補足のようなものが雑節です。
昔は農業に従事する人が多く、季節の変化は重要なものでした。
より正確に季節の変化を把握するために、日本独自で考えられたのが「雑節」なのです。
雑節はこの9つ
雑節には、以下の9つがあります。
節分
今では2月3日に行われる行事として知られている節分ですが、元来は春夏秋冬全てに節分があります。
立春・立夏・立秋・立冬の前日に設けられています。
特に立春前日の節分は、かつて大晦日的な意味合いもありました。
彼岸
彼岸は3月20日と9月23日頃。
「彼岸会」と呼ばれる仏教行事が行われ、先祖供養や、墓参りを行う慣習があります。
春の彼岸には「ぼたもち」を、秋の彼岸には「おはぎ」を食べる風習が全国にあります。
社日
3月21日と9月27日にある社日は、春分や秋分にもっとも近い戊(つちのえ)の日です。
その土地の神様・産土神に参拝する日です。
春には豊作を願い、秋には収穫を感謝する行事が執り行われます。
八十八夜
5月はじめにある八十八夜は、立春から88日目です。
歌に歌われている一番茶摘みの頃でもあります。
遅霜の被害が発生することもあるから、農業従事者に注意を促すために設けられたとされます。
入梅
6月11日の入梅は、暦の上での梅雨入りの日です。
現在は、二十四節気の「小暑」(7月7~8日)までに梅雨入りしていない場合、梅雨入り無しとされる事もあります。
半夏生
7月2日の半夏生は、梅雨の終わりごろの日です。
畑仕事や田植えをこの頃までに終わらせておくという目安の日になります。
天地に毒気が満ち、半夏という毒草が生えるとされていました。
また、この日に採れた野菜は食べてはいけないとする地域もあります。
土用
1月17日・4月17日・7月20日・10月20日頃にある土用。
いずれも、立夏・立秋・立冬・立春の前18日間となっています。
そのため、土用の最後の日はいずれも節分にもなります。
夏の土用には、ウナギを食す「土用の丑の日」が知られていますね。
二百十日
現在の暦で8月31日や9月1日に訪れる二百十日は、立春から210日目のことです。
台風の襲来する時期として恐れられていました。
二百二十日
9月10日の二百二十日は、立春から220日目の日です。二百十日同様、嵐の襲来する時期として恐れられていました。
「節句」との違い

日本の季節を言い表すものとして、「節句」があります。
この「節句」は、雑節ともまた別物になります。
「節句」とは
「節句」は、中国での風習を日本人のくらしに合わせて取り入れたものです。
陰陽五行説を由来とするともされますが、江戸時代には節句のうちいくつかが公的な行事として定められました。
それらが現代に伝わり、節句として馴染んでいます。
「節句」はこの5つ
主な節句は、以下の5つです。
七草の節句
1月7日の七草の節句は「人日」とも呼ばれる日です。
中国では正月から7日間をそれぞれの動物の運勢を占う日とされていました。
そして、7日が人間の占いを行う日なので「人日」ともいうのだとか。
日本では、正月の間にご馳走を食べたので、胃を休めると共にその年の健康を願って「七草粥」を食べる風習が古くからあります。
桃の節句
3月3日の桃の節句は「上巳」とも呼ばれます。
ひな祭りの日として親しまれています。
このひな祭りは、女の子が健康に育つことを願う行事となっています。
また、雛飾りはもともと厄除けの存在だったとされます。
菖蒲の節句
5月5日の菖蒲の節句は「端午の節句」とも呼ばれ、男の子の健康を祝う日として知られています。
季節の変わり目のため、健康を保つために薬効を持つ菖蒲湯に入浴し、菖蒲酒を飲む日ともされています。
この日はもともと、男の子の健康を祝う日ではありませんでした。
しかし、鎌倉時代になって武士勢力が台頭してくると、菖蒲が「尚武」とも読めることなどから、男の子の成長を祈る日になったのとされています。
七夕
7月7日の七夕は星祭とも呼ばれ、短冊を結んだ竹や笹が飾られる風景は夏の風物詩とされています。
もともとは手芸の上達を願う行事でしたが、現在では願い事全般に代わっています。
また、江戸時代にはそうめんを食べる風習もありました。
重陽の節句
重陽の節句は9月9日。
九という陽の数字(奇数)がふたつ重なることから、めでたい日とされました。
菊の花びらを浸した菊花酒や旬の栗を食べる風習がありました。
現在では、他の節句に比べるとあまりなじみのない風習になっています。
まとめ

「中国より渡って来た暦日の「二十四節気」。
しかし、これだけでは季節の変化を十分に読み取れなかったため、日本の気候に合わせて追加したのが「雑節」です。
農業従事者にとって、欠かせない存在でした。
「節句」もまた日本に併せて調整された風習となっています。
そのため、中国の節句とはまた異なる内容となっています。
関連記事はこちら
「縁の下の力持ち」、元は同じ意味の「縁の下の舞」だった?語源とされる行事も解説!