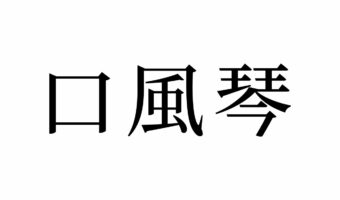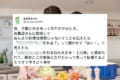余計なことを言うことを「雉も鳴かずば撃たれまい」と言います。
この言葉は、余計な発言などで災難に見舞われることを指します。
しかし、なぜ雉が関係しているのでしょうか?
そこで今回は「雉も鳴かずば撃たれまい」の意味をご紹介します。
この言葉の成り立ちには悲しい物語が言い伝えられていました。
目次
「雉も鳴かずば撃たれまい」とは

まずは「雉も鳴かずば撃たれまい」について見ていきましょう。
ここでは「雉も鳴かずば撃たれまい」の表現と意味をまとめます。
「雉も鳴かずば撃たれまい」という表現
「雉も鳴かずば撃たれまい」は、後悔の念が詰まった言葉です。
猟師は獲物を探して常に狙っています。
そのため、鳴かずにやり過ごせば見つからないかもしれません。
しかし、鳴いてしまったがために、命を狙われてしまうわけです。
特にこの言葉は「余計なことをしなければ」というニュアンスの強い表現です。
「雉も鳴かずば撃たれまい」の意味
「雉も鳴かずば撃たれまい」は、無用なことを言ったばかりに災難に巻き込まれてしまうことの例えです。
言わなくてもいいことを口走って墓穴を掘る人などに使用されます。
特に「鳴く」という表現がこの言葉の核となっています。
そのため、行動よりも発言に対して使われることが多いです。
しかし、余計なことをして被害が大きくなることをあらわす際にも用いられます。
由来とされる2つの悲しい物語

「雉も鳴かずば撃たれまい」の由来にはある2つの物語があります。
ここでは「雉も鳴かずば撃たれまい」の語源についてまとめます。
大阪・淀川に伝わる物語
その昔、淀川に長柄橋と呼ばれる橋を建てる計画がありました。
しかし、工事の着手すると川が度々氾濫を起こしてしまっていました。
この川の氾濫により作業が難航し続けました。
そんな中、橋奉行らが雉の鳴き声を聞きながら話し合っていたところ、ある夫婦が通りかかり以下のように呟いたそうです。
「袴の綻びを白布でつづった人をこの橋の人柱(一種のいけにえ)にしたらうまくいくだろう」
これを聞いた橋奉行らがその夫婦を見ると、その夫自身がまさにその通りの格好をしていることに気付き、すぐに捕らえて人柱にしてしまいました。
その後、伴侶を失った妻も淀川で自殺してしまったのだとか。
「ものいへば 長柄の橋の 橋柱 鳴かずば雉の とられざらまし」
この和歌は、伴侶を失った妻が最後に残したものとされます。
口が滑ったばかりに人柱にされた夫のことを嘆いた歌となっています。
この歌の「鳴かずば雉の」の箇所から「雉も鳴かずば撃たれまい」という言葉が生まれたとされます。
長野・犀川にまつわる物語
長野県を流れる犀川にも「雉も鳴かずば撃たれまい」の由来となったとされる物語が伝わっています。
この犀川、昔から秋になると氾濫する暴れ川とされ、地域住民を困らせていました。
そんな屑川の付近に、昔むかし父親と暮らすお千代という娘がいました。
ある日、お千代は病にかかってしまいましたが、困窮したお千代の家族は医者を呼ぶことなど到底かないません。
熱に苦しむお千代は、以前に一度だけ食べたことがあるご馳走「赤飯」が食べたいとごねました。
それを聞いたお千代の父親は、小豆と米を地主の蔵から盗み取ってきて、お千代に赤飯を食べさせてあげました。
看病の甲斐もあって、お千代はすっかり元気になりました。
その後のお千代は、手毬歌として赤飯を食べたことを口ずさむようになりました。
そんな矢先、ふたたび屑川が氾濫し、村では人柱を立てる話が持ち上がります。
村人の中から人柱を選ぶという事、そして罪のない人間を人柱にするわけにもいかないので、罪人から選ぼうとなったのですが、村人に罪人などいませんでした。
そのため誰を人柱にするか難航する中、ある人がお千代が赤飯を食べたという手毬歌を口ずさんでいるという話をしました。
お千代に家に、赤飯を作る余裕が無いというのは村の人ならだれでも知っています。
そこで、お千代の父を詰問すると、風邪を引いたお千代のために地主の蔵に忍び入ったことを白状しました。
こうして、お千代の父親が罪人として人柱に選ばれてしまったのです。
お千代は、自分のせいで父親が人柱になったことを心から悔やみ悲しみました。
自分が病気になったせいで、うれしかったからとはいえ手毬唄で赤飯の事をうかつに手毬唄にしたせいで・・・と幾日も泣き悔やみ続け、その後は一切口をきかなくなってしまいました。
それから幾年物時が経ちました。
お千代も年頃に成長しましたが、そうなっても口をきくことはありませんでした。
そんなある日の事、猟師が山へ狩りに向かいました。
雉の鳴き声を聞いた猟師は、声を頼りに鉄砲を発射。
見事に撃ち落としました。
喜び勇んで、撃ち落としたところに向かうと、、そこには撃たれたキジを抱いてたたずむお千代の姿が・・・。
驚く猟師を見て、お千代はこう言ったそうです。
「お前も鳴かなければ撃たれなかったろうに」
鳴き声をあげたことで撃ち落とされた雉を、赤飯の事を手毬唄にして歌った自分と重ね合わせたのでしょう。
幾年ぶりかに口を開いたこの言葉を残して、お千代は村から姿を消してしまいました。
「雉も鳴かずば撃たれまい」の類義語
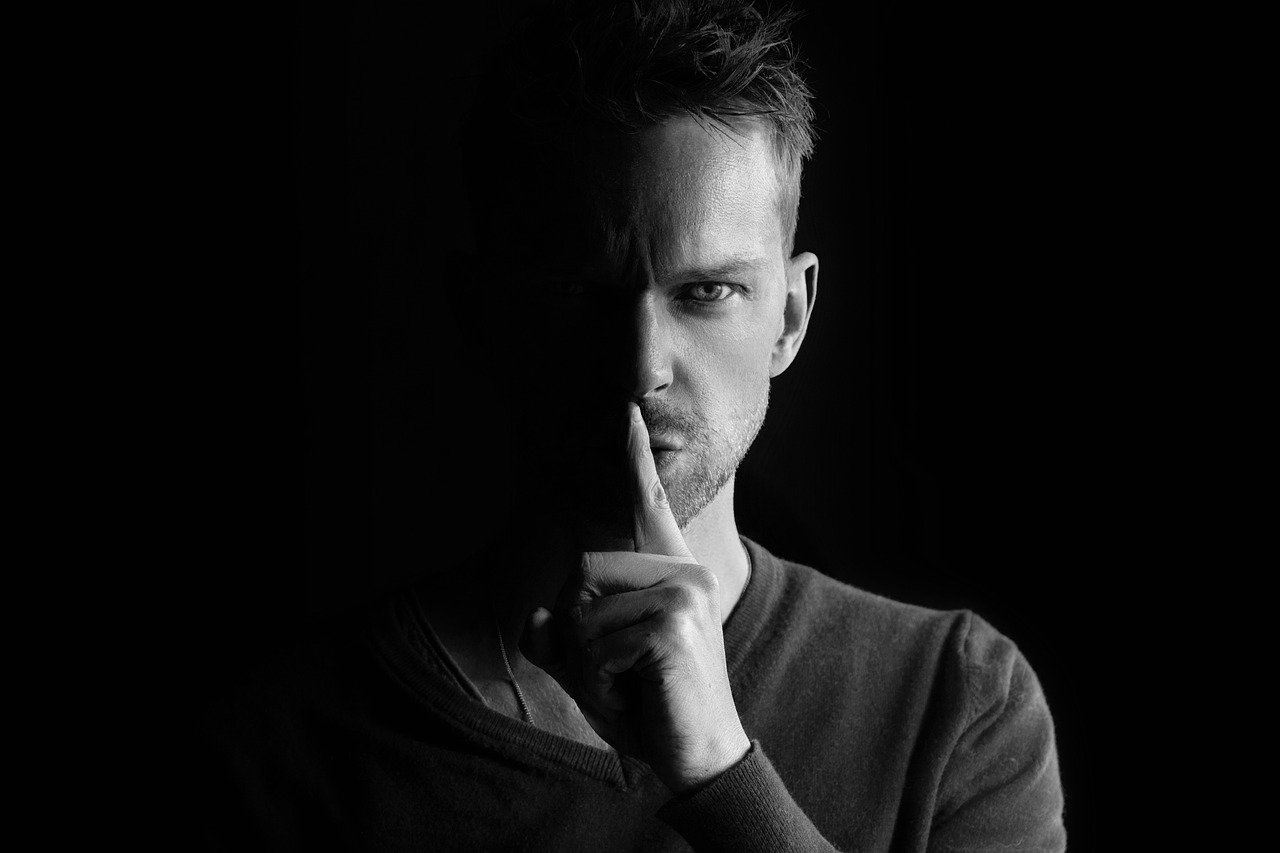
ここからは「雉も鳴かずば撃たれまい」の類義語を見ていきましょう。
口は禍の元
「口は禍の元」は、不用意な発言は身を滅ぼすことになるという例えです。
迂闊に言葉を発するべきではないという戒めでもあります。
物言えば唇寒し秋の風
「物言えば唇寒し秋の風」は、悪口を言えば後味の悪い思いをするという例えです。
また、余計なことを口走ると災いを招くという例えにもされます。
まとめ
「雉も鳴かずば撃たれまい」は余計なことを口走ったがために、最悪の結果を招いてしまうことをあらわす言葉です。
この言葉は、人柱にされたとされる悲しい物語が2つ由来として伝わっています。
「口は禍の元」や「物言えば唇寒し秋の風」といった言葉も同じような意味合いで用いられます。