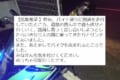先行きが見通せず、手探りでなにかをしなければいけないことの表現のひとつ「五里霧中」。
この「五里」の「里」は昔の距離の単位ですが、「五里」って実際どれぐらいの長さなのでしょうか?
ここでは、五里霧中という言葉の意味はもちろん、その成り立ちについて見ていきましょう。
目次
「五里霧中」とは

まず最初に、「五里霧中」の意味について見ていきましょう。
「五里霧中」の意味
「五里霧中」は、物事の先行きが見えず、方針や見込みが立たずに困ることを例えた言葉です。
霧の中にいるかのように、手探りで何かをすることを表す慣用句です。
「五里夢中」ではないので注意!
「五里夢中」と書いてしまったり変換してしまいこむこともあるかもしれませんが、これは間違いなので要注意。
「夢中」と言うと、なにかに熱心になり心が囚われている様子となります。
周りが見えていないという意味では一緒かもしれませんが、「五里夢中」は見たくても先が見えない様子となっていますのでまるっきり違う言葉なのです。
「五里霧中」の由来

「五里霧中」という言葉は、中国のある人物の得意技に由来するとされています。
中国の故事に由来する「五里霧中」
「五里霧中」の由来は、中国の故事にあります。
中国後漢の時代の出来事をまとめた史書「後漢書」に登場する「張楷(ちょうかい)」という人物は、呪術やまじないともされる道術をよく使い、五里四方にわたって霧を起こすことで自らの行方をくらますことができたきたとされます。
この張楷の術がもとになり、五里にもわたって霧が発生したら周りが見えなくて困ってしまうということで「五里霧中」という言葉が生まれたのです。
由来となった「張楷」という人物
「張楷」は、後漢の時代の儒学者です。
儒学者というのは、孔子を始祖とする「儒学」を学んだり研究する学者です。
張楷は、非常に優秀な人物だったらしく、その門弟は常に100人以上いたとされます。
しかも、その弟子たちから相当慕われていたようで、張楷が隠居を決めて山の中に籠ると、弟子たちも揃ってその山周辺の町に引っ越ししてきてしまうほどだったのだとか。
また、権力には興味なかったとされます。
高官として度々招かれてもそれに応じることが無く、一度は地方の長官にあたる「県令」に任じられたのに、赴任することさえしなかったとされます。
「五里」とは

今となっては使われることがあまりない「里」という単位ですが、一体具体的にはどれほどの長さを表すのでしょうか?
時代や国によって変わる「里」の長さ
「里」の長さは、実は時代や国によって変わっています。
中国における「里」の長さ
里は、元々は古代中国で使われていた面積の単位でした。
三百歩四方の面積を表す単位だったのですが、のちにこの一辺の長さが距離の単位になりました。
当時、漢の時代の1歩は1.38m余りだったと推定されるので、一里の長さは415m程度となります。
ちなみに、ここでいう1歩は現代の私たちと認識が異なります。
歩というのが長さの単位なのですが、これは左右どちらかの足を踏み出し、更に反対の足も踏み出した際の距離、つまり現在でいう2歩分の長さです。
現代の日本における認識でいう2歩分を長さの単位としたのが「歩」になります。
この単位は、時代によって変化します。
唐の時代の一里は、540m程度ともいわれれば560m前後などともいわれます。
差があるのは、古代中国における一里の長さは実はまだ明確になっていないからだとされます。
現在の中国では、明確に定められており、一里は500mとなっています。
日本における「里」の長さ
日本にも飛鳥時代に「里」の距離単位は唐から伝わり、使用されてきました。
導入された当初は、一里が三百と中国と同じ考え方でした。
しかし、そもそも歩の長さが異なったため唐とは距離が異なり、533m前後だったと考えられています。
その後は、時代や地域によって「里」の長さはまちまちになります。
再び一定の長さになったのは戦国時代の終わり、豊臣秀吉の時代です。
天下統一を成し遂げた豊臣秀吉は、あらゆる規格を全国共通にしようと動きます。
「里」もまた、その一環です。
この時、「一里」を三十六町とし、街道ごとに一里塚が設けられました。
「一町」が約109mなので、一里は3,927mとなります。
これは明治時代以降も基準となっています。
中国で発祥した「一里」と日本の「一里」では、大きく異なるという事になりますね。
当時の「五里」の距離は・・・
前述のとおり、後漢書が記された漢の時代の一里は415mほどです。
つまり、五里は約2,075mという事になります。
たしかに、周囲2kmに渡って霧がかかったらとうていその場を見通すことはできそうもないですね・・・・。
まとめ
「五里霧中」は、先が見通せないため、方針も立てられない様子をあらわす言葉です。
これは、古代中国の「張楷」という儒学者が霧を周囲に起こして身を潜めることを得意としていたことから来た言葉とされています。
その霧の範囲は周囲2kmにも渡るということなので、たしかにその状況は先が到底見通せそうもありません。
ちなみに、この故事の五里と日本の江戸時代の五里では相当距離感が異なります。
日本だと5里は19,635m、約20kmということになります。