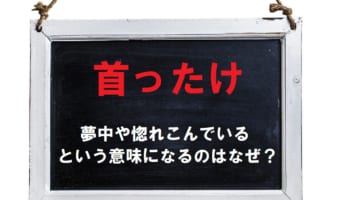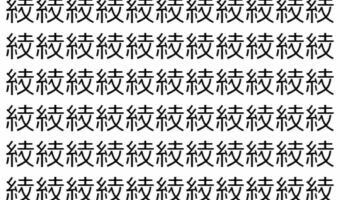「管鮑の交わり」という言葉をご存知ですか?
この言葉は、「友人としての親密な交わり」ことをあらわす言葉で、中国の故事が由来となってできた言葉です。
同じような使い方をする言葉で「水魚の交わり」というものもありますが、こちらとは由来は異なり、実は使い方も若干違いがあります。
そこでここでは、「管鮑の交わり」の意味や使い方、由来などについて解説します!
目次
「管鮑の交わり」とは

まずはじめに、「管鮑の交わり」の意味んいついて見ていきましょう。
「管鮑の交わり」の意味
「管鮑の交わり」は、友人としての親密な交流をあらわす言葉です。
非常に仲のよい親友や、お互いを助け合うような友人関係に対して用います。
時に、男女の清い交際という意味合いでも用いられます。
「水魚の交わり」との違い
「管鮑の交わり」に似た言葉として、「水魚の交わり」という言葉があります。
水と魚のように切っても切れない親しい関係という意味合いで用いられます。
「管鮑の交わり」が友人同士の関係に使うのに対して、「水魚の交わり」は主従や上司と部下の関係性や、非常によい夫婦関係についても用いることが多いです。
「管鮑の交わり」の由来

「管鮑の交わり」という言葉の由来は、「史記」に登場する「管仲(かんちゅう)」と「鮑叔牙(ほうしゅくが)」という人物についての逸話から来ています。
「管」と「鮑」は人名から
「管鮑の交わり」の「管鮑」は、「管仲」の「管」と「鮑叔牙」の「鮑」からきています。
逸話の舞台は春秋時代の中国。
管仲と鮑叔牙は若いころから親睦を深めてきました。
一時は一緒に商売をし、鮑叔牙が失敗をすることもありました。
それにたいして管仲が鮑叔牙を攻めることはありませんでした。
逆に儲けが出れば、鮑叔牙は貧しい管仲に利益の多くが行くようにしていたのだとか。
相手を糾弾し合うことも無く、融通し合う関係を2人は築いていたのです。
「管鮑の交わり」の故事
若かりし頃から共に商売をするほどだった2人でしたが、時が経ち主を違えます。
同じ「斉(せい)」の国に仕えたのですが、主となる人物が違ったのです。
そして時が経ち、鮑叔牙の主は後継者争いによって国外へ逃亡、鮑叔牙もまた国外に旅立ちました。
対して管仲の主は、後継者争いの結果国王となりました。
しかし、管仲の主である斉王は暗殺されていまいます。
そこで再び、「斉」で後継者争いが勃発したのです。
この後継者争いには、鮑叔牙の主も参加。
鮑叔牙の活躍もあって国王となりました。
この時、管仲は鮑叔牙の主とは違う人物を後継者として推していました。
つまり、後継者争いの敗者となり、管仲の主は殺され、管仲自身も捕らえられてしまいました。
その時、鮑叔牙は管仲の才能を惜しみました。
管仲を積極的に新しく国王になった主に推薦します。
そしてなんと、管仲を宰相つまり配下の中で最高職に就け、自身はその配下となるように手筈を整えたのです。
いかに鮑叔牙が管仲を信頼し、その才能を買っていたかが分かります。
この鮑叔牙に対し、管仲は「私を生んだのは両親だが、自分を真に理解してくれているのは父母ではなく鮑叔牙だ」と深い感謝と恩義を抱いていました。
2人のこの逸話がもとになり、「管鮑の交わり」という言葉が生まれたのです。
「管鮑の交わり」の類義語
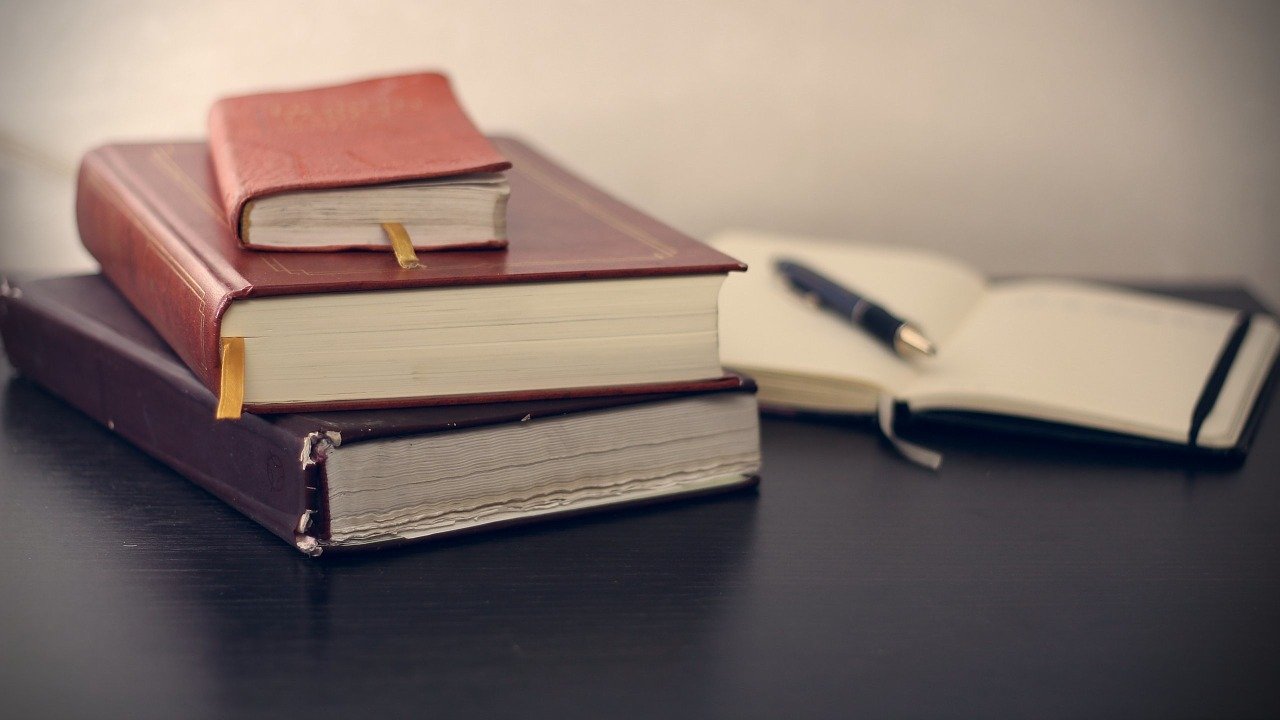
友情話が由来となった「管鮑の交わり」。
似たような意味合いで用いる言葉は他にもありますのでご紹介します。
刎頸の交わり
「刎頸の交わり(ふんけいのまじわり)」は、非常に親密な間柄を意味する言葉です。
「刎頸」とは首を斬ることを意味する言葉で、お互いに首を斬られても後悔しないような仲というような意味合いになります。
少し物騒な言葉にも思いますが、こちらは中国の戦国時代に「趙(ちょう)」で活躍した、「藺相如(りんしょうじょ)」と「廉頗(れんぱ)」という人物が残した故事が由来となっています。
元は藺相如を口だけの人物と思っていた廉頗、ある時に藺相如が国を思う思慮深い人物という事を知ったことでこれまでの自分の言動を恥じました。
そして、「あなたになら首をはねられるようなことになっても悔いはない」と藺相如に言えば、藺相如もまた「私もあなたになら私の首を差し出すことができる」と返しました。
こうして藺相如と廉頗は深い絆で結ばれたことから「刎頸の交わり」という言葉は生まれました。
竹馬の友
「竹馬の友」という言葉は、小さい頃から遊んでいた幼馴染みやよきライバル、切磋琢磨する関係の相手という意味の言葉です。
こちらも中国の故事に由来する言葉です。
「竹馬」は乗って遊ぶ「タケウマ」のことではありません。日本では「春駒」と呼ばれた、竹の棒の先の部分に馬のたてがみをつけたもの、もしくは頭部をあしらったおもちゃを意味します。
「殷浩(いんこう)」と「桓温(かんおん)」という人物は、共に東晋に仕えた人物で、幼いころから交流がありました。
そして、後に2人とも東晋にとってなくてはならない存在にまで上り詰めたのです。
この桓温が「殷浩とは子供の頃に竹馬で遊んでいたが、いつも自分が乗り捨てた竹馬に後から乗って遊んでいたな」と懐述したことが「竹馬の友」の由来とされています。
「竹馬の友」の由来となった2人はあまり仲が良くなく、どちらかといえば競争相手としてのライバルだったようです。
まとめ

「管鮑の交わり」は「友人としての親密な交わり」ことをあらわす言葉です。
中国の故事が由来となっており、「管仲」と「鮑叔牙」というふたりの人物を巡る、アツいエピソードから来ています。
類義語には、同じく中国の故事を由来とする「刎頸の交わり」や「竹馬の友」があげられます。