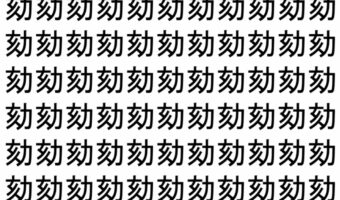ものごとを簡単にできることを「おちゃのこさいさい」と表現することがあります。
おどけたり、容易なことを強調する際に使われることが多いです。
では、この言葉の「おちゃのこ」と「さいさい」とはそれぞれ何をあらわしているのでしょうか。
ここでは、この「おちゃのこさいさい」という言葉について見ていきましょう。
目次
「おちゃのこさいさい」とは

まずは「おちゃのこさいさい」という言葉の意味やその用い方を見ていきましょう。
「おちゃのこさいさい」の意味
「おちゃのこさいさい」は、物事が簡単にできることを言います。
とても容易いことをあらわす表現となっています。
何かを行う事や完成させることが造作もないことを強調する表現です。
そんなの簡単さ!とアピール際に用いる
「おちゃのこさいさい」は簡単なことのアピールに使います。
例えば、ある仕事を任されたときに「こんなのおちゃのこさいさいだよ」という具合に使用します。
自分に任せてくれれば難しいことなど何もない!というアピールにもなります。
自分のスキルやテクニックが高い場合は「自分であればできる」というアピールとしても用いられます。
「おちゃのこさいさい」の由来

ここからは「おちゃのこさいさい」の「おちゃのこ」と「さいさい」にそれぞれどのような由来があるかを見ていきましょう。
「おちゃのこ」の由来とされる3つの説
まずは「おちゃのこ」の由来について見ていきましょう。
ここでは、語源とされる3つの説を説明します。
茶菓子を食べた後の感覚から来たとする説
「おちゃのこ」とは茶菓子のこととする説があります。
茶菓子は、腹に溜まらず容易に食べられることができます。
それが転じて、簡単にできるという意味で使われるようになったのだとか。
茶道から来たとする説
「おちゃのこ」は、茶道から来たという説もあります。
茶道には、難しいお茶の作法がいくつもあります。
それらを習得するのは簡単なことではありません。
しかし、それに比べると茶菓子を食べる作法は難しくありません。
それが転じて容易という意味で「おちゃのこ」が使われるようになったともされています。
朝食からきたとする説
「おちゃのこ」は一節によると、朝食に食べる茶粥のことを指すという説があります。
茶粥は間食の一種ともされ、ゆるめに作ればお腹が満たされることはありません。
そのため、寝起きであっても簡単に食べることができます。
そこから簡単や容易の意味で「おちゃのこ」が用いるようになったというのです。
「さいさい」の由来
「さいさい」は、俗謡の囃子詞をもじったものとされています。
いわゆる「よいよい」や「おいおい」という囃子詞のことです、
これが「おちゃのこ」の後ろに付くことで、より軽快に物事をこなす表現として役目を果たしているのだとか。
「おちゃのこさいさい」は英語でもお菓子が関係している

英語にも「おちゃのこさいさい」に似た表現があります。
なんの偶然か、この言葉もまたお菓子が関係しているのです。
「おちゃのこさいさい」を英訳すると・・・
「おちゃのこさいさい」を英語表現にすると"It's a piece of cake."となります。
これは、物事がとても簡単なことであることを意味します。
直訳すると「1ピースのケーキ」となりますが、これはケーキを1ピースならササッと口にできる上に1ピース食べただけでは腹が満たされないことから来ているとされます。
まとめ
「おちゃのこさいさい」は、とても簡単になせるということをあらわす表現です。
「おちゃのこ」は茶菓子のことから来ているともされ、「さいさい」は囃子詞が転じたものとされます。
英語では、"It's a piece of cake."と表現できますが、奇しくもどちらもお菓子に関りがある表現となっています。