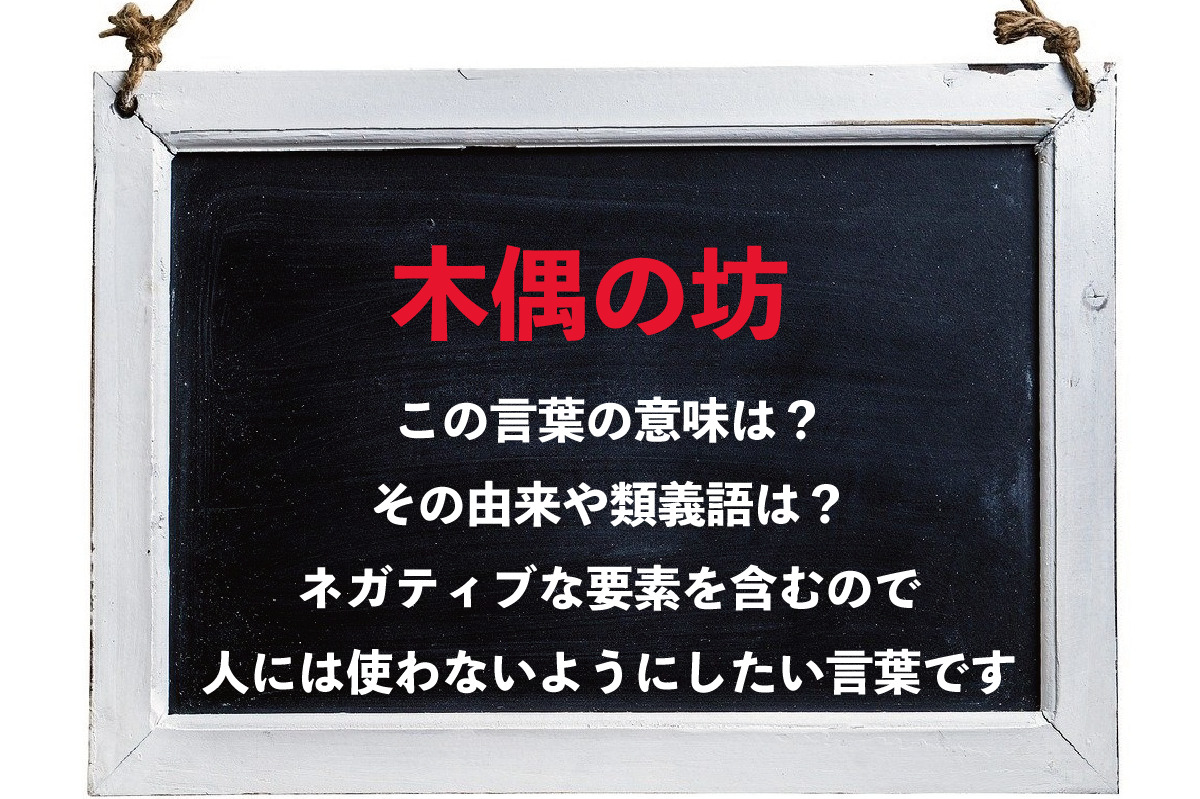
役に立たない人や物を、俗に「木偶の坊」と表現します。
「木偶」という言葉自体、役に立たないことを指す表現とされています。
では、なぜ「木偶の坊」という表現がされるのか、その由来や類義語について見ていきましょう。
目次
「木偶の坊」とは

まずは「木偶の坊」がどのような言葉なのか見ていきましょう。
「木偶の坊」の意味
「木偶の坊」は、役に立たない人や気が利かない人を指す言葉です。
単に役に立たないことだけではなく、気が利かないことをあらわすこともあります。
また、人の言いなりになっている人についても使用されます。
操り人形の如く、誰の言うことにも従ってしまう人を指すのです。
「木偶の坊」は人を罵倒する際に用いられる
「木偶の坊」は、相手を罵る言葉のひとつとなります。
そのため、相手を罵倒する際の悪口として使うことが多いです。
口汚い言葉の表現の一つとなることから、あまり口にすべき言葉ではないでしょう。
また、相手に言われるのも避けたい言葉です。
「木偶の坊」の由来

「木偶の坊」という言葉は、どのようにして生じた表現なのでしょうか。
この成り立ちについて、ここでは見ていきましょう。
「木偶」は人形の事
「木偶の坊」の「木偶」とは、木彫りの操り人形のことです。
この木彫りの人形と無能な人間を重ねたことで生まれた表現と考えられています。
「坊」はどこから来た?
「木偶の坊」の「坊」とは、親しみを込めた接尾語となります。
単に「木偶」と呼ぶと、悪口の度合いが強いです。
そのため、軽い嘲りを込めて「坊」をつけたとされます。
また、手傀儡が訛った「坊(でくる)」から来たという説や「出狂坊(でくるぼう)」から来たという説などもあります。
使いたくないし、使われたくもない。類義語は人を悪く言う際に使われる言葉

「木偶の坊」は人に言うのも言われるのも避けたい言葉です。
そのため、類義語もまた、同じ傾向にあります。
うどの大木
「うどの大木」は、大きい体をしていながらも役に立たない人の例えです。
その由来は、ウドの植物としての特性が関係しています。
植物のウドの茎は、木のように長く成長します。
しかし、ウドの茎は木材としては使うには柔らかすぎます。
そこから、体ばかり大きくて役に立たない人の例えとして「うどの大木」が使用されるようになったとされています。
あんぽんたん
「あんぽんたん」とは、間が抜けている人のことです。
間抜けを指す「あほ」や愚か者を指す「だらすけ」が複合された「あほだら」「あほんだら」が転じた言葉ともされています。
ひょうろくだま
「ひょうろくだま」とは、のろまで間の抜けた人のことです。
ふらふらしていてどこに行くかわからない人に対しても使用されます。
まとめ
「木偶の坊」は、役に立たない人や物、そして気が利かない人の例えです。
これは、操り人形から来たことばということもあって、人の言いなりになってしまう人についての表現となっています。
人に向けて発してはいけない、ネガティブな要素が含まれた言葉となっています。




