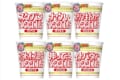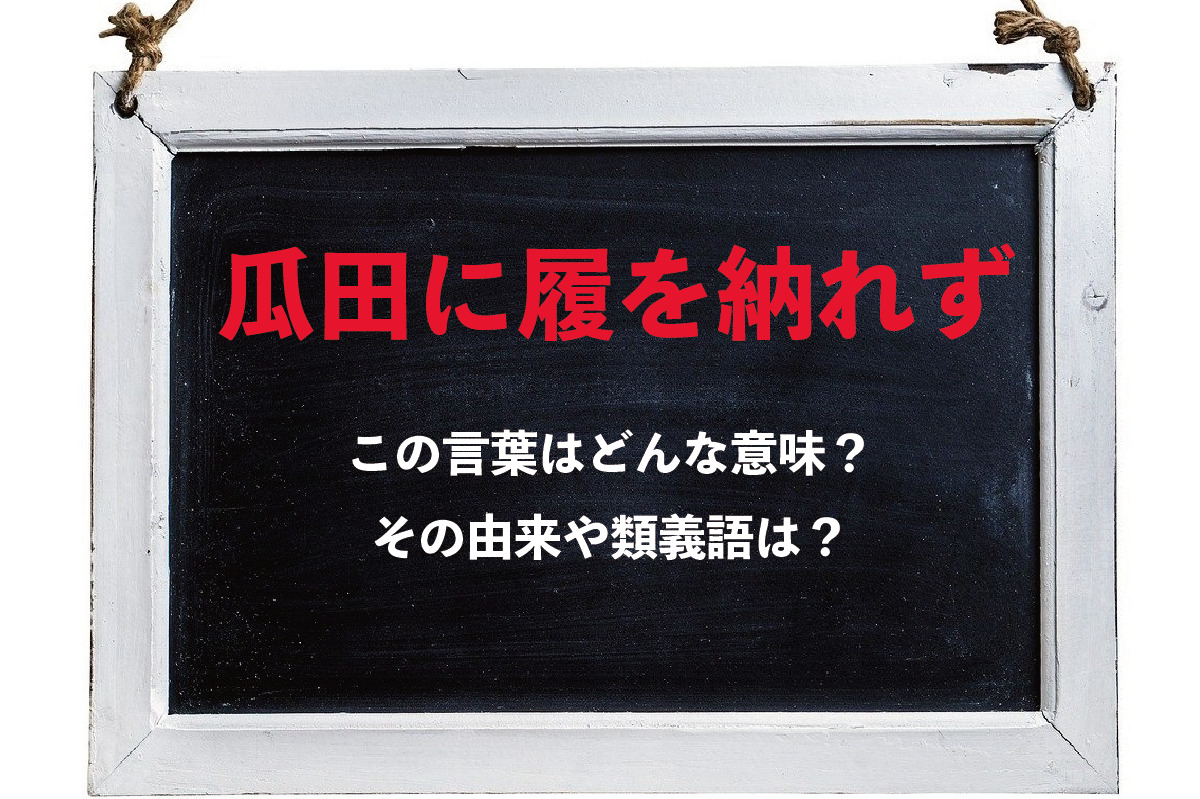
人に疑われるようなことをしてはならないという例えとして使用される言葉のひとつ「瓜田に履を納れず」。
この言葉は、実は続く言葉があります。
ここでは、この「瓜田に履を納れず」という言葉について、その意味や由来について見ていきましょう。
目次
「瓜田に履を納れず」とは

まずは「瓜田に履を納れず」という言葉について見ていきましょう。
「瓜田に履を納れず」の意味
「瓜田に履を納れず」は、人に疑われる行動を取ってはならないという意味の言葉です。
必要があって人の瓜畑に入っていったとして、もし靴が脱げてしまったからと身を屈めたら瓜を盗ろうとしていると畑の持ち主に思われてしまうことでしょう。
つまり、泥棒と間違われてしまうということです。
そのため、安易に疑われるような行為をしてはいけないという意味となるのです。
ちなみに「履を納れず」は靴に足を入れるということをあらわしています。
「君子危うきに近寄らず」とは意味が異なる
「瓜田に履を納れず」と似た言葉に「君子危うきに近寄らず」という言葉があります。
しかし、このふたつはニュアンスこそ似ていても意味は異なります。
「瓜田に履を納れず」が疑われるようなことをしないという意味なのに対して、「君子危うきに近寄らず」は危険なことはしない、行動に気を付けるという意味です。
「瓜田に履を納れず」の由来

「瓜田に履を納れず」は、どのようにして生まれた言葉なのでしょうか?
その由来について見ていきましょう。
由来は『古楽府‐君子行』から
「瓜田に履を納れず」は、古代中国の詩を集めた「古楽府」にある君子行を出典とする言葉です。
そこには「君子防未然 不處嫌疑間 瓜田不納履」とあります。
これは、「君子たるもの、疑われるようなことは未然を防ぎ、県議を向けられるようなところに身を置いてはいけない」ということを説いています。
その続きとして「瓜田不納履」という「瓜田に履を納れず」の原型となる漢文があります。
ここで書かれていることも「瓜畑でしゃがみ込み、靴を履く仕草を見せてはいけない」となっています。
「君子防未然」から続くこの詩は長く続くのですが、その一部だけがピックアップされことわざとして現在も残っているのです。
「李下に冠を正さず」と続く
「瓜田に履を納れず」の原型となる詩では、「瓜田不納履」の後に「李下不正冠」と続きます。
そしてこの一文は「李下に冠を正さず」ということわざとしても使用されます。
「李下に冠を正さず」は「瓜田に履を納れず」の類義語
「李下に冠を正さず」は、「瓜田に履を納れず」の類義語となります。
「李下に冠を正さず」は、李(すもも)の木の下で冠をきちんと直そうと手を伸ばしたら、その手は李を取るものと疑われてしまうという様子を描写しています。
この言葉も疑われるような行為をしてはいけないという意味で用いられます。
まとめ
「瓜田に履を納れず」は、古代中国の詩から生まれたことわざです。
疑わしいことはすべきではないという意味があります。
類義語として「李下に冠を正さず」がありますが、この言葉も同じ詩から来た言葉です。