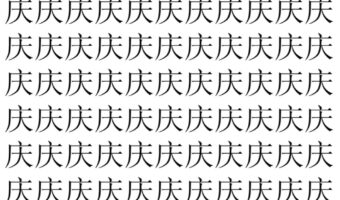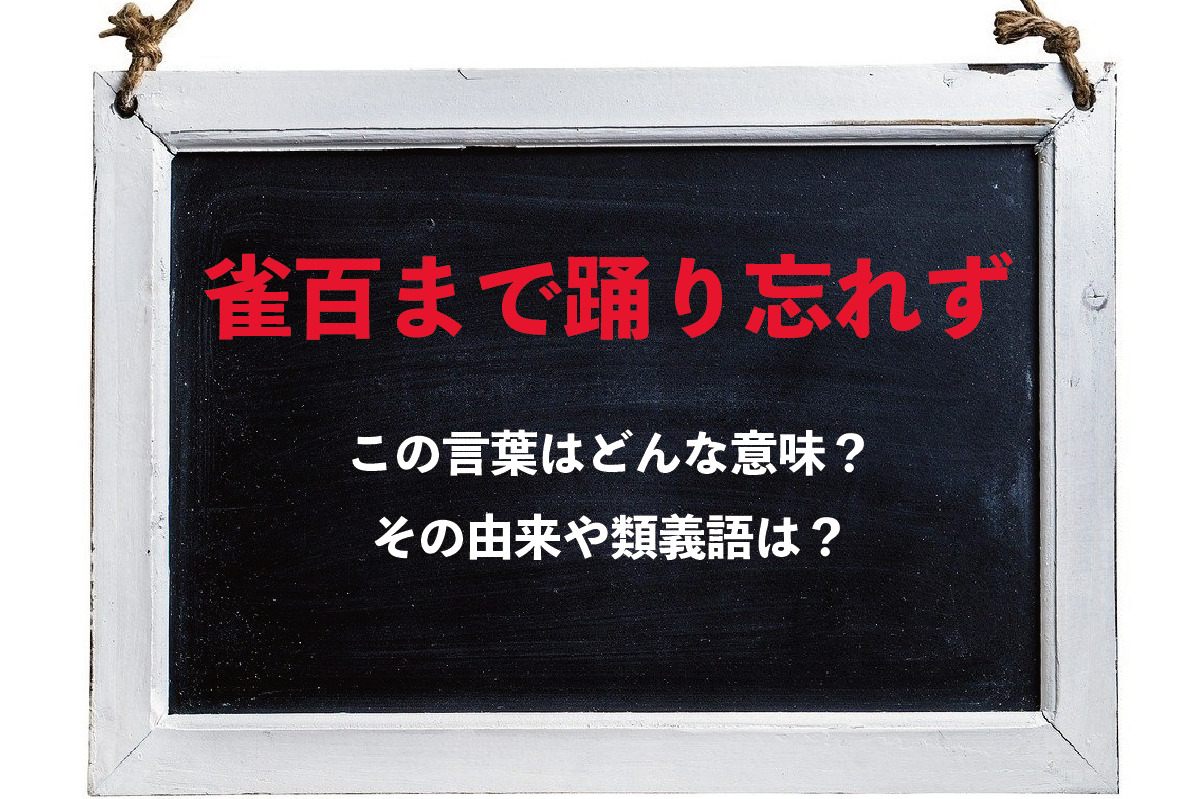
若い頃に身についてしまった習性は、年を重ねても容易には変えられません。
そんな習性に対しては、「雀百まで踊り忘れず」と表現されることがあります。
この言葉の意味や用い方、そして由来についてここでは見ていきましょう。
目次
「雀百まで踊り忘れず」とは

まずは「雀百まで踊り忘れず」の意味や用い方について見ていきましょう。
「雀百まで踊り忘れず」の意味
「雀百まで踊り忘れず」とは、若い頃に身についた習性は年をとっても変わらないということを例えた言葉です。
若い頃から遊び回っていた人は、年をとってからも遊び回る人が多いです。
幼い頃から掃除が苦手な人は、よほどのことがないと成長したらこまめに掃除をするようにはなりません。
このように、若い頃に身についた習性が年齢を重ねても抜けないようなことを「雀百まで踊り忘れず」と表現するわけです。
ポジティブな表現としては用いられない
そして、この「雀百まで踊り忘れず」は主にネガティブな表現となります。
ポジティブな表現として使用されないので、小さい頃から早寝早起きが得意な大人に対して、「子供の頃から、睡眠時間をしっかり取っているだなんて雀百まで踊り忘れずだね」なんて言い回しはされません。
「雀百まで踊り忘れず」は、昔から道楽者や浮気者に対する表現として使用されてきました。
そのため、当初からネガティブな意味を持つ言葉だったと言えるのです。
また、、「雀百まで踊り忘れず」が対象としているのは、本人が有している習性です。
若い頃に身につけた知識や技術は年をとっても衰えない、というようなニュアンスでは用いられません。
「雀百まで踊り忘れず」の由来

ここでは、「雀百まで踊り忘れず」の成り立ちについて見ていきましょう。
成り立ちは「雀」の動きから
「雀百まで踊り忘れず」は、雀の動きから来ています。
雀は、小さいときからぴょんぴょんと飛び跳ねるようにして地上を移動します。
これは、成鳥になっても変わりません。
「雀百まで踊り忘れず」では、この雀の動きを「踊り」と例えています。
ちなみに、今では「雀百まで踊り忘れず」で定着していますが、もともとは「踊り忘れぬ」という表現の方が一般的だったそうです。
しかし、江戸時代に京都を中心に普及した『上方いろはかるた』では「踊り忘れず」という表現が採用されました。
それによって「雀百まで踊り忘れず」という形が定着したとされています。
「雀百まで踊り忘れず」の類義語

習性や癖が直らないことを例えた言葉は他にもいくつかあります。
ここでは、「雀百まで踊り忘れず」の類義語となる言葉について見ていきましょう。
三つ子の魂百まで
「三つ子の魂百まで」とは、幼少期に身についた性質はいくつになっても変わらないことの例えです。
この言葉は、悪癖が直らないことに対して使用されることが多い表現となっています。
ここでいう「三つ子」とは、双子・三つ子の三つ子といった同時に生まれた3人の子の意味ではありません。
三歳児のことを指しています。
つまり、三歳までに身に付いた癖は成長しても残っているということを言っているのです。
噛む馬はしまいまで噛む
「嚙む馬はしまいまで嚙む」とは、悪癖はなかなか直らないことの例えです。
子馬の頃から噛み癖のある馬は、成長し亡くなる時まで噛み癖は残ることが多いです。
そこから、悪癖は容易に直せないという例えで用いられるようになりました。
漆剥げても生地は剥げぬ
「漆剥げても生地は剝げぬ」とは、本人が持って生まれた素質や性格は変わらないことの例えです。
器の外側に塗った漆は剥げることもありますが、内側の生地は剥げることはそうそうありません。
転じて、物事の本質が変わらないことを言う表現として使用されるようになりました。
まとめ
「雀百まで踊り忘れず」は、幼い頃に身につけた習性は大人になってから直るものではないことを例えた言葉です。
その対象となるのは、悪癖などネガティブな要素です。
ポジティブな癖について用いられる言葉ではありません。
この言葉は、ヒナのときから成長しても地面をぴょんぴょんと跳ねるように移動するスズメの姿から来たとされています。
関連記事はこちら
「悪事千里を走る」とはどういう意味?その由来はどこにあるの?