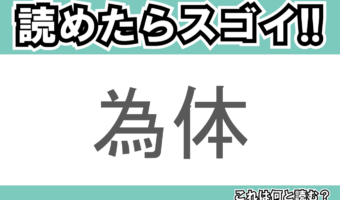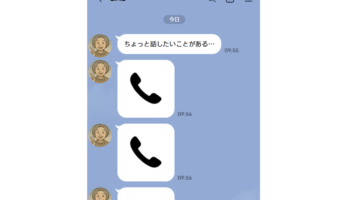毎年9月29日は「洋菓子の日」です。
しかし、洋菓子と9月29日・・・いったいどんな関係があるというのでしょうか?
そこでここでは、「洋菓子の日」という記念日について見ていきましょう。
目次
9月29日は「洋菓子の日」

まずは「洋菓子の日」がどのような日なのかを見てみましょう。
誰が制定した記念日?
「洋菓子の日」は、三重県洋菓子協会が2002年に制定した記念日です。
三重県洋菓子協会は、三重県伊勢市に事務局を置く日本洋菓子協会連合会に加入している団体です。
なぜ9月29日なの?
9月29日が「洋菓子の日」と制定されたのには、大天使ミカエルが関係しています。
洋菓子大国であるフランスでは、ミカエルを「菓子職人の守護聖人」として崇めています。
そのミカエルの祝日である9月29日が「洋菓子の日」として選ばれました。
ちなみに、日本でも洋菓子屋に並んでいることもある「サン・ミシェル」という名のケーキは、フランス生まれの洋菓子でその名前もミカエルにあやかったものとなっています。
何を目的とした記念日?
「洋菓子の日」は業界の発展と交流、若手の育成などを目的として制定された記念日です。
三重県の洋菓子協会が始めた記念日ですが、今では各地でイベントが催されてもいます。
「和菓子の日」は6月16日
ちなみに、「和菓子の日」は毎年6月16日となっています。
これは、全国和菓子協会が1979年に制定した記念日です。
平安時代の中期、日本国内では疫病が蔓延していました。
それを受けて、848年に仁明天皇は年号を「嘉祥」と改め、その年の6月16日に6個のお菓子を神前に供えて疾病除けと健康招福を祈りました。
それ以降、6月16日になると厄除け・招福を願ってお菓子を食べる「嘉祥菓子」の習俗が生まれたのです。
江戸時代も、幕府は毎年6月16日に大広間で和菓子が配られていたという記録が残っています。
この故事や「嘉祥菓子」の習俗にちなんで、6月16日が「和菓子の日」として制定されました。
「洋菓子」とは

ここからは、そもそも「洋菓子」とは何かという点について見ていきましょう。
ショートケーキやプリンをはじめとした洋菓子
ショートケーキやプリンなどをはじめとした「洋菓子」。
ヨーロッパやアメリカといった、いわゆる西洋社会にルーツを持つお菓子です。
あんこやもち、和三盆を使用した「和菓子」の対となるお菓子です。
プリンや生クリームを使った洋菓子などが一般家庭に普及したのも1965年頃とされています。
これは、1964年に開催された東京オリンピックの影響ともされています。
流通や冷蔵設備が整備されていったことで、果物や生クリームなどが全国に普及したこと。
オリンピックで海外の選手が来日したことで各国の料理が注目されるようになり、レシピが広まったからともされています。
カステラは洋菓子ではない!?
カステラは、ポルトガル人によって伝わったお菓子です。
西洋にルーツがあるので、こちらも洋菓子とされるようにも思われますが、実は和菓子に分類されます。
実は、洋菓子に分類されるのは明治維新以降に西洋から伝わったお菓子やルーツとするお菓子とされているのです。
カステラが伝えられたのは、戦国時代とされていますので、明治時代よりも遥かに昔です。
そのため、和菓子に分類されるのですが南蛮文明のお菓子という意味で、和菓子の中でも「南蛮菓子」に属するとされることもあります。
洋菓子にまつわる記念日

他にも「洋菓子」にまつわる記念日はありますので見ていきましょう。
毎月22日は「ショートケーキの日」
毎月22日は「ショートケーキの日」です。
この記念日の理屈はカレンダーをみると分かります。
毎月22日の一週間前、つまり真上は15日となります。
上にイチゴ(15)が乗っているので、22日は「ショートケーキの日」になったということですね。
7月3日は「ソフトクリームの日」
1951年7月3日、東京で行われた米軍主催カーニバルの模擬店の中で日本で初めてのコーンスタイルのソフトクリームを販売されました。
この日にあやかって、7月3日が「ソフトクリームの日」とされています。
3月4日は「バウムクーヘンの日」
毎年3月4日は「バウムクーヘンの日」です。
1919年3月4日、広島で行われたドイツ俘虜展示即売会で日本で初めてドイツ伝統菓子のバウムクーヘンを販売されました。
これにあやかり、ドイツ菓子製菓会社の株式会社ユーハイムが毎年3月4日を「バウムクーヘンの日」に制定しました。
まとめ
毎年9月29日は「洋菓子の日」です。
これは、フランスで菓子職人の守護聖人とされるミカエルの祝日にちなんだ記念日となっています。