
毎年10月5日は「レモンの日」です。
この記念日は、詩人・高村光太郎の作品から来ています。
しかし、その詩には深い愛とともに深い悲しみが綴られていたのです。
っこでは、この「レモンの日」という記念日について見ていきましょう。
目次
10月5日は「レモンの日」

まずは、「レモンの日」がどのような記念日なのかを見てみましょう。
「レモンの日」の由来
「レモンの日」は、毎年10月5日です。
これは、彫刻家として活躍し、現在では詩人として知られる高村光太郎の詩集「智恵子抄」のなかの一篇「レモン哀歌」にちなんだ記念日です。
1938年10月5日この日、高村光太郎が愛した妻・智恵子が亡くなりました。
その今際の際に、智恵子が口にしたレモンのことを詩にしたのが「レモン哀歌」です。
この時、智恵子は統合失調症を患っており入院していましたが、長らく冒されていた肺結核が悪化していました。
しかし、この時高村光太郎が持ってきたレモンをかじったその時、智恵子は意識を正常なものに取り戻したのだとか。
この亡くなる数時間前の出来事が、詩の中には克明に描かれています。
「レモン哀歌」を書いた高村光太郎とは

ここからは高村光太郎という人物について迫ります。
詩人「高村光太郎」
「レモン哀歌」を書いた高村光太郎は、彫刻家高村光雲の長男です。
彼自身も最初は彫刻家として名を馳せており、芸術家として活動しました。
そんな彼は、1897(明治30)年に東京美術学校(現在の東京芸術大学・美術学部)に入学し、その後はニューヨーク・ロンドン・パリへ芸術留学をしています。
しかし、1909(明治42)年に帰国した高村光太郎は、事由の精神といった西洋的な価値観も学んできていたこともあって旧態依然とした日本の芸術会に不満を抱くとともに、日本の家長制度などにも辟易してしまいました。
そんな日本社会に絶望している中で出会ったのが、生涯愛することとなる智恵子でした。
「レモン哀歌」が載せられているのは代表作「智恵子抄」のひとつ
「レモン哀歌」が掲載されている「智恵子抄」は、智恵子が亡くなった後、1941年に出版された高村光太郎の代表作のひとつです。
この詩集は、智恵子にまつわる詩が29篇、短歌が6首、散文が3篇で構成されています。
前述の通り、智恵子抄に載っている「レモン哀歌」には、2人の結婚生活最後の様子が描かれています。
高村光太郎の命日は「連翹忌」
智恵子の命日がレモン哀歌から「レモン記念日」となっているのに対し、1956年に亡くなった高村光太郎の忌日である4月2日は「連翹忌」と呼ばれています。
この「連翹(レンギョウ)」というのは、彼がアトリエの庭に咲く連翹の花を好んでいたことから来ています。
彼の告別式でも、棺の上にその一枝が置かれていたこともあって、4月2日は連翹忌と呼ばれるようになりました。
文豪などの命日には植物の名前が付けられていることも
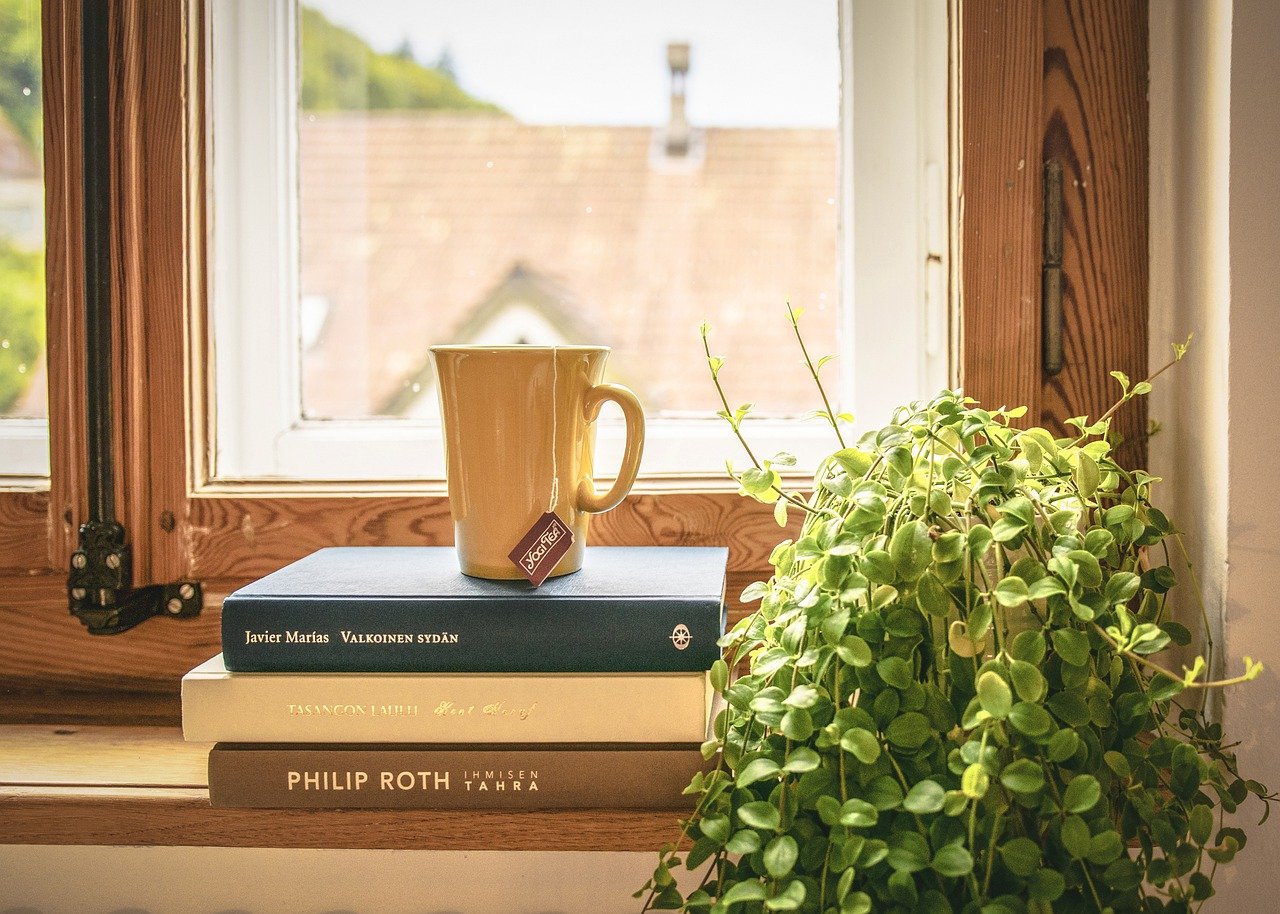
文豪などの命日には、植物の名前が付けられることがあります。
桜桃忌
6月13日の「桜桃忌」は、人間失格や走れメロスといった作品で知られる、作家・太宰治の命日です。
「太宰忌」と呼ばれることもあります。
1948年6月13日、彼は愛人の山崎富栄とともに玉川上水に入水自殺を実行します。
太宰治は、それまでにも何度か自殺未遂をしていますが、この入水自殺で命を落としてしまいました
ただし、その遺体が発見されたのは6日後の6月19日だったとされています。
この遺体が見つかった6月19日が命日として、忌日の「桜桃忌」となりました。
くしくもこの日は、太宰治の誕生日でもありました。
ちなみに、「桜桃忌」という名前は親交のあった作家の今官一が命名したもので、太宰治の短編小説「桜桃」というタイトルから来ています。
石榴忌
7月28日の「石榴忌」は、1965年にくも膜下出血のため自宅で亡くなった推理小説作家」江戸川乱歩の忌日です。
この「石榴忌」は、1934年に発表された江戸川乱歩の中編小説「石榴」にちなんで命名されたそうです。
まとめ
10月5日は「レモンの日」です。
1983年に亡くなった高村光太郎の妻、智恵子の忌日となっています。
妻を最後まで愛した高村光太郎が、死の直前亡くなる数時間前のことを綴った詩「レモン哀歌」が由来となっています。




