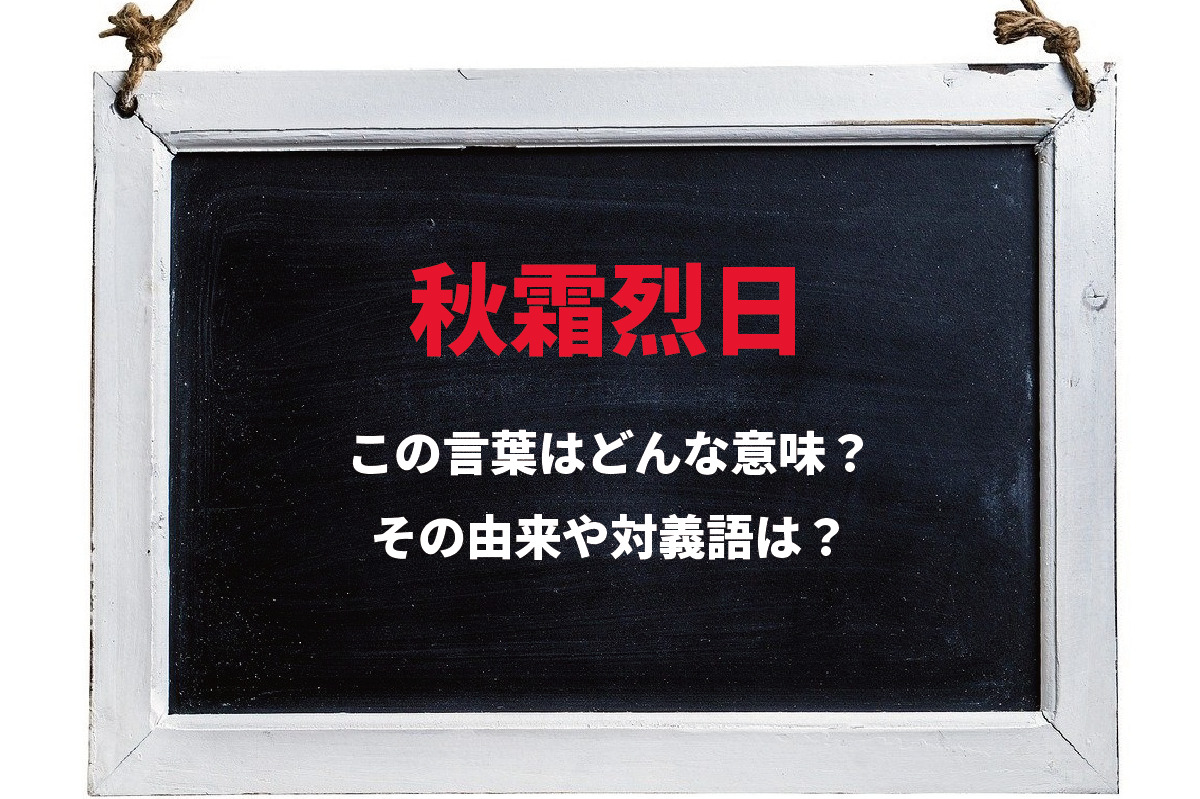
刑罰や意志がとても厳格であり激しいことを「秋霜烈日」と表現します。
これは、厳しく追及することについて指すこともあります。
これらの意味がなぜ「秋霜烈日」と表現されるのでしょうか。
そこでは、「秋霜烈日」という四字熟語についてその意味はもちろん成り立ちや類義語についても見ていきましょう。
目次
「秋霜烈日」とは

まずは「秋霜烈日」がどのような言葉なのか見ていきましょう。
「秋霜烈日」の意味
「秋霜烈日」は、権威・刑罰などが非常に厳格なことの例えとなる四字熟語です。
厳しく追及することの例えとしても使用されます。
物事をはっきりさせるといったニュアンスの含まれた言葉となっています。
「秋霜烈日」と検察官の関係性
検察官が付ける記章には、「菊の花弁と菊の葉の中央に旭日」がデザインされています。
このデザインが霜と日差しをあしらっているようにも見えることから、「秋霜烈日」と呼びあらわされるようになりました。
冷たい霜と夏の強い日差しが、厳格な刑罰やそれを担う検察官の職務を思わせうことから例えとして用いられてきました。
「秋霜烈日」の成り立ち

「秋霜烈日」は、どのようにして成立した言葉なのかを見ていきましょう。
天候を対比したことで生まれた言葉
「秋霜烈日」は、本来は秋の霜と夏の日差しを対比した言葉でした。
日本では夏の日差しには強い印象がありますが、霜は真冬の印象があり秋というイメージは強くありません。
実際、和歌などの世界では「霜」は初冬・中冬・晩冬の三冬の季語となっています。
この差は、「秋霜烈日」が中国から伝わってきた四字熟語だからだとされています。
明代の「備忘集」や、より古い時代である宋代の「新唐書」で使用されている言い回しとなります。
「秋霜烈日」の類義語

ここからは、「秋霜烈日」の類義語を見ておきましょう。
類義語としては「志操堅固」や「堅忍不抜」「雪中松柏」などがあげられます。
志操堅固
「志操堅固」とは、思考や主義などを堅く守り、何があっても変えないことの例えとなる四字熟語です。
「志操」は思考や主義などを守って変えない意志、「堅固」は特定のものを堅く守ることを意味します。
堅忍不抜
「堅忍不抜」とは一切心を乱さず、じっと我慢して堪え忍ぶことを意味します。
「堅忍」は極めて強く意志を持って堪え忍ぶことを、「不抜」は固くてまったく抜けないことを意味します。
雪中松柏
「雪中松柏」とは、意志や節操を決して曲げないことの例えです。
松や柏の葉の色が雪が降っても青々していて変わらないことから来た言葉となります。
まとめ
「秋霜烈日」は、ある物事を強く追及することを言います。
これらは志操や刑罰がとても厳格なことも意味します。
夏の強い日差しと秋の寒さから来る霜という厳しい天候から来た言葉となっています。
霜がおりる秋の寒さというのは、中国の天候から来たからとなっています。




