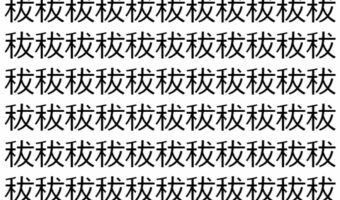「サンコウチョウ」という鳥を、みなさんはご存知ですか?
特徴的な鳴き声から名前が付けられたこの鳥は、全国的に知名度が高い野鳥ではたしかにありません。
しかし、皆さんが知っているだろうとあるスポーツチームの公式キャラクターやエンブレムとして、このサンコウチョウは採用されているのです。
目次
サンコウチョウとは

サンコウチョウとは、スズメ目カササギヒタキ科に分類される鳥類です。
鳴き声が個性的なだけではなく、その見た目もかなり特徴的だったりします。
まずはそんなサンコウチョウについて見ていきましょう。
サンコウチョウの大きさや姿
サンコウチョウは、オスもメスも似たような姿をしています。
頭部は全体を黒みがかった体毛で覆われていますが、目の周りとクチバシはコバルトブルーになっているのが特徴の鳥です。
翼や胴、尾にかけては茶色の体毛が生えており、全体を通して見ると黒と茶のツートンカラーになっています。
大きさはオスで約45cm前後、メスは17.5cm前後なので、外見的特徴こそ共通していてもオスとメスでかなり大きさに違いがあるということになります。
オスは繁殖期に向けて尾羽を伸ばすのですが、最長では体長の約3倍にまでなるので、それも含めるとオスとメスで相当な差になります。
サンコウチョウの生息地
サンコウチョウは本州から四国、九州、沖縄まで広く分布している鳥です。
平地を好みますが、低い山などにも生息しています。
普段は薄暗い森林に生息している他、市街地や住宅地でも稀に見かけることがあります。
しかし、日本にやってくるサンコウチョウの数自体が少ないため、希少性の高い鳥でもあります。
海外では主にアジアに生息しており、台湾やフィリピンなどの東南アジアまで広く分布しています。
サンコウチョウの生態
サンコウチョウは日本に5月頃の春から夏にかけて渡来し、繁殖をします。
そのことから夏鳥として認識されていますが、秋になるとマレーシアやインドネシアなどの南の方へ渡るという生態を持っているそうです。
前の項目で長い尾を持つオスと短い尾を持つメスがいると説明しましたが、南に渡る際には自分で尾羽を抜くため、尾が消失するという特性もあります。
そのため、時期によってはオスとメスの見分けがつきにくいこともあるようです。
また、食性に関しては、主に昆虫を食べて暮らしていることがわかっています。
サンコウチョウの名前の由来

サンコウチョウは、独特な鳴き声から名付けられた鳥です。
ここからはサンコウチョウの名前の由来についてご紹介します。
鳴き声から名付けられたサンコウチョウ
サンコウチョウの名前の由来となっているのは、そのユニークな鳴き声にあります。
その鳴き声は「ツキ・ヒ・ホシ・ホイホイホイ」というものです。
この鳴き声が月・日・星と聞こえることから、3つの光「三光鳥(サンコウチョウ)」と名付けられました。
これは繁殖期に鳴くさえずりで、普段の鳴き声である地鳴きは「ギィギィ」「ギーギー」というような地味なものです。
英語では「Japanese Paradise Flycatcher」
サンコウチョウは、英語で「Japanese Paradise Flycatcher」と呼ばれています。
「Japanese」は文字通り日本、「Paradise」は楽園、そして「Flycatcher」は昆虫食の鳥ヒタキのことをそれぞれ意味しています。
静岡の鳥、サンコウチョウ

サンコウチョウは、静岡県の県鳥でもあります。
静岡県の県鳥
昭和39年2月から静岡県の県鳥として、サンコウチョウが相応しいかどうかの検討が始まり、同年10月に県鳥に指定されました。
当時選定された鳥は他にもいて、ヤマドリ、セキレイ、ヒバリ、オシドリが候補として挙がっていたそうです。
これらの中から一般公募によって県民の意見を集め、サンコウチョウが一番多くの票を獲得しました。
それ以降、サンコウチョウは静岡県の県鳥として定着しています。
あの有名チームのエンブレムになっているサンコウチョウ
エンブレムやマスコットとしてサンコウチョウを採用しているのは、静岡県磐田市をホームタウンとしているサッカーチームの『ジュビロ磐田』です。
エンブレムには、サンコウチョウだけでなく、名前の由来となった鳴き声、月・日・星も一緒に描かれています。
また、チームの人気マスコットであるジュビロくんも、サンコウチョウがモチーフとなっています!
まとめ
サンコウチョウは不思議な名前の鳥ですが、その由来は「ツキ・ヒ・ホシ・ホイホイホイ」というユニークな鳴き声にありました。
見た目も結構ユニークなので、ぜひ夏になったら探してみてください。
また、サンコウチョウは静岡県の県鳥であり、ジュビロ磐田のエンブレムとマスコットにもなっています。
静岡県の方やサッカーファンの方からしたら、意外と馴染み深い存在かもしれません。