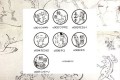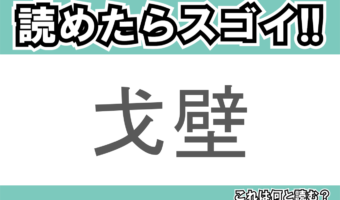黄色くてかわいい花を咲かせる「女郎花」。
その読み方は「おみなえし」です。
漢字表記と一致しないこの名前は、女郎花と対になる花が関係しているのだとか。
そこでここでは、そんな女郎花とはどういう花なのかを見ていきましょう。
併せて花言葉などもご紹介していきます。
目次
「女郎花」とは

女郎花とはどういう花なのか、原産地や開花時期について見ていきましょう。
「女郎花」の原産地
女郎花は、日本や中国、東シベリアなどにかけて分布しています。
原産地は日本とされますが、中国なども原産地の1つです。
なお、日本には約5種類~6種類ほどの女郎花があるとされています。
温暖で水はけも良く、日当たりが良い草地や手入れの行き届いた池の土手などを好む女郎花にとって日本は最適な環境に恵まれた土地とされています。
しかしその一方で、近年は地球温暖化や開発などの影響を受けている土地も多く、自生するものは減少傾向にあります。
「女郎花」の開花時期
女郎花の開花時期は、6月~10月とされています。
特に8月~9月に見頃を迎えて、10月まで咲かせます。
黄色い花を咲かせるものが一般的で、秋の七草のひとつにも数えられています。
「女郎花」は秋の七草のひとつ
女郎花は主に観賞用として人気がありますが、秋の七草の一角を担います。
ちなみに、秋の七草とされる植物は以下の通りです。
1.女郎花
2.尾花(すすき)
3.桔梗
4.撫子
5.藤袴
6.葛
7.萩
この秋の七草は、春の七草とは違い食用ではなく、見て楽しむ観賞用としての立ち位置となります。
確かに、中秋の名月に供え物にされる尾花(すすき)は、さすがに食べろと言われても無理ですよね。
女郎花も、伊勢神宮の観月会などに備えられることが多いです。
他の秋の七草も、野草ではなく花なので食用には決して適していません。
「女郎花」の名前

女郎花は、漢字だけ見てもとても読めない難読の名前となっています。
「男郎花」の対の存在として
女郎花の対となる存在として、「男郎花(おとこえし)」という花があります。
お互いが対になるのは、この2つの花の姿形がとても似ているという点にあります。
そのため、男郎花の対のそんざいということで女郎花と名付けられたとされています。
つまり、先に男郎花という名前があったということになりますね。
では、なぜ女郎花が女なのかというと、これには男郎花より優しい雰囲気があるから、という説があります。
もともとは「おとこめし」と「おんなめし」だった?
もともとは男郎花は「おとこめし」、女郎花が「おんなめし」という名前だったという説もあります。
男郎花は白い花、女郎花は黄色い花をそれぞれ咲かせます。
そこから男郎花は白米、女郎花は粟飯が連想されました。
昔は白米の方が粟飯より上で、社会的立場も男性の方が上でした。
そこから、白い花を咲かせる方を「おとこめし」と言ったといわれています。
そして、黄色い花を咲かせる方を女性に例えて「おんなめし」とされましたが、時代が下り「おとこえし」と「おみなえし」に訛化したのだともいわれています。
「女郎花」の花言葉
女郎花の花言葉は、「美人」「儚い恋」「親切」です。
これらの花言葉は、女郎花の花が秋風に揺れている姿が、寂しく悲しそうみ見えるところから来ているとされます。
ちなみに、対とみなされる男郎花の花言葉は「野性味」「慎重」「賢明」となっています。
「女郎花」は臭い?

女郎花はその見た目と名前からとても良い香りがしそうですが、実はとても臭い花なのだとか。
別名は「敗醤」
女郎花はとても臭い花で、別名では「敗醤」と呼ばれます。
これは腐敗した味噌という意味で付けられたのだとか。
この名前は、女郎花を乾かすと嫌な臭いを発することに由来しており、そのにおいは別名の通り味噌が腐ったような匂いと形容されることもあります。
また、生け花として挿した後の水が臭うからともされています。
原産地中国での名前は
原産地のひとつである中国では「黄花竜牙」と呼ばれています。
文字通り黄色い花を咲かせるため「黄花」という文字が入っています。
ちなみに中国では、「敗醤根」の名前で漢方薬にされることもあります。
まとめ
女郎花は黄色くかわいい花を咲かせます。
難読な漢字ですが、これは対となる「男郎花」という花から比較して付けられました。
漢方薬にも用いられるのですが、その際の名前は「敗醤根」と言います。
この「敗醤」もまた女郎花の別名なのですが、これは根の部分が傷んだ味噌のような臭いを発するからともいわれています。