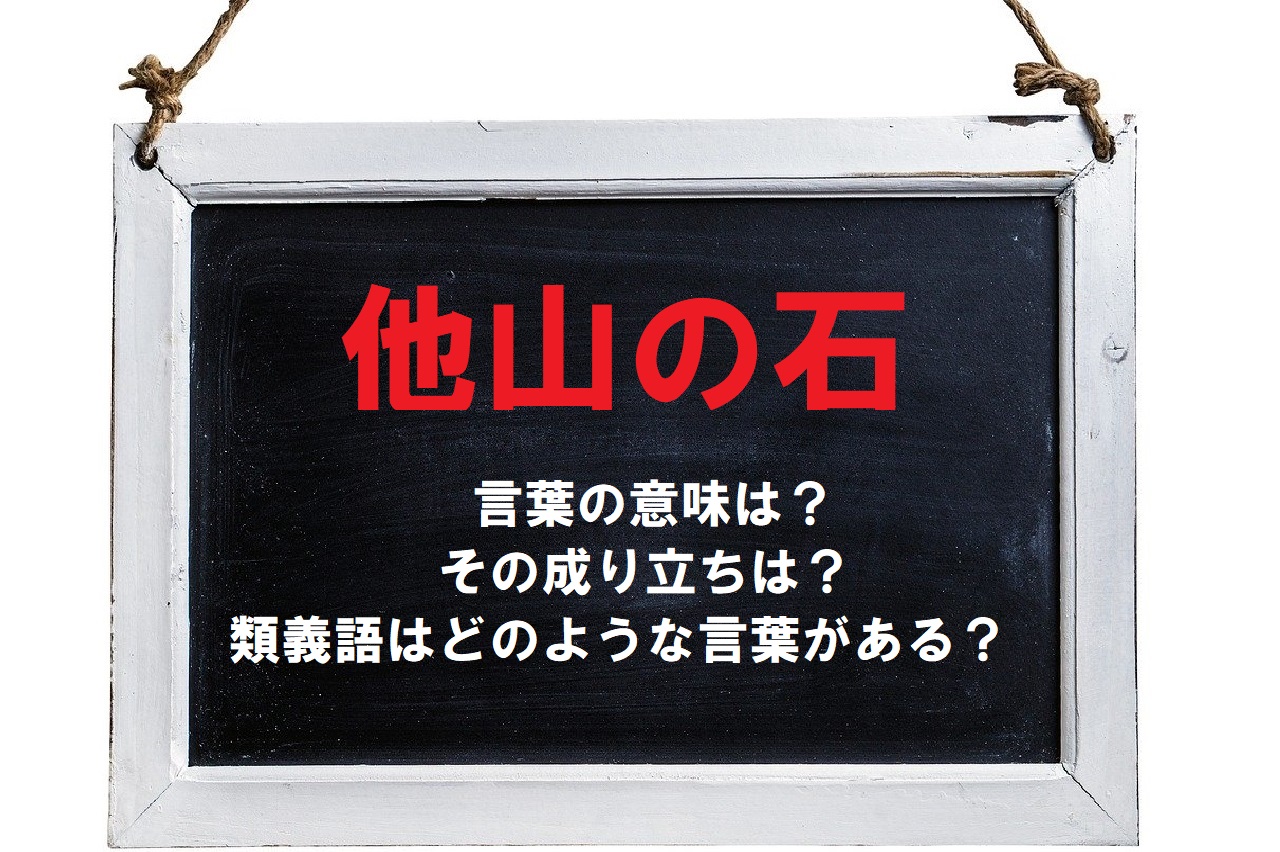
「他山の石」は、ポジティブな意味にもネガティブな表現にも使われる言葉です。
しかし、現在使われる意味合い自体は、もともとの意味とは異なる用いられ方をしています。
そこでここでは、この「他山の石」という言葉に意味や用い方、由来についてご紹介します。
目次
「他山の石」とは

まずは「他山の石」が、どのような言葉なのかを見ていきましょう。
「他山の石」の意味
「他山の石」は、他人のつまらない行動や悪い行い、自分と関係がない物事も参考にできるという例えとして使用される言葉です。
人の話や行動を踏まえて行動する際に用いられます。
近年用いられるようになった使われ方
しかし、近年ではもとの意味とは異なる用い方も多くなっています。
現在では「他山の石」を、良い物事や他人の良い行動から学びとることをあらわす際に使用されることも多くなっています。
他者の悪い行いに対して使っていたのが、いい行いに対して用いるようにシフトチェンジしてきているという事ですね。
「対岸の火事」との違い
「他山の石」と、似ているとされる表現に「対岸の火事」があります。
この「対岸の火事」とは、自分に関係がなく何の苦痛もないことの例えなので、意味は大きく異なります。
火事が発生しても、自分がいるのが大きな川などを隔てていれば被害は被りにくい環境となります。
つまり、対岸で何か事件が起きていても自分は被害者にならないだろうと、高みの見物を決め込むこともできます。
この高みの見物していられる状況を「対岸の火事」と表現します。
「他山の石」は、他人の行動などが自身に影響を与えることを意味しますが、「対岸の火事」では影響を受けることがないという大きな違いがあります。
「他山の石」の由来

ここからは「他山の石」という言葉の成り立ちについて見ていきましょう。
語源は中国の詩集から
「他山の石」は、中国の詩集「小雅・鶴鳴」の一節から来た言葉です。
他山の石、以もって玉を攻みがくべし
これが「他山の石」の語源となる言葉です。
直訳すると「山から出た宝石を、宝石の出ない別の山から取ってきた石であろうとも磨くことはできる」となります。
この言葉は最初、つまらない他人の行動や関係ない物事であっても、自分を磨くための材料になるという意味で解釈されていました。
それが転じて、直接の関係がない人物や物事からであっても学ぶことができるという例えとして広まりました。
「他山の石」の類義語

最後に「他山の石」の類義語を見ていきましょう。
類義語には「人の振り見て我が振り直せ」「人を以て鑑と為す」「上手は下手の手本下手は上手の手本」「反面教師」などがあげられます。
人の振り見て我が振り直せ
「人の振り見て我が振り直せ」は、他人の振る舞いを見て良いところは見習い、悪いところは自分の振る舞いを反省して改めよという教えです。
「他山の石」が直接自分と関りのない物事も参考にし吸収するというニュアンスがあるので、他人から学ぶという点では共通した言葉となります。
人を以て鑑と為す
「人を以て鑑と為す」は、他人の発言や行動に自分を当てはめて考え、間違った生き方をしないように慎むことです。
この言葉は「他山の石」よりも、間違っているところは是正するというニュアンスが強いです。
上手は下手の手本下手は上手の手本
「上手は下手の手本下手は上手の手本」は、下手な人が上手な人のやり方を手本にする一方で、上手な人もまた下手な人のやり方から参考になるものを見出すことを例える言葉です。
達者な人も、初心者をよくよく観察することで手間取るところや意外な疑問点から新たな発見をすることができるという事をあらわしています。
反面教師
「反面教師」とは、悪い面の見本をあらわす言葉です。
それらの行いを見て「そうなってはいけない」と学ぶ教訓でもあります。
反省すべき言動をする人物や物事に対して用いられます。
まとめ
「他山の石」は、宝石の採れない山にある粗悪な石を指していました。
この粗悪な石でも、宝石の採れる山から出た宝石を磨くことには使えます。
これが転じて、他人のつまらない言動や関係のない物事から学んで自分を高めるための表現として広まりました。
近年は他人のよい行いを吸収するという意味合いでも用いられることがあります。





