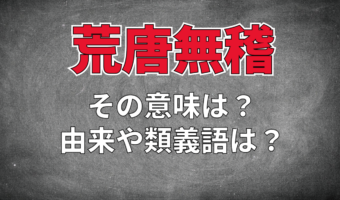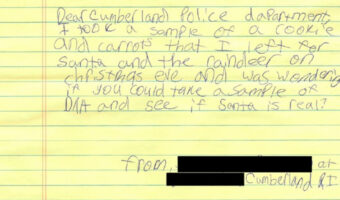「本気」や「真剣」であることを指して用いられる「マジ」という表現。
この言葉は、江戸時代から用いられていたとされています。
しかし、当時は違う意味合いで用いられていたとされます。
そこでここでは、「マジ」という言葉の意味や成り立ちについて見ていきましょう。
目次
「マジ」とは

まずは、「マジ」がどのような言葉なのかを見ていきましょう。
「マジ」の意味
「マジ」は、本気である様や、真実であることを指す言葉です。
真剣である、という意味合いでも使用されます。
「本気」という表記は当て字
「マジ」は、「本気」という漢字表記がされることがあります。
しかし、この表記は当て字となっています。
「マジ」は江戸時代には使われていた?!

「マジ」は、昭和や平成になってから使われ始めた言葉のように思えます。
しかし、実は江戸時代にはすでに用いられていた言葉とされています。
江戸時代の「マジ」の意味は・・・
江戸時代、「マジ」は楽屋言葉として使用されていました。
楽屋言葉というのは、現代で言うところの業界用語のようなものです。
その中で、「マジになる」といった用いられ方などが見られることから、当時から「真面目」さや「本気」「真剣」であることを指す言葉だったことがうかがえます。
「マジ」の語源
「マジ」は「真面目」の略語として生まれた言葉ともいわれています。
その「真面目」自体は、まばたきをあらわす「まじ」と目つき・目元を指す「目」の組み合わせから来ています。
緊張感から目を何度もまばたきさせる様子から来たとされ、その姿が誠実な態度という意味合いで用いられるようになったとされています。
ちなみに、真面目の「真面」は、意味合いから来ている当て字だとされています。
この言い回しがその後も直接使われていたわけでは無いかもしれませんが、1980年代頃に入り若者を中心に用いられるようになっていきました。
真面目というほど語っ苦しさは無いけれども、本気であることを伝える軽さも含んだ言い回しとして略した形が定着したのかもしれません。
「マジ」以外にもある江戸時代からあった意外な言葉

「マジ」以外にも、江戸時代から存在する言葉は多くあります。
ヤバい
危険な状況をあらわす「ヤバい」。
江戸時代に活躍した作家・十返舎一九の著作である「東海道中膝栗毛」で用いられていることから、1800年頃には存在した言葉とされています。
ガラが悪い人が集まる「矢場」から、犯罪に巻き込まれる危険性がある→危ない場所である→危険な状況を指す様になった、とも
牢屋の看守を「厄場」といい、「厄場」がいる場所を厄介者である囚人が忌み嫌ったことから来ているともされています。
ムカつく
現在だと腹が立つという意味あいで使用される「ムカつく」は、もともと体調が優れないことを指す言葉でした。
特に、胸やけを起こしたり、吐き気を催したりする状態をあらわしていました。
平安時代には胸焼けの意味合いで用いられていたようですが、江戸時代になった頃からは苛立ちとといった現在的な用い方がされるようになったのだとか。
ビビる
「ビビる」は、驚きすっかり腰が引けてしまっている様子に対して用いられます。
この言葉は平安時代から使われており、江戸時代に広く用いられるようになったとされています。
大軍が動き鎧が触れ合う際に鳴る「ビンビン」という音を「びびる音」と呼んでいたことから来たともされています。
まとめ
「マジ」は、「真面目」という言葉の略から来たとされています。
その意味合いも、当時から真面目さをあらわしていたとされています。
現代的な表現に思われることもありますが、実は江戸時代にはすでに使用されていた言葉です。