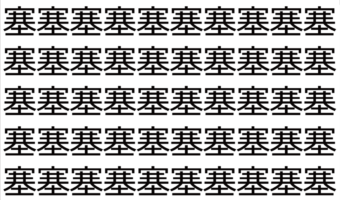平和であることの例え、それが「鼓腹撃壌」です。
直訳するとたくさん食べて腹鼓を打ち、大地を踏みながらリズムを取って楽しく歌っている様子となります。
ここでは、この「鼓腹撃壌」という言葉について、その意味や由来について見ていきましょう。
目次
「鼓腹撃壌」とは

まずは「鼓腹撃壌」という言葉の意味について見ていきましょう。
「鼓腹撃壌」の意味
「鼓腹撃壌」とは、平和であることの例えとなる四字熟語です。
人々が平穏な暮らしを送っている様子という意味でも用いられます。
善い戦時がしかれているため、飢えや戦争によって苦しむようなことのない穏やかな日常の様子から、平和な世の中を満喫していることを意味する言葉となっています。
「鼓腹撃壌」の由来

では、「鼓腹撃壌」はどのようにして生まれた言葉なのかを見ていきましょう。
由来は中国神話にあり!
「鼓腹撃壌」の由来は、「帝王世紀」や「十八史略」といった中国神話の伝説にあるとされています。
中国神話の時代、伝説の君主とされる「堯」は、数十年にわたり争いのない世を治めていましたが、実際に自分がうまく治める事ができているかが気になり、町の様子を見に行きました。
すると、街では1人の老人が満腹になった腹を打ち鳴らし、地面を踏んで拍子をとりながら、世の中は平和で天子はいてもいなくても変わらないという歌を歌っているのを目にしました。
それを見た堯は、民が政治を行う者の力を意識せずに満ち足りた生活ができていると知り安心することができました。
そこから老人の様子を描写した「鼓腹撃壌」が平和であることを指す言葉として用いられるようになりました。
成り立ちに関係ある「堯」は凄い王様だった!
「堯」は中国神話において、非常に優れた君主だったとされる人物です。
古代中国に置いては、君主の理想像とされてきました。
伝説の1つとして、10あった太陽を1つにしたというものがあります。
当時は10個もあり、地上を灼熱としていたという太陽。
そこで、堯は太陽を1つにしようと考えました。
そこで、弓の達人であった「羿」という人物に9つの太陽を射落とさせました。
見事に太陽を射落とした羿の事を起用した堯は人を見る目があると非常に高評価を得ることになったそうです。
「鼓腹撃壌」の類義語

最後に「鼓腹撃壌」の類義語について見ていきましょう。
「鼓腹撃壌」の類義語には、「天下泰平」や「尭風舜雨」、「含哺鼓腹」などがあります。
天下泰平
「天下泰平」は、天下がよく治まっていて平和であることをあらわす四字熟語です。
善政が敷かれ政治がうまく回っており、平穏な時代となります。
尭風舜雨
「尭風舜雨」とは、天下が平和に満ちていることを言います。
尭は、「鼓腹撃壌」の由来となった君主、舜はその後を継いだ君主のことです。
尭や舜のような偉大な君主による平和な世の中を恵みを呼び風雨に例えた四字熟語となっています。
まとめ
「鼓腹撃壌」は、平和な暮らしをあらわす四字熟語です。
これは、中国神話の伝説上の君主の逸話から来た言葉となっています。