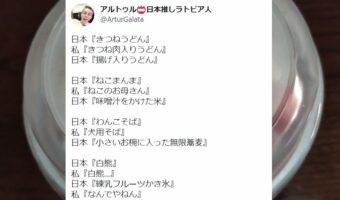世界では神として信仰させたり、もしくは神の使いとして愛され保護されている動物が多くいます。
ハヌマンラングールというサルもまた、インドではハヌマーンという神の使いとして手厚い保護を受けています。
なぜ神の使いとされているのか、ハヌマンラングールについて解説します。
目次
ハヌマンラングールの生息域と生態

ハヌマンラングールの生息域
ハヌマンラングールはインドを中心に、パキスタン、バングラディシュにネパール、そしてスリランカに分布しています。
低地から標高3500mの山岳地帯までの幅広い場所に生息し、草原や森林地帯、岩山など様々な環境に適用してします。
また、インドでは街中で見ることもあるそうです。
ハヌマンラングールの生態
ハヌマンラングールは木に登ることもありますが、基本的には地上で活動しています。
木の葉や果実を食べる植物食のリーフイーターの一種で、胃は3つにくびれており反芻的な行動を行うことで食した植物を綿密に消化する他、胃に宿っているバクテリアがセルロースを分解することで栄養を効果的に吸収しています。
長い尾をしているので食事をする際に木に登るのに一役買っていますが、地上で活動する際は長い尾は邪魔になるため尾を上げて行動します。
その際にどのように尾を上げるかは地域差があるそうです。
オス一頭に対してメス数頭の小規模な群れ、もしくはオスも複数いる数十頭規模になる群れを作って行動します。
群れを率いるオスを倒し、新しい群れのリーダーとなったオスは、倒した元リーダーのオスのこどもであるメスの連れ子を殺めるという習性があることが判明しています。
この習性は現在では他の種、ライオンやイルカでも確認されています。
1962年に世界で初めて子殺しという行為が野生下では行われているというのを確認されたのがハヌマンラングールを観察している中でのことだったことからよく知られる成体となりました。
ただし、広大なエリアの生息域と様々な生活環境の中にいるためこの習性は絶対のものではなく、例えばオスが複数等いる群れでは子殺しは行われないといったこともあるようです。
神猿ハヌマーンの使い

インドでは民間信仰が特に強いハヌマーンに似ていることから、ハヌマンラングールは神の使いとして保護されています。
神猿ハヌマーン

ハヌマーンとはインド神話と古代インドの大長編叙事詩にしてヒンドゥー教の聖典でもある『ラーマーヤナ』で活躍する神です。
風神ヴァーユと天女アンジャナーの子として生まれ、空を飛ぶことができるとされています。
一度は死亡するも不死の体と叡智を授かりよみがえったとインド神話では語られています。
一方ラーマーヤナの中では、主人公ラーマ王子を幾度と助ける作中でも屈指の強さを誇る猿族最強の戦士として描かれています。
西遊記の孫悟空のモデル?
インド神話やラーマーヤナの物語はインドから離れた中国にも伝わりました。
そして西遊記に登場する觔斗雲の術で空を舞い、超常的な神通力や最強の力を持つ猿の仙人、孫悟空のモデルになったともいわれています。
外見がハヌマーンのよう
ハヌマンラングールは灰色、もしくは灰褐色の毛をしています。
肌は黒く、体長はオスの成獣で50~80cm、尾は体長と同じかそれよりも長く、70~100cmほどあります。
尾も長いですが手足も細長く、名前の乱グールはサンスクリット語で「痩せたサル」。
ヒンディー語では「長い尾」をあらわしています。
この灰色の毛が、白猿の姿で描かれることも多いハヌマーンに似ていることから、ハヌマンラングールはハヌマーンの使いとしてインドでは愛され保護されています。
日本にいるハヌマンラングール

ときわ動物園でのみ飼育
神に使いとされるハヌマンラングールですが、日本でその姿を見られるのは現在では山口県にあるときわ動物園のみになります。
ときわ動物園の霊長類紹介「#ハヌマンラングール」
果実や昆虫も食べますが、エサの多くは木の葉。ときわでは毎日新鮮な枝葉や野菜を食べています。生息地では神様に使える神聖な聖獣として大切にされています。日本の動物園ではときわ動物園でのみ見ることができます。(3枚目:子どもの頃の姿) pic.twitter.com/d2celYKcG2— ときわ動物園(公式) (@tokiwazoo) 2019年8月20日
まとめ
ハヌマンラングールは、インドで広く民間信仰されているハヌマーンに姿が似ていることから、街中で平気で見かけることもあるほど愛されています。
日本ではときわ動物園でしか見ることのできませんが、一度神の使いといわれるハヌマンラングールがどのように過ごしているのか観察しに行きたいですね。