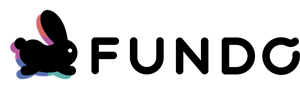数の子といえば、正月のお節料理の中の縁起物として定番の一品ですね。美しいその黄金色とパリパリポリポリ食感が相まって非常に印象深い食べ物です。
そんな数の子ですが、ニシンから取れるのになぜ「数の子」と呼ぶのか、そしてなぜお節料理に入っているのかご存じでしょうか?今回はその理由を解説したいと思います。
目次
「数の子」はニシンの卵

「数の子」はニシンの魚卵です。ニシンのメスの卵巣を腹から取り出し、天日干しもしくは塩漬けすることで完成します。
ニシンとは

ニシンは冷水域を好む魚で、北太平洋に日本海、黄海北部からアラスカにも分布しています。日本では、春先になると北海道沿岸や東北地方で姿を見ることができるようになります。
ニシンの干物は「身欠きニシン」と呼ばれ、冷凍・冷蔵技術や輸送手段が発達していなかった時代、山間部や京都などの海から遠い地域でも食べられる数少ない魚でした。
京都ではニシンそばやコブ巻きが名物としてあるのは、それだけ身欠きニシンが普及していたからだと考えられます。また、ニシンは食用だけではなく、肥料に加工されることもありました。
「数の子」の名前の由来
現在は一般的に「ニシン」と呼ばれますが、近世以前は「カド」もしくは「カドイワシ」と呼ばれていました。
そのため、数の子も最初は「カドのこども」の意味で「カドの子」と呼ばれていましたが、訛って「カズの子」になり、現在の「数の子」に転じたとされています。
子持ち昆布も「数の子」

珍味として知られる「子持ち昆布」。昆布の周りをびっしり何かの卵が覆っている不思議な形状をした珍味です。
昆布は胞子で増えるので卵を産みませんが、一体なんの卵が昆布の周りに付いているのでしょうか。
それは「ニシンの卵」つまり「数の子」です。ニシンは春になると、昆布をはじめとする海藻類の表面で産卵します。こうして昆布に産め付けられた粘着性のあるニシンの卵、すなわち数の子が子持ち昆布です。
縁起物の「数の子」

伝統的なお節料理なら必ずと言っていいほど入っている「数の子」ですが、「子孫繁栄」を連想させる縁起物とされています。
しかし、江戸時代中期以前の数の子はそれほどありがたいものではなかったようです。
おせちに入るようになったのは、日本史で習うあの人物が関わっていた!
「数の子」が現在のようにお節料理の定番になったのは江戸時代中期、8代将軍「徳川吉宗」の時代といわれています。
徳川吉宗がはじめた「享保の改革(きょうほうのかいかく)」と呼ばれる幕政改革。
これは「江戸時代の三大改革」のひとつとして数えられ、目安箱の設置から法典や行政の整備、そして蘭学の推奨などで有名ですが、実はこの改革の中で倹約も非常に重要な項目にあげられていました。
贅沢を慎むように庶民にも命じた倹約令ではおせち料理にまで口出しをしていたようで、あまりにも贅を凝らしたものは禁止とされ、貧富貴賤みな同じものを食べるように命じたとされます。
当時数の子は安価な食品だった
倹約令が出された際に、幕府側からおせちの食材として推奨されたのが、数の子・黒豆・ゴマメの三品だったのです。
当時のニシンは下魚のひとつとされており、特にその干物は庶民が食べる魚とされていました。食用だけでなく肥料にされる他、猫の餌にする魚ともいわれていたそうです。
漁獲量の多いニシンの卵である「数の子」は当時庶民でも気軽に食べられる食べ物として知られていたようですね。
春を告げる魚、ニシン

ニシンは産卵時期になると日本近海に現れ産卵をする魚です。この鵜様子から、ニシンには春を教えてくれる「春告魚(はるつげうお)」とも呼ばれています。
まとめ
「数の子」という名前は、ニシンの昔の名前「カド」または「カドイワシ」の子供の意味から訛ったものとされています。
今ではちょっとお高めの食べ物で、お節料理くらいでしかお目にかかることもないというか人も多いと思いますが、江戸時代は逆に下魚中の下魚という扱いだったそうです。今とは扱いが真逆だとは驚きですね!